生徒指導提要、読んでいますか?|武器としての教育法規(2)

教育法規と生徒指導提要の知識があると、生徒指導の方針が見えてきます。目の前にいる子どもたちと、自分の本心、学校のきまり、力のある先輩教師の方針、保護者の視線……。様々な場所で板挟みになって、何のために教師をやっているのかさえわからなくなってしまいそうな時、いつでも北極星のように正しい方向を教えてくれるものなのです。
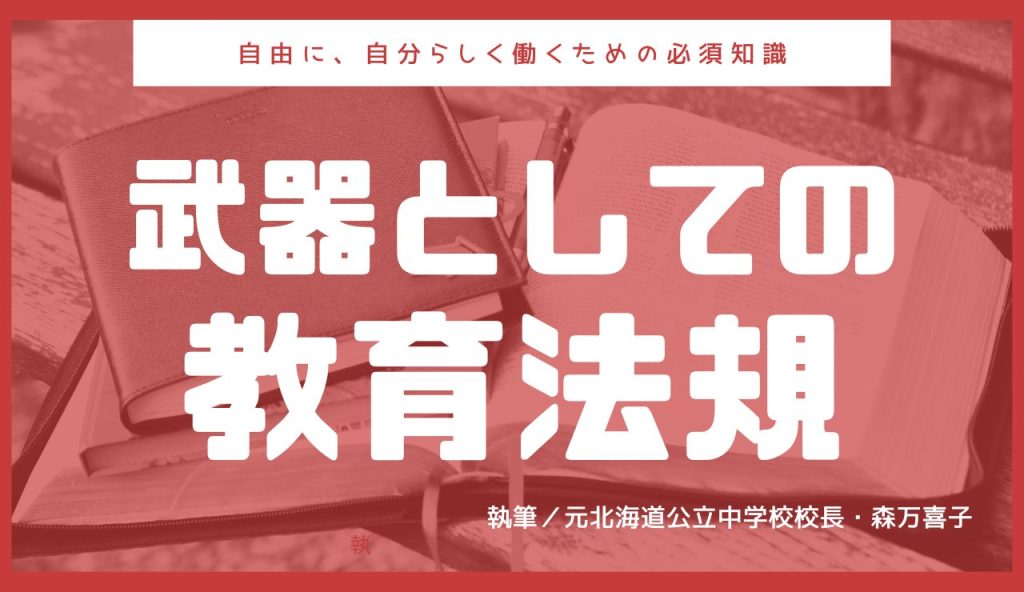

<プロフィール>
森万喜子(もり・まきこ) 北海道生まれ。北海道教育大学特別教科教員養成課程卒業後、千葉県千葉市、北海道小樽市で美術教員として中学校で勤務。教頭職を7年勤めた後、2校で校長を勤め、2023年3月に定年退職。前例踏襲や同調圧力が大嫌いで、校長時代は「こっちのやり方のほうがいいんじゃない?」と思いついたら、後先かまわず突き進み、学校改革を進めた。「ブルドーザーまきこ」との異名を持つ。校長就任後、兵庫教育大学教職大学院教育政策リーダーコース修了。
こちらもあわせてお読みください↓↓↓
管理されづらい先生になろう!武器としての教育法規(1)
目次
子どもに関する法律を尊重すると意見に筋が通る
1回目では、先生方が法律を知らないことで不利益を被る可能性があることをお伝えしましたが、逆に、先生方が子どもを相手にした時にはどうでしょう。子供に関する法律を常に尊重した行動をしていると言えるでしょうか。子どもが不利益を被っている可能性はないでしょうか。
例えば、「子どもの権利条約では、『子どもに関係のあることを決めるときはいつでも、自分の意見を持つ年齢になった子どもには、自分の考えを言う権利があります』と書いてあります。なぜ校則に対する僕たちの意見を聞いてくれないのですか」と生徒が言ってきたら、どうしますか?
こういうとき、「面倒くさいから、子どもに権利のことなんか教えないほうがいい」と思うのと同時に、「ダメなものはダメ」と言ってしまう先生が多いのではないでしょうか。そういう先生がいるから、「学校のやることに対して意見を言えない。言ったら叱られる」と思い込んでいる生徒が多く、身の回りの課題を解決しよう、社会を変えようとする気持ちが育たないのです。
これが健全な状態だと言えるでしょうか? 子どもたちが自分の考えを言えない状態を変えていくためには、まずは先生方が子どもたちに関係する法律を知っておく必要があります。
特に若い先生たちには、きちんと子どもに関する法律を学んでもらい、それもただ知識として理解するのではなくて、「それを具現化するのが学校なのだ」と知っていたほうが、仕事がしやすいのではないかと思います。
若い先生たちに知っておいてほしい法律を三つ挙げておきます。
まずは「教育の目的」からいきましょう。これは、教育基本法の第1章第1条に書いてあります。
●教育基本法 第一章<教育の目的>
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
教員は、この目的のために日々頑張っているのです。目指しているのは人格の完成です。心身ともに健康な国民を育成したいのであって、学力の高い子供を育てなさい、とは書かれていないのです。
続いて、児童憲章です。これは昭和26年に制定され、「教育小六法」の「子ども法編」の最初に書かれています。ここでは冒頭の部分をご紹介します。
●児童憲章
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。
この後、十二条の条文が続くのですが、ぜひ読んでみてほしいと思います。そこに込められた切なる願いが伝わってきて、涙がこぼれそうになります。先生たちが児童憲章のこの文言を知っているのと知らないのでは、子どもに対する見方が全然違ってくると思います。
2022年6月に「こども基本法」が成立しました。これも知っておいてほしいです。
●こども基本法
第三条四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
すべての子どもの意見を尊重する必要がある、と書いてあります。
例えば、課題のあるAくんについて、先生たち何人かで今後の対応を検討しているとします。そして、若い先生が「これまで学校がしてきたやり方はあまり効果があると思えないので、反対です」と異論を唱えたとします。
そんな場面でよくあるのは、大ベテランの先生が、「何を言っているんだ。このような子どもにはこのように対応すると決まっているのだから、黙って言うことを聞け」と言って、誰も何も言えなくなってしまうという展開。でもこの時、この法律の知識があれば、どんなにキャリアの浅い先生であっても、それではダメだとわかるはずです。
法律が示しているのは、「どうしていくのがいいと思う?」とまずAくん本人の意見を聞いて、Aくんをより良い方向へと導いていくにはどうしたらいいかと、みんなで話し合う必要があるということだからです。
もちろん、子どもの意見をなんでも尊重すればいいというものではありません。ダメなこともあります。そんなとき、学校では先生の「ダメなものはダメ」という言葉だけで済まされることが多いように思います。大人になった元生徒たちに話を聞くと、「自分たちは子どもだったけど、ちゃんと説明してほしかった」と言う人が多いのです。
子どもが言ってきた時に、「こういう理由があって、こういうことが起こるかもしれないからダメなんだよ」と、ダメな理由を先生たちはちゃんと説明する必要があります。
まず手に入れてほしい「教育小六法」
学校の先生は、経験則で話す人が多いのですが、それを鵜呑みにするのは危険です。ときに経験則は、法律を尊重していないことがあるからです。
今後、若い先生が習慣にしてほしいのは、何か行動を起こす前に、法律の原点をあたってみることです。なぜかというと、法律には定義が書いてあるからです。何のためにそれをするのかを理解して行動するのは大事なことです。そのためにおすすめしたいのは「教育小六法」を手元に置くことです。
みなさんは「教育小六法」を毎年買って読んでいますか? これは毎年買って読まなくてはいけないものです。例えば、こども基本法は2022年6月22日に公布され、2023年4月1日にこども家庭庁の発足と同時に施行されました。こんなふうに、子どもを取り巻く法律は毎年少しずつ変わっていくものなのです。
つまり、「教育小六法」の賞味期限はたった1年であることが多いのです。だからこそ、どうせ期間限定のものなのなら……と、私は「教育小六法」を”デコッて”います。使ったところに付箋を貼ったり、索引を付けたり、シールを貼ったりして、何か調べたくなったらすぐに見るようにしていました。2023年度版には、こども基本法、こども家庭庁設置法が新たに加わりました。法は社会とともに変わる「生もの」です。もし学校に何巻も分冊になった立派な教育法規集がでーんと鎮座していても、古かったら意味がないのです。

