「徹底した個への関心~一人一人の子どもを知ろう~」インクルーシブ教育を実現するために、今私たちができること #1

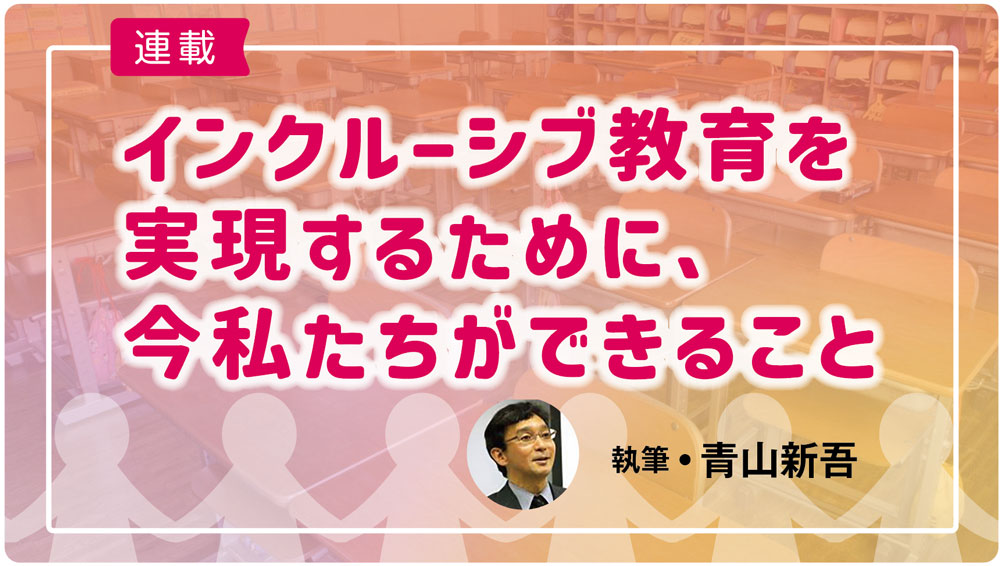
「インクルーシブ教育」を通常学級で実現するためには、どうすればよいのでしょうか? インクルーシブ教育の研究に取り組む青山新吾先生が、現場の先生方の悩みや喜びに寄り添いながら、インクルーシブ教育を実現するために学級担任ができること、すべきことについて解説します。
第1回のテーマは「徹底した個への関心~一人一人の子どもを知ろう~」です。多くの方が誤解している「インクルーシブ教育」の定義を整理したうえで、4月の学級開き時に最初にすべき第一歩について考えます。
執筆/ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長・青山新吾
目次
1.インクルーシブ教育とは?
「インクルーシブ教育」という言葉を聞かれたことがありますか? 今、急速にこの言葉、考え方に触れる機会が増えているように思いますが、読者のみなさんにとってはいかがでしょうか。
野口晃菜(2022年)は、インクルーシブ教育をユネスコが示している定義を元にして「多様な子どもたちがいることを前提とし、その多様な子どもたち(排除されやすい子どもたちを含む)の教育を受ける権利を地域の学校で保障するために、教育システムそのものを改革していくプロセス」であると定義しています。
これを読んで、「あれ?」と思われた方はいらっしゃいませんか?
この定義の中には「障害のある」という言葉が出てきていませんよね。
インクルーシブ教育とは、障害のある子どもとない子どもが共に学ぶということではなかったのかなと思われた方も多いのではないでしょうか? でも、実はインクルーシブ教育の対象は、障害のある子どもだけではないのです。
2.「インクルーシブ教育」と「インクルーシブ教育システム」は異なるもの
「そんなことはないでしょう!」
「研修で習ったことと違います!」
このように混乱されている先生方も多い気がします。そこには、次のような秘密があるのです。
我が国の文部科学省(2012年)は、「インクルーシブ教育システム」を障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要だと示しています。
お気付きになったでしょうか。そう、文部科学省は「インクルーシブ教育システム」だと言い、その対象は障害のある者と障害のない者だと述べたうえで、「インクル-シブ教育システム」を進めるためには、「特別支援教育」を充実させていこう! という考えを示しているのです。
今、我が国では「インクルーシブ教育」と「インクルーシブ教育システム」が混在し、混乱していると感じます。
野口晃菜(2022年)は「インクルーシブ教育」の対象は虐待をされている子ども、外国にルーツのある子ども、貧困状況にある子ども、性的マイノリティの子ども、障害や病気のある子ども、不登校の子どもなどのマイノリティ属性の子どもを含むすべての子どもたちであり、子どもたちが地域の学校で教育を受けることを目指していくと述べています。そう、「インクルーシブ教育」と「インクルーシブ教育システム」は異なるものなのです。
この連載では、「インクル-シブ教育」を進めることをテーマとしていきます。

