「学級じまいに絆づくりの総仕上げ」対話型授業と自治的活動でつなぐ 深い絆の学級づくり #12

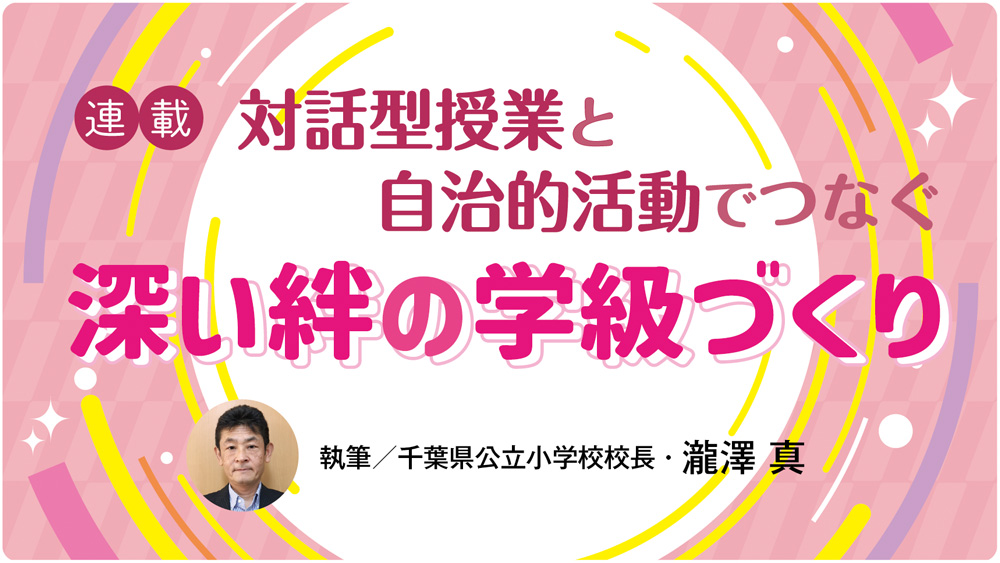
コロナ禍以降、コミュニケーションに苦労する子供や人間関係の希薄な学級が増えていると言います。子供たちが深い絆で結ばれた学級をつくるには、子供同士の関わりをふんだんに取り入れた対話型授業と、子供たちが主体的に取り組む自治的な活動が不可欠です。第12回は、学年末に行うべき最後の絆づくりについて解説します。
執筆/千葉県公立小学校校長・瀧澤真
目次
感謝すること、されることを感じられる子供に育てよう
1年間、「深い絆の学級づくり」について連載してきました。今回はいよいよ最終回です。
学年末に今さら学級の絆を深めても……と思うかもしれません。しかし、人との絆を深める経験は、子供たちがこれからの人生を生きていく上での糧になるのではないでしょうか。そして、我々教師の仕事はそうした、種まきをすることなのではないでしょうか。
ですから、最後の1日まで、子供たちが人との絆を深めるような機会を設けていきましょう。
さて、改めて根本的なことを考えてみましょう。人と絆を結ぶために必要なことは何でしょうか。いろいろとあるとは思いますが、その中で特に重要なのは、人への信頼ではないでしょうか。
この仲間は信じられる、この人なら頼ることができる。そういう他者への肯定的な感情をもっている人は、様々な人と絆を深められるでしょう。これは、その逆を考えると、より明らかです。人間不信な人が、他者と絆を深められると思いますか。
他者への肯定的な感情を育むために有効な手立ての1つに、「感謝」があります。
自分は1人で生きているのではない、他者によって支えられているのだと「感謝」の気持ちをもつこと。また、自分が他者の役に立っていると「感謝」されること。この両面の感謝を感じることができれば、相互の信頼感が高まっていくのではと思っています。
そこで、まずは「感謝」の意味について考えます。
まずは「ありがとう」について考えよう
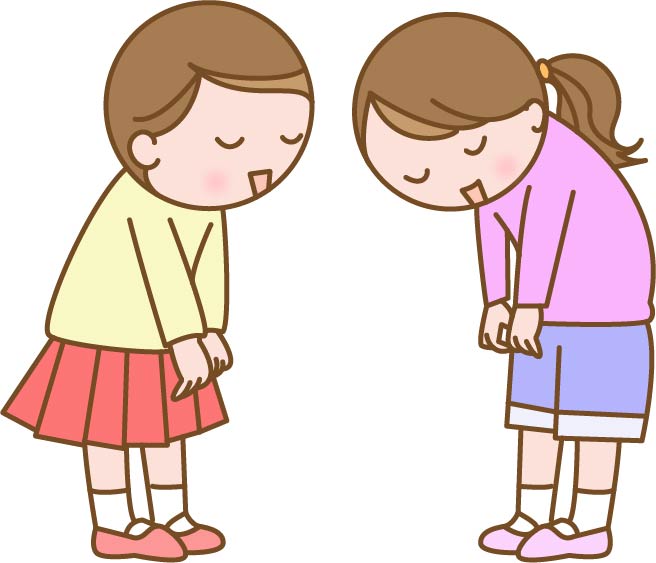
人に感謝するときに使う言葉は何でしょうか?
学級の子供たちに、このように問いかけます。子供たちは、「ありがとう」だとすぐに分かります。
では、「ありがとう」を漢字でどう書くのか聞きましょう。これは難しいので、すぐに答えを教えます。
(板書し)「有り難う」ですね。
担当学年によってはまったく読めない字もあるでしょうが、そのまま示します。
次に、この言葉を解説します。
「有り難う」というのは、「有り難い」という言葉からできた言い方です。有り難いというのは、「有るのが難しい」ということで、その意味は、「それは当たり前ではない、難しいことだよ」ということです。
例えば、友達が君の落としたものを拾ってくれたとします。友達が君の落としたものを拾ってくれるのは当たり前ですか? 違うよね。わざわざ他のことをやめて拾ってくれたんじゃないかな。だからそんなに簡単なことではない、当たり前じゃない、有り難いこと。そこで、君は「ありがとうございます」と感謝を伝えるんだ。
君が当たり前だと思っていることでも、よく考えたら、本当は感謝しなければいけないことがたくさんあるのではないかな。そういうことを探して、たくさん「ありがとう」を言いたいね。
こんな話をしてから、次のことに取り組みます。

