専門となる教科や領域を極めるには?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #12

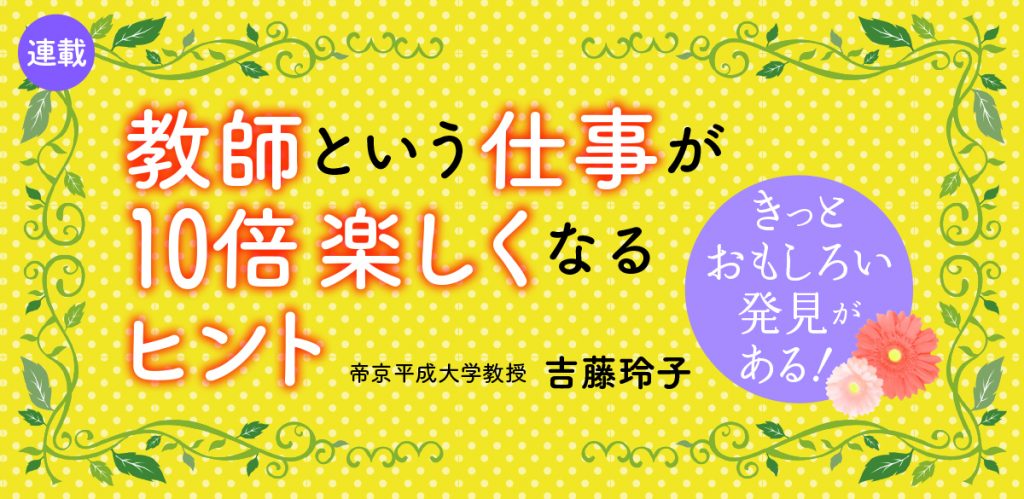
教師という仕事が10倍楽しくなるヒントの12回目のテーマは、「専門となる教科や領域を極めるには?」です。教師の本領は授業です。授業がうまくなるには教師各人の勉強が欠かせません。専門となる教科や領域を極めていくことを通して、すばらしい教師人生が拓けるはずです。どのようにして勉強するとよいのでしょうか。その勉強の仕方の様々な方法が分かります。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等、様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
授業が学級をつくる!
教師になると、子供が言うことをきかない、クラスがまとまらない、思うような関係が子供とつくれないなどいろいろな悩みがあります。特効薬はありません。まず、日々の授業をしっかり行うことに取り組みましょう。1日6時間子供たちは授業を受けているわけですから、その中に「おもしろい!」「楽しい」と感じる授業があれば子供との人間関係は変わってきます。
授業がうまくなるのは一朝一夕にはいきません。そこには教師一人一人の勉強が必要になってきます。各自治体や学校では、月に1回研究日を設け、午後の授業をカットし、教師が学習できる研究会を設けています。毎月の区の研究会に、みなさんは参加していますか? 全教師が必ずどれかの教科に属しますが、授業がカットされて時間が空いたのだから、わざわざ他の学校へ研究授業を見に行かず、「学校に残って仕事をしたいな」と思ったことはありませんか? でもこの研究会が教師には大切なのです。そのため、各自治体が力を入れて計画しているのです。
なかなか自分でインターネットを調べたり書籍を読んだりしていても授業はうまくなりません。授業を見て、体験し、教師の子供たちへの問いかけや子供の反応を見て、その教科を長年勉強している講師から話をうかがい、授業のノウハウを学んでください。
私は、教師生活のほとんどを社会科の研究会に所属し、勉強してきました。しかし、最初から社会科に興味があったわけでなく、どちらかと言えば教えるのが苦手な教科でした。その教え方を学びたいと思い、社会科の研究会に入ったことが社会科を専門にしたきっかけでした。今、大学で社会科を教えていると、学生たちの最初の反応として、社会科は覚える教科、暗記教科なので嫌いでしたという声が多いのです。しかし、講義を通して、教材づくりや授業の進め方、子供が主体的になる活動などをいっしょに学んでいくと、社会科がこんなにおもしろいとは思いませんでしたという感想に変わります。
今回は、社会科という1つの教科を通しての授業づくりのおもしろさについて話します。

身近なことから教材を見付ける
スーパーマーケットのチラシ
私たちの生活を囲んでいるすべての事象が社会科につながります。例えば、スーパーマーケットのチラシ1枚からでも消費者の立場、売り手の販売者の立場に気付くことができます。
売り手は、季節の物やセットメニューを載せて、できるだけ多くのお客さんにスーパーマーケットまで足を運んでもらおうと考えます。買い手の消費者は、値段や製品、安売りセールの日時などに着目して、スーパーマーケットに行くかどうかを考えます。1枚のチラシの情報から考えられることがたくさんあります。
史跡の説明版
街中にある区や都が立てている史跡の説明版も教材になります。昔、ここにどんな施設や誰の住居があったかなど勉強になります。私が勤務する大学へ中野駅から向かう途中に犬のモニュメントがあります。生類憐みの令で有名な徳川家五代将軍綱吉のとき、この地に巨大な犬屋敷があったそうです。江戸城からかなり離れている中野ですが、徳川の史跡があり、頭の中でタイムトリップしてちょっと想像してみると楽しくなりませんか? このように通勤途中でも毎日目を凝らしているといろいろな発見があります。社会科の学習では、教師が日常生活と関わらせてどのように教材を見付けていくかが大切になってきます。
ゴミのゆくえ
人々の健康や生活環境を支える事業の学習で、廃棄物を処理する事業として生活の中から出るゴミのゆくえについて考えるときに、小学校であれば、出したゴミがまだ残っている時間に実際に学校の周りを歩かせてみたり、ゴミ収集車がゴミを回収している様子を見せたりすることもよいでしょう。毎日の掃除の時間に各教室から出るゴミを、子供たちが学校の中のゴミ捨て場に捨てに来る様子を動画に撮って授業で紹介してもよいかもしれません。私たちの生活は毎日大量のゴミを排出していることが実感できます。
私は、コロナ禍から自動販売機に付随して設置されているゴミ箱に注目してきました。感染症の拡散を防ぐため、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで外に置いてあったゴミ箱が店内に配置換えになりました。
すべての自動販売機の横にゴミ箱が設置されているわけではありません。最近は、すごく減りました。それはなぜかというと、関係ないゴミがゴミ箱に捨てられて、ゴミの処理が大変だからです。このゴミの回収は、公共事業でなく、自動販売機を設置した会社が回収しているのですが、自動販売機の飲み物の売り上げと関係なく、いつもゴミ箱がゴミの山になっているのは、商業地などの街角をちょっと見れば分かります。
世界の他の国々に比べて、日本は非常に自動販売機が多く設置されている国です。その数に外国人は驚きます。しかし、今、自動販売機で飲み物を買っても、捨てる場所がないのです。そのような小さなことにも着目してみると、社会の問題が少し見えてきます。
戦争を考える
生活の中の問題だけでなく、この数年はウクライナやガザ地区の問題、台湾有事など、平和な日本でも決して戦争が自分たちと関わりのないことだとは言い切れなくなってきている状況があります。私の叔父は、学徒出陣で海軍に入り、終戦の年の7月に亡くなっています。その叔父の遺品として我が家には奉公袋があり、その中に叔父の大学や高校の学長や先生たち、その他の人々が寄せ書きをした2枚の日の丸の旗が残っています。今、私が教えている学生と同じ年の人たちが若くして命を絶った時代があったということ、この日の丸の旗を見せ、戦争に関する動画、自分が訪ねた平和祈念館などの資料を用いて、戦争について考えさせる授業を行いました。
学生からは「戦争については反対だけれど、それはよくないことと言い切ってしまっては、徴集されて亡くなった人たちが報われないと思う。なぜ、戦争が起きたのか、どうして防げなかったのか、考えていくことが大切だ」という意見が寄せられました。「女子学生は戦地へ行く人たちを見送っていた。もし自分の子供がそこにいたらやるせない。自分が教師になったら、いろいろな立場の人の思いを歴史の授業のなかで子供たちに考えさせたい」という女子学生の感想もありました。
自分ごととして問題を考えたとき、そこには、主体的な学習意欲が生まれてきます。教材研究というのは自分のためにすることももちろんですが、どうしたら、子供たちが主体的に学習に取り組めるかを考えて準備することが大切です。ぜひ皆さんも街中を歩いて気付いたことやニュースや新聞から分かったことなどをアレンジして教材づくりをしてみてください。

