第59回 2023年度 「実践! わたしの教育記録」特別賞作品 上村洸貴さん(長崎県立長崎北高等学校教諭)
生徒と創り、広める「教育×ChatGPT」の可能性と学びの個別最適化に向けた取組
~生徒・教師・AIの三位一体で目指す教育の質の向上~
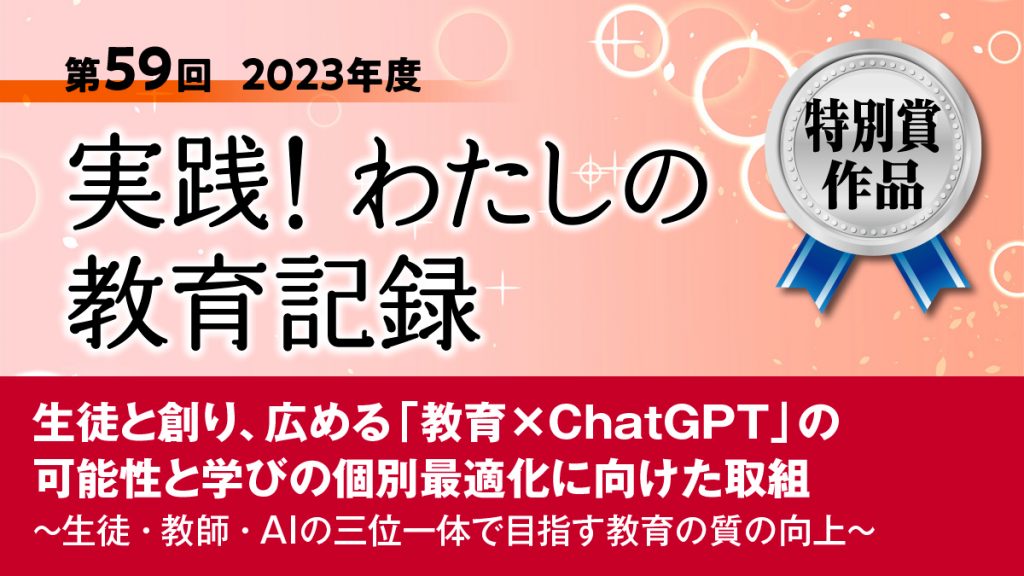
目次
1.はじめに
私は前職でIT企業に勤務していた際に日本の教育の在り方に疑問を抱き、ITを活用して教育の質を高めることができないかと考え、教職に転職した。それ以来、本来生徒が学びたいことや最適な学び方など、学習ニーズは異なっているにも関わらず、一斉授業や一斉宿題といった画一的な授業に終始してしまっている自身の指導の在り方に大きなもどかしさを感じてきた。
画一的な学びを脱却して、いかに個別最適な学びを実現するかという壁は、教育者であれば誰もが一度はぶつかるものではないだろうか。本実践では、その解決策の一つとしてChatGPTを活用し、個別最適な学びの実現に取り組んできた。
ChatGPTの真骨頂は学びの個別最適化の促進と、的確な助言によるメタ認知及び学習意欲等の非認知能力の向上にあり、ひいては学びの格差を是正する装置にもなり得ると考えている。そして、活用を進める上で最も大切にしているのは「AIの賛否」や「AIか人間の教師か」といった二項対立ではなく、その中間地点にこそ最適な教育の姿があると考える「グラデーション思考」である。
本論では、以上の考えに則って進めている具体的な活用実践や適切な活用を促すためのルールメイキングの授業、そして今後の懸念点及びその解消に向けて取り組んでいる活動について詳述したい。
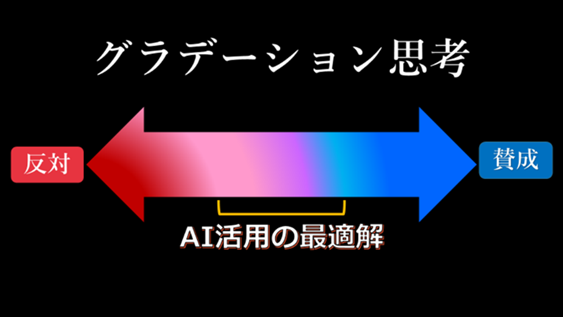
2.ChatGPTで解決を目指す教育課題
(1)知識伝達型の授業からの脱却
担当科目である英語においては、英語の「言語」としての側面よりも大学入試等で正解が求められる「科目」としての側面が重視され、そのことが生徒の学習意欲や自己肯定感の低下を招いている実情に課題意識を抱いてきた。それに加えて私自身の指導力不足や昨今の教員不足の問題も相まって、個別最適な学びを実現できずにいた。
(2)地域と経済的格差に紐づく教育格差の是正
本県のような地方都市に住む生徒は、地理的・経済的な制約から学習塾や家庭教師といった学校外教育の恩恵を享受することが難しく、それが教育格差拡大の一因ともなっている。そこで、生徒がChatGPTを効果的に使いこなすことができたら、24時間365日質問ができる「近未来の家庭教師」として、生徒一人ひとりの学びに伴走する存在になるのではないかと期待している。
(3)学校での学びと実社会の課題の”距離”の縮小
生徒を主語に捉えた際、学校で得た知識や学びがどのように社会と繋がっているか、どのように社会で活かせるのかが生徒にとって分かりづらいことも、現行の教育の課題の一つではないかと捉えてきた。そこで、どうすれば学校の学びと実社会を近づけ、社会の諸問題に対して生徒の当事者意識を育むことができるかということも視野に入れる。

