菊池省三の「コミュニケーション力が育つ教室づくり」 #37 菊池省三解説付き授業レポート⑧ ~香川県東かがわ市立大内小学校5年1組 <前編>

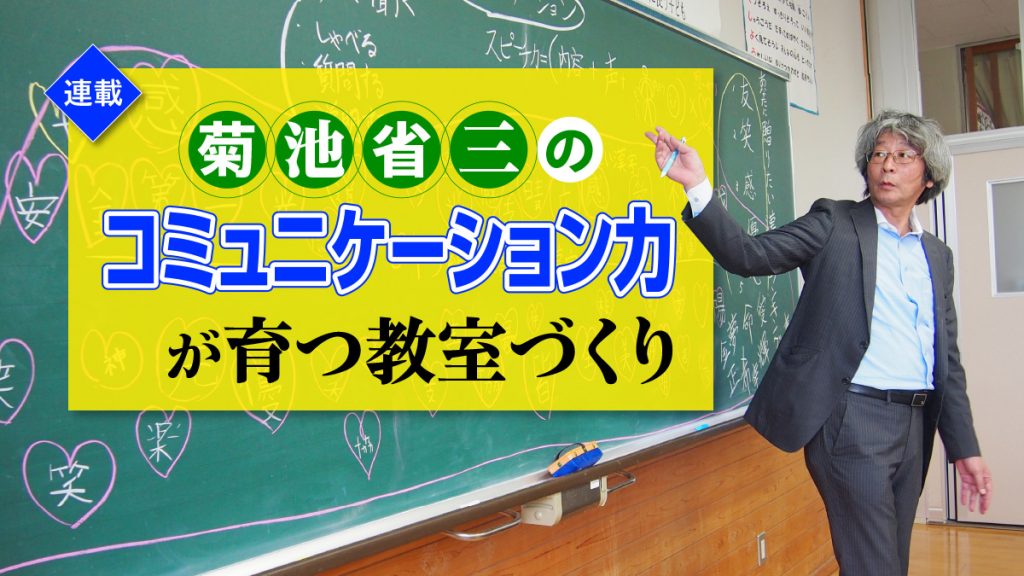
全国各地での飛び込み授業を、菊池先生ご自身の解説付きでレポートする好評シリーズ。
今回は、東かがわ市立大内小学校の5年生に対する授業レポートです。
学級崩壊立て直し請負人・菊池省三の「子供を見る目」を学びたい方、必読の連載です。
目次
スピード展開で、子供たちは一気に集中
「5年1組のみなさん、こんにちは! さっきみなさんの4時間目の授業を見ていたんだけど、めっちゃよかったので、そのことを早く黒板に書いてもいいかな?」
菊池先生がそう話しかけると、子供たちは興味津々の表情で「いいよ!」と元気よく答えた。
「じゃあ、本気の拍手で迎えてもらえる? 本気の拍手というのは、指の骨が折れるほど大きな拍手のことだよ」
菊池先生が教室に入ると、みんな笑顔で本気の拍手で迎えた。
教室に入るなり、菊池先生が黒板の左側に行き、<成長>と書いた。
「読める人いますか?」
「せいちょう」と何人かがつい口に出してしまった。菊池先生はそれをスルーし、黙って手を挙げている子に向かって、
「早いなあ」
とほめた。
「手を挙げるというのは、中指の爪の先を天井に突き刺すことなんだぞ」
菊池先生がそう話しながら、挙手をしていた女子のところまで歩いていき、その子を指名した。
発言しようと女子が席を立つと、
「みんな、拍手の準備をしているか?」
と菊池先生。子供たちがさっと両手を合わせてスタンバイした。
「せいちょう」
「はい、大きな拍手!」
子供たちの拍手が教室に響いた。
黒板に書いた<成長>の文字の下に、菊池先生が<生長>と書き加え、説明した。
「生長は、草や木や虫のせいちょう、こっちは人間のせいちょうを言います。成長を目指す人は、やる気の姿勢を見せましょう」
子供たちがぴしっとした姿勢になった。
「今日4時間目の授業を見て、みなさんの<成長>を感じました。5時間目も、一緒に成長していく授業にしましょう」
菊池先生がそう話すと、子供たちの姿勢がさらにぴしっとなった。
![]()
昼休みが終わった5時間目の授業、周りに先生や見知らぬ大人が授業を参観している様子に緊張しているのか、教室がざわざわと落ち着かない様子でした。 このまま授業に進むと、次のようなマイナスの行為をする子が出てきます。
●後ろの子とおしゃべりをする
●手遊びをする
●机に突っ伏す
●水筒の水を飲み始める
●奇声を上げる
●下品な言葉を発する
●髪をとかす
こうした行為は、授業が進むにつれ、さらなるマイナスの行為につながっていきます。
●教科書やノートを出さない
●発問しても、挙手しない
●グループの話し合いに参加しない
そうなってしまっては、教室での学びが共有できず、授業が成立しません。
教室がざわついていたら、マイナスの空気を素早く変えてしまうことが大切です。
教室に入る前の声かけから、<生長>の説明まで約2分。子供たちの関心を引きつけて一気にたたみかけ、「みんなで学ぶ」空気を教室につくりました。
学びにふさわしい教室の空気を、子供自らが感じる
「今日は、ある人について勉強します。知らなくてもかまいません。30人の誰かが知っているかもしれないから、知らなくても安心しましょう。『見たことある・名前を知っている』人はやる気の姿勢を見せましょう」
菊池先生が一枚の写真を見せた。
「この人の名前を知っている人?」
4、5人が手を挙げた。
手をぐるぐる回して挙げている子に対して、
「みんな見て見て。『当てて、当てて!』とアピールする彼のやる気!」
と菊池先生が言うと、みんな大爆笑。
「じゃあ、君に答えてもらいましょう。この人は誰ですか?」
「栗山監督」
男子が答えると、菊池先生がその子に歩み寄り、握手しながらみんなに話しかけた。
「いい教室だね。さっき、先生がみんなに写真を見せたとき、あちこちで『栗山』『栗山』というつぶやきが聞こえました。けれども、彼は『栗山』と言わずに、『栗山監督』と言いました」
菊池先生が黒板に戻り、<公>と書いた。
「教室はみんなで成長する場所。公の場です。公にふさわしい、『栗山監督』という答え。公の言葉を使ったり、公にふさわしい態度、行動、仕草、振る舞いをしたりすること。彼は公にふさわしい言葉を使いましたね」
「栗山」と勝手につぶやいていた教室がシーンとなった。
そこですかさず菊池先生が、
「ここで拍手!」
と声をかけた。すると、みんなが笑顔に戻って、大きな拍手をした。
![]()
勢いづいて手をぐるぐる回した行為を「やる気の表れ」というプラスの視点で子供たちに示す。
「公の言葉を使ってすごいね」とほめることで、学びにふさわしい言葉づかいに気付かせる。
「きちんとした言葉づかいをしなさい」と言わなくても、何人かの鋭い子供たちは感じ取ります。感じ取った子供たちが次の発言から実行したら、またそれをほめる。
この繰り返しによって、学びにふさわしい空気が教室に広がっていきます。このような指導は、集団の中でこそ、生きてくるのです。

