学校の存続をかけて地域を巻き込むには?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #6

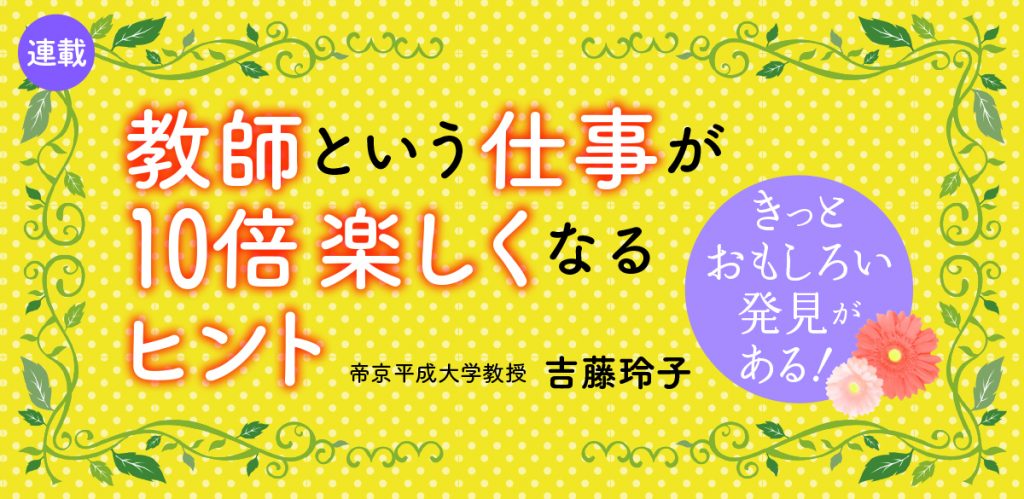
教師という仕事が10倍楽しくなるヒントの6回目のテーマは、「学校の存続をかけて地域を巻き込むには?」です。児童数を増加させることが課題の小学校に赴任し、統廃合の危機をどのように乗り越えたか? 地域を巻き込み、魅力ある教育活動を実践して児童数の増加につなげるコツが分かる話です。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
地域の人たちと仲よくなるには
地域シリーズの3回目です。できるだけ地域に関わり、地域と共に教育活動をしたいと考えていた私ですが、縁あって教員生活最後の学校は、自分が生まれ育った地域に戻ってくることができました。これは幸運なことでした。地域行事はどうしても土日になることが多いものです。自宅が遠いと、なかなかすべての行事に参加することはできませんが、私の場合、自宅と勤務地が近くなった分、管理職として様々な行事に積極的に関わることができました。
今、あらゆる行事がコロナ禍前に戻りつつあります。祭りに盆踊り、餅つき大会、駅伝など。確かに休みの日に地域行事に参加するのは大変ですが、教員の場合は、交代でよいので、できるだけ参加してみるとよいと思います。学校とは違った子供たちの顔を見ることもできるし、保護者や地域の人たちとも仲よくなれます。その関係で自分が困ったときに味方になってもらえる場合が多々あります。「大変だ!」と決め付けないで地域と関わってみてください。


