有名ミドルリーダーが推薦!若手教員が読むべき夏の課題図書2023



もうすぐ夏休みですね。日々、子供と向き合ったり、授業計画や教材開発に追われたりしている若い先生たちにとって、夏休みは絶好の学びの時期だと思います。スキルアップのために、様々な研修やこれまで手を付けられなかった読書を計画している先生も多いことでしょう。
そこで、本サイトでも多数の読者をもち、第一線で活躍している樋口綾香先生、鈴木優太先生、丹野裕基先生の3人に、この夏、若い先生方に読んでほしい3冊を推薦していただきました。

目次
樋口綾香先生のおすすめ3冊

【ひぐち・あやか】大阪府公立小学校教諭。Instagramでは、@ayaya_tとして、♯折り紙で学級づくり、♯構造的板書、♯国語で学級経営などを発信。著書に『「自ら学ぶ力」を育てる GIGAスクール時代の学びのデザイン』(東洋館出版社)、『子どもの気づきを引き出す!国語授業の構造的板書』(学陽書房)ほか。編著・共著多数。
【1】『眠れなくなるほど面白い 図解ヤバい心理学』神岡真司監修(日本文芸社)
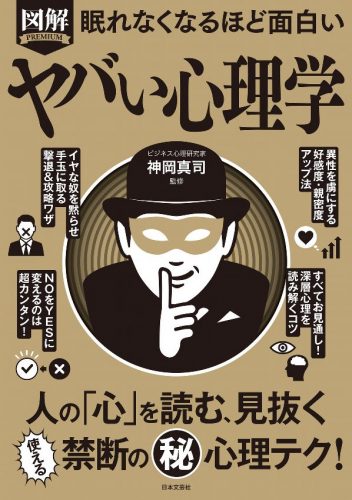
本書は、人のしぐさや口癖からその深層心理を読み解くコツだけでなく、人を思い通りに動かすテクニックまで書かれています。特に薦めたいのは、「学級経営や保護者関係で悩んでいる人」「職員室の雰囲気をよりよくしたい人」「効率的に仕事を進めたい人」です。
人間関係におけるヒントがたくさん詰まっています。本書を読んでいると、「こう言えばよかった」や「確かに、自分はこういうことをしているな」と、自分自身の言動を振り返る機会を得ることができます。
【2】『まんがで知る デジタルの学び2 創造的な学びが生まれるとき』前田康裕(さくら社)
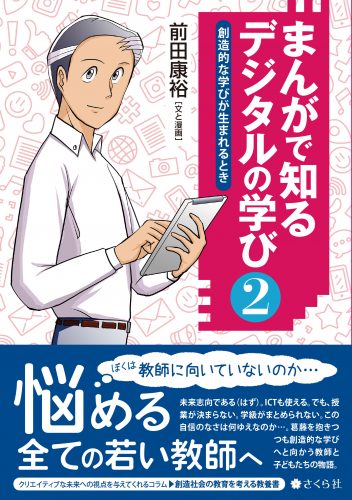
「令和の日本型教育」「個別最適な学び」「協働的な学び」…急速に進む情報化社会の中で、教育の世界でも新しい言葉がどんどん増えています。新しい言葉を知り、自分の教育観に落とし込んでいこうとすると、多くの時間を要します。
本書は、今の時代の教育がどのような流れの中で生まれたのかや、新しい教育観の根底で大事にすべきことを分かりやすく教えてくれます。登場人物の名前が癖強めで、人物像が容易に想像できることも、内容を理解する手立てになっています。
【3】『増補改訂版 国語力をつける物語・小説の「読み」の授業』阿部昇(明治図書出版)
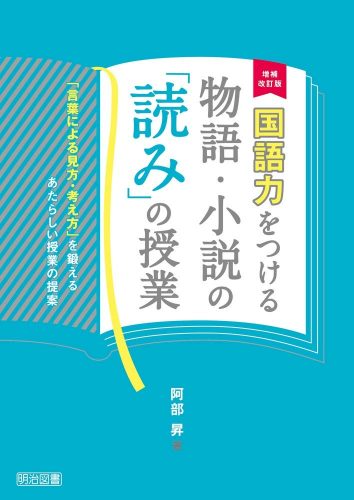
私が国語授業のおもしろさにどっぷりとハマるきっかけをくれた3冊の本のうちの1冊です。ちなみにあとの2冊は『文学の授業づくりハンドブック』(溪水社)と『白石範孝の国語授業の教科書』(東洋館出版社)。どれも教材を深く読む方法と授業づくりについて教えてくれる本です。
本書は、筆者が国語教育について考えるときの「目的論」「内容論」「教材論」「指導過程論」「授業論」の5つの枠組みのうち、「内容論」と「指導過程論」について書かれています。読みの3つの指導過程「構造読みー形象読みー吟味読み」は、教材を深く読むヒントになり、具体的な教材と授業実践についても詳しく書かれているため、読むとすぐに実践したくなります。
鈴木優太先生のおすすめ3冊

【すずき・ゆうた】宮城県公立小学校教諭。1985年宮城県生まれ。「縁太(えんた)会」を主宰する。『教室ギア55』(東洋館出版社)、『「日常アレンジ」大全』『学級づくり&授業づくりスキル レク&アイスブレイク』(明治図書出版)など、著書多数。
【1】『精神科医が見つけた3つの幸福 最新科学から最高の人生をつくる方法』樺沢紫苑(飛鳥新社)
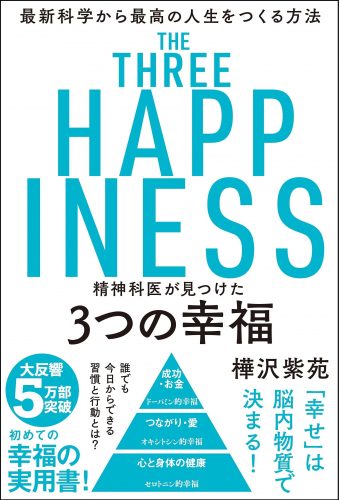
「幸せ」になりますように! 私たち教師が、縁あった子供たちに願うことです。「幸せ」とは、人それぞれでつかみどころがないものだと思っていました。しかし、精神科医の著者は、「幸せ」の正体は「3つの脳内物質」と言い切ります。
①セロトニン……健康
②オキシトシン…つながり
③ドーパミン……成功
セロトニン、オキシトシン、ドーパミンが十分に分泌されている状態が「幸せ」です。この「3大幸福物質」が分泌される条件が「幸せになる方法」です。「健康」「つながり」「成功」を感じられる幸福度の高い教室で、子供たちと共に過ごしたいものです。私たち自身も「幸せ」になりますように!
オーディオブックの聴き放題で3度聴き、結局書籍も購入したのが本書です。
【2】『学級経営がうまくいくファシリテーション』阿部隆幸・ちょんせいこ編著(学事出版)
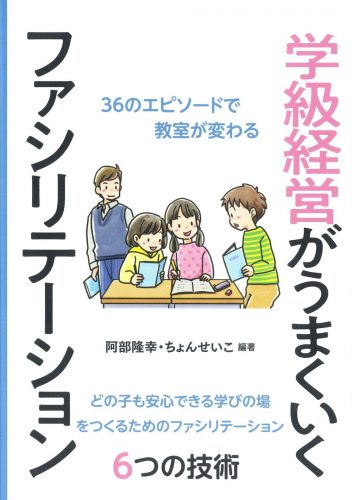
主体的・対話的で深い学び、個別最適な学び、協働的な学び…これからの学級経営には、学習者の気付きを促す「ファシリテーション」が欠かせません。
ちょんせいこさんが体系化した「ファシリテーションの6つの技術」があります。
①インストラクション
②クエスチョン
③アセスメント
④グラフィック&ソニフィケーション
⑤フォーメーション
⑥プログラムデザイン
この6つの技術が、現役実践者たちのエピソードによって、まるで動画のように鮮明にイメージできるのが本書です。阿部隆幸先生による学級経営の研究的視点からの解説と共に、「よくある失敗例」が掲載されている点も読者に優しいです。実践と研究が融合した最新・最強のファシリテーションスキルを学べる必読の1冊です。
【3】『動物キャラナビ[バイブル]』弦本將裕(集英社)
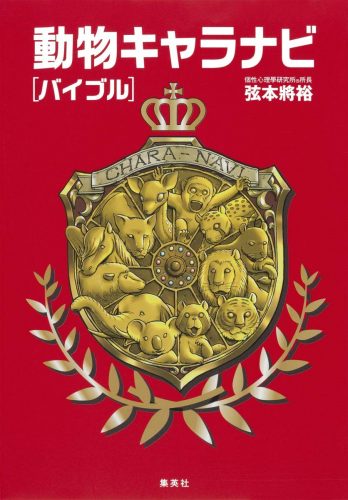
春休み、一緒に学年を組む先生方とこれで盛り上がって距離が一気に縮まりました。生年月日から60の動物キャラクターに分類する……、そうです! 動物占いです。
「自分と他の先生は違うのだ」と思えたほうが、私たちはお互いを素直に認め合えるようです。自分や他者の「強み」を知ることは、よいパフォーマンスで仕事をするためには必須です。これは違うかなと思う分析もあるでしょうが、それがまた自らの「強み」を顕在化するきっかけになります。
子供のトラブル予防や対策にも活用できます。通信表のヒントにもなるでしょう。
アプリ(動物キャラ診断は無料)を試してみるのも楽しいです。ちなみに、私は「強い意志をもったこじか」です(笑)。

