ほめ方、𠮟り方について教えてください(後編)【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#10】

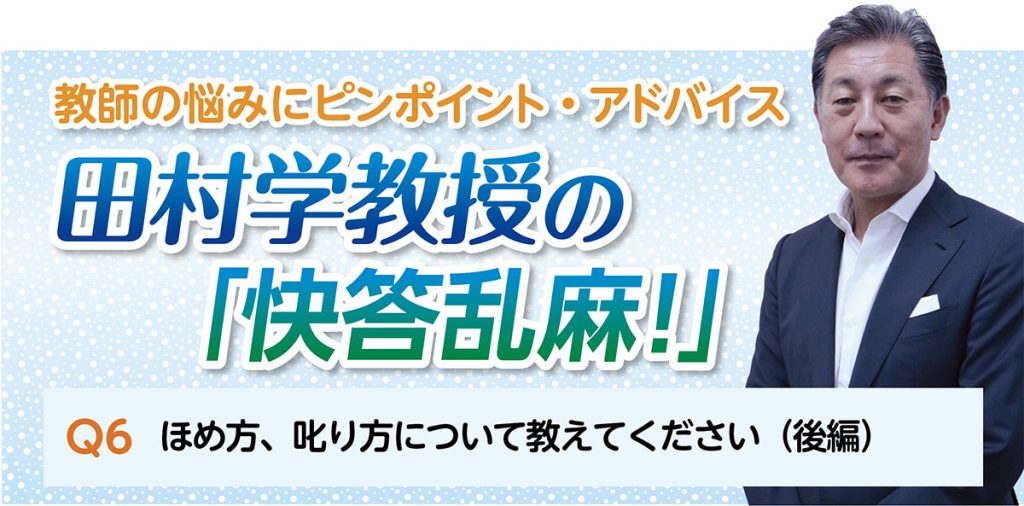
先生方のご相談について、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回も前回に続き、子供のほめ方、叱り方をどうしたらよいか考えている先生のご質問に対し、さらに詳しく「快答」していただきます。
※
Q6 昨年度、同じ学年を組んでいた先生はとても厳しい方で、授業中によく隣の教室から子供を叱る(怒る?)大きな声が響いていました。そのたびに、「ああ、あんなに厳しく叱らなくてもいいのに。私はなるべく子供たちをほめて育てたい」と思っていました。ただ、子供たちを成長させるには叱ることが必要な場面もあると思います。そこで、子供たちを伸ばしていくための、ほめ方、叱り方について教えてください。(20代・小学校)
日常生活の中で意識してトレーニングしてみる
A 前回は、ほめること、叱ることについての基本的な考え方についてお話をしました。今回は、もう少し突っ込んでほめ方、叱り方について考えていくことにしましょう。
先生は、よい行為や態度をほめ、問題のある行為や態度を叱るわけですが、その時に大事なのは、先生がほめたり叱ったりしている行為や態度、さらに先生とその子供とのやり取りが、周囲にもいろんな影響を与えることを知っておくことです。つまり、当該の子供をほめたり、叱ったりしていることを、周囲の子供たちも聞いている可能性があるということです。
ですから、どこでほめるか(叱るか)、どのようにほめるか(叱るか)を考えることも大切なポイントになります。みんなの前でほめたほうがよい場合もあれば、周囲に人のいない場所でほめたほうがよい場合もあるでしょう。例えば、小学生でも高学年になって思春期に差しかかり、周囲の子供たちの目が気になり始めると、「ほめることも個別に行ったほうがよい場合もある」と言う先生もいます。
あるいは、一人の子供をほめている(叱っている)ことはその子に(行動の継続や改善を)期待するだけでなく、学級全体にも期待しているということになります。そういったことも意識されると、より効果があると思います。
また、どのようにほめるかということで言えば、先生が直接ほめるほめ方もあれば、ほめたいことを第三者の口を通して語ってもらったほうが効果的な場合もあります。例えば、保健室の養護教諭から何気なく、「~先生が~ってほめてたよ」と話してもらうとか、家で保護者から「~先生が、連絡帳にこんなふうに書いてあったんだけど、よくがんばっているんだね」とほめてもらう、といった方法です。それは、子供たちにとっても嬉しいことだと思います。私自身をふり返ってみても、先生からほめられれば嬉しいわけですが、周囲の人から「~なふうにがんばっているんだってね」と言われるのは、悪くない気持ちになると思います。
それは、その子供の良い行動を校内の先生方とシェアすることにもなりますし、保護者とシェアすることにもなるわけです。そのように、ほめたり叱ったりする行為が、その場だけに限定されず、広がりがあったり、影響があったりすることを少し頭に入れておくと、多様な効果が期待できるのではないかと思います。
いずれにしても、ほめられるということは自己肯定につながるわけで、子供に限らず誰でも嬉しいわけです。それだけに、たくさん、小さなことでも、さりげなく、上手にほめられる教師であれば、多様なことがうまくいくのではないでしょうか。
余談ですが、それは大人でも同様で、WBCの栗山英樹監督も、きっとそうだったのではないかと思います。そのために、栗山監督は手紙を書いて出したといったことが報道されていましたが、それ以外の場面でも上手にほめていたのではないでしょうか。ほめ上手は、人心を掌握するだけでなく、集団をまとめていったり、指導を確かな形で浸透させていったりすることにつながるのだと思います。

