2年生担任になったあなたへ 1年間の見通し&10の戦略!

校長せんせいより2年生担任を命じられたあなたは、どんな担任になればいいでしょうか。
学校で1年間生活し、学校とはこういうところだと分かってきた児童。自分の世界が広がり、クラスメイトだけでなく上級生と接したり、多くのせんせい方と接したりする中で経験したことを生かして自分なりの学校生活を楽しむ学年でもあります。こんな10のポイントを意識してみましょう。
【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~
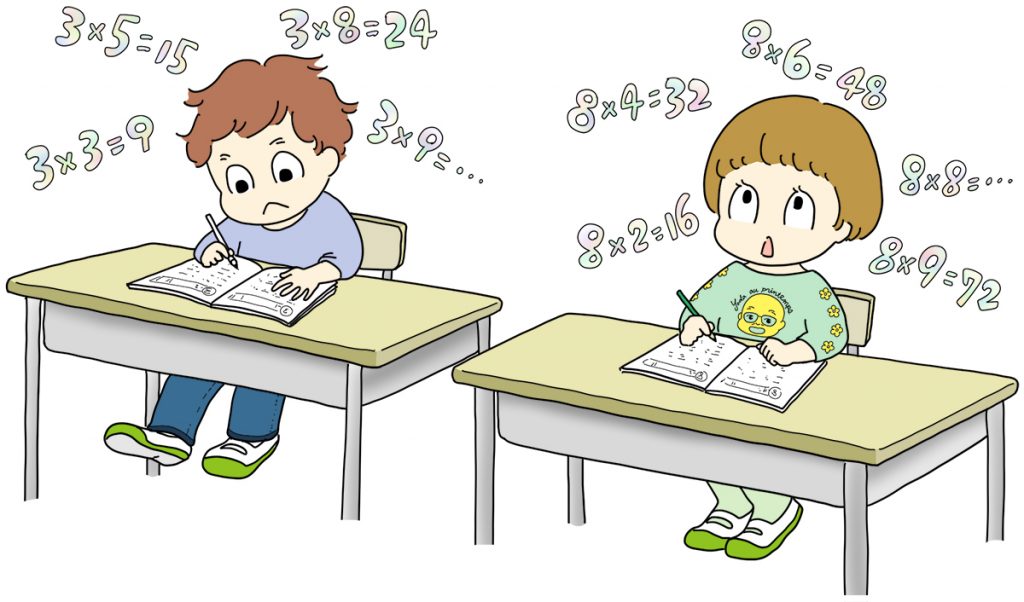
目次
学習指導・生徒指導編
1 教科横断的活動を仕組む
わたしたち教える側の立場からすれば、国語ではこれ、算数ではこの内容、と教科単位ごとに内容を考えがちですが、この期の児童は、全てが学びにつながると言っても過言ではありません。
教科内容を教えるというよりも、学習発表会などの機会を利用して、総合的な学習の取組の中から、いつの間にか教授すべき教科内容が身につくというような活動を設定すると良いと思います。
生活科ですと、合科的な学習活動を設定しやすいです。年間を通じて、どの教科のどの内容が結びついていくかを考え計画してみてはどうでしょうか。
特に言葉や身体、音楽などは密接に結びついています。自分たちで考えたストーリー仕立ての表現運動、オペレッタ、ダンスなどは1つの教科横断的な活動して、理想的だと言えます。
2 人生の基礎 九九の習得を位置づける
2年生と言えば、九九の習得期として大切な時期です。できるだけ迅速に、しかも確実に九九を暗唱できるようにしたいです。
九九の習得には、上がり九九、下がり九九の基本的な暗唱や問題を出してもらって唱えるランダム九九など様々ですが、九九習得達成表などを作って、これらの要素を入れ込み、児童がステップアップしていけるようにしましょう。
また、時間も大切です。何秒で言えるようになったか、とストップウォッチを用意して記録していくこともいいことです。
最近は100円ショップでストップウォッチが買えるようになってきました。ぜひ教室に常備しておきたいですね。
また九九の暗唱にはぜひ、家庭を巻き込んでいきたいです。
保護者に暗唱を聞いてもらって、チェック印をもらうとか、一緒に唱えるとか、いろいろな場所(おふろ、トイレ、台所など)で唱えるなど、ゲーム性を盛り込むと長続きします。とにかく全員が確実に暗唱しなければならないことを考慮して、学級経営に位置づけていきたいです。
3 ものの準備・場の準備を心がけさせる
1年生では、保護者と担任が児童に寄り添って、ものの準備や場の準備をしてきましたが、2年生になったとたん、自立しなさいと促されることが多いです。
しかし、何でも急に行うと、戸惑いや反動を生むものです。
4月に一斉に自立させるということではなく、徐々に習慣づけていくようにしましょう。
学級通信などで保護者に依頼しながら、1年間かけて自立させるくらいが、児童の成長にはちょうど良いと思います。
例えば図工で使うものを家庭で準備してもらうとき。1年生では学級通信で依頼すると保護者が用意してくれる場合がほとんどだと思いますが、まず2年生では、児童が自分の口で保護者にお願いできるように。そして次第に、自分自身で準備することを心がけさせたいです。
また、時間割を揃える、鉛筆を削って筆箱に入れるなどの基本的な学習用具の揃え方、体育の時間の前にきちんと体操着を着ている状態にする、音楽室に移動する際に自発的に楽器を持って行く、などのことが確実にできるようにしなければならないです。
この期を逃すと、なかなか身につかないものですので、長い目で指導していきましょう。
ものの準備・場の準備の指導にしっかり取り組みたいです。
4 自由へチャレンジさせる
1年生では、「ここにこんなふうに書きましょう」と担任が細かく指示し、「書いた人はちょっと待っていてね」と、児童の行動を一つ一つチェックしていくことが多いので、児童を待たせる時間がかなりあります。
しかし、2年生では、速度差がだいぶ出てきますので、終わった人の待ち時間がもったいないです。
「○○とノートに書きます。終わった人は□□していましょう。」といった「終わった人への行動指示」をしていきたいです。空白の時間がないようにすることが重要です。
さらに、ドリル学習でも「今日は何ページの何番から始める」と全員の進度を固定化するのではなく、自分の進度に合わせてどんどん進ませる、あるいは繰り返させる、といった自由進度で進めていくことも必要です。
5 トラブル処理術を会得する
2年生になると、自分と相手の意見の違いなどをはっきり意識するようになってきます。
学習面では、一定のルールを決め、黒板の前で自分の意見を話したり、他のクラスメートの場所へ行き、活発に意見の交流ができるようにしていくと良いですね。
しかし、自分の主張が通らなかったりすると、「ものかくし」などの嫌がらせ行為が出てくることもあります。これは、見逃してはならないです。
予防法としては、できるだけ児童と共に過ごし、児童観察をすることです。
ちょっとした仕草や顔色の変化などをチェックしていきましょう。
それでも起きてしまったら、
「今日は、残念なことが起きました。○○さんの□□がおいていた場所にないのです。とても悲しいです」
と宣言して、学級全員で探させます。
だいたいどこからか出てきます。
「見つかって良かったです。どうしてそこにあったのか分からないのですが、心当たりがある人がいたら、あとでコッソリ教えてくださいね」
と言います。
ここで、隠した本人が出てくればいいのですが、なかなか出てきません。
それはそれでいいのです。
大げさに騒ぐことで、「大変なことをしたのだ」という意識を芽生えさせることが目的であり、些細なことでも問題を見逃さず、全体で共有していくことで、トラブルはどんどん減っていきます。
もし犯人捜しになって個人を糾弾するようなことになってしまうと、その児童の孤立を生んだり、学級の雰囲気を壊したりと、弊害がたくさん出てきます。

