提言|中邑賢龍 学習障害の子どもの見つけ方とICT支援 【発達障害8.8%をどう受け止めるか #6】
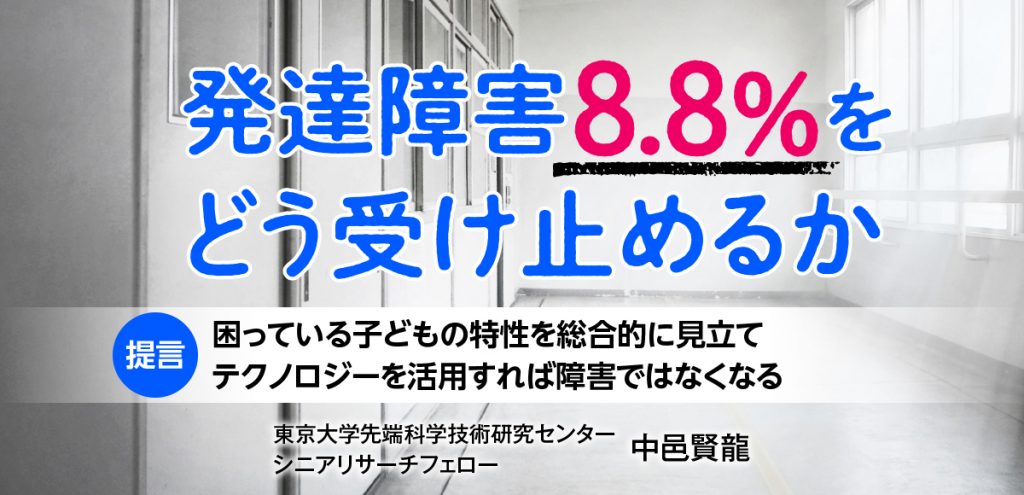
「通常学級の小中学生の8.8%に発達障害の可能性」という調査結果を専門家たちはどう受け止めているのかを知り、学校の未来を考える7回シリーズの第6回目です。学習障害のある子どもへの支援を、学校は今後どのように進める必要があるでしょうか。東京大学先端科学技術研究センターで、障害のある子どもへのICT支援研究を行ってきた中邑賢龍さんに聞きました。

中邑賢龍(なかむら・けんりゅう)
1956年、山口県生まれ。広島大学大学院教育学研究科博士課程後期単位取得退学後、香川大学教育学部助教授、カンザス大学・ウィスコンシン大学客員研究員、東京大学先端科学技術研究センター教授などを経て、2022年より現職。専門は人間支援工学。ICTを活用した学び支援研究、不登校やひきこもり状態になっている若者を支援する研究などを推進。著書に『発達障害の子を育てる本 スマホ・タブレット活用編』(講談社、2019年)、『どの子も違う』(中公新書ラクレ、2021年)がある。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全7回予定)
●提言|川上康則 学校管理職に気づいて欲しいのは「学校が子どもに合わせる時代」になったこと
●提言|児童精神科医が指摘! 発達障害の子どもと不登校の関係は?
●提言|木村泰子 「困っている子が困らなくなる学校」をつくる
●提言|赤坂真二 今、学校がすべきなのは学級経営のUD化
●提言|授業づくりのポイントはUDL×「個別最適な学び」
●提言|中邑賢龍 学習障害の子どもの見つけ方とICT支援(本記事)
目次
実際に困っている子どもはもっとたくさんいる
8.8%という調査結果には意味がないと感じます。この調査に答えたのは先生であって、回答に子ども本人や保護者の困り感は反映されていないからです。困っている先生方がたくさんいるから、このような調査を行うのだと思いますが、これでは「先生が困っている子ども=発達障害」になってしまいます。学習するうえで困っている子どもがどれぐらいいるのかを把握することのほうが重要でしょう。
それと同時に、困っている子どもを発達障害と認定することに危険性も感じます。発達障害と診断される子どもの特徴は、生まれつき有する認知や性格の偏りです。それを治療することは彼らを否定することにもつながりかねません。発達障害の子どもにありがちな、空気を読まない、こだわりが強いなどの特性は、使い方次第でプラスに働く可能性があるのに、最初から障害、「よくないもの」として扱うことには疑問を感じます。しかも、文字を読むのが遅い、文字を書くのが遅い、文字が汚いなど、読み書きが苦手な子どもがいたとしても、今はICTを使えば、負担を軽減することができます。これからは、困っている子どもにはICTを使って学びの支援を行うことを前提とすればいいと私は考えていますが、その際に、あえて子どもを発達障害と認定しなくても、読むのが苦手な子ども、書くのが苦手な子ども、計算が苦手な子ども、などの分け方をすればいいと思うのです。
私たちの研究室では、児童生徒の不登校問題を研究していますが、不登校の子どもたちの中には相当数、読み書きが苦手な子どもがいることがわかっています。書けないわけではないし、読めないわけでもないのですが、文字が汚いこと、書くのが遅いことなどを、いつも先生から注意され、もちろん、不登校の原因はそれだけではないですが、だんだん学校に行かなくなってしまうのです。
問題は、困っていても、困っていると言えない子どもがいることです。そのような子どもたちは、現在のシステムでは医師による診断や認定がないために、学校で特別支援教育を受けることができず、先生から注意され続けることになります。おそらく、通常学級で困っている子どもは、8.8%よりももっとたくさんいることでしょう。これからは診断や認定がなくても、子ども本人が望んだら、通級指導などを受けられるようにする必要があります。
小学校低学年では書字の苦手意識を持たせないことが大事
子どもが困っているかどうかは、小学1、2年生の頃はまだわからないと思います。その時期に大切なことは、書字への苦手意識を持たせないようにすることです。
そのために大事なことは、子どもが書いた文字に対して、例えば、ハネがない、曲がっている、枠からはみ出しているなどと、先生があまり細かく指導しないことです。視覚-運動協応が苦手な子どもは、見本と同じように文字を書くことが難しいのです。にもかかわらず、細かいことをあれこれ言われ続けると、文字そのものを書かなくなりますので、長文が書けなくなってしまいます。
子どもが書くことへの意欲を失わないためには、多少間違っていても、例えば、漢字の線が一本多くても少なくても、先生には丸を付けてやって欲しいところです。しかし、先生ご自身にこだわりがあって、完璧な形の文字にしか丸をあげたくない方もいるかもしれません。その場合は、赤ペンでバツをつけるのではなく、青ペンで丸をつけてあげて欲しいのです。結果的に、漢字テストなどが青丸ばかりの子どもが出てくるかもしれませんが、それを見ることで保護者は「子どもが困っているかもしれない」と気付けます。青丸の得点がその子の理解度を示すことになりますので、保護者は「赤丸は40点だったけど、本当は青丸を加えて80点だね」などと言ってやれますから、子どもは自信を失わずに済むはずです。
また、宿題は、クラス全員に同じことを課すのではなく、それぞれの子どもの特性に合った内容に調整することも重要です。例えば、同じ漢字を複数回書かせるような宿題を出すとしたら、他の子どもは10回でも、書くのが遅い子どもは3回でいいことにします。枠を大きくしてもいいでしょう。それにより、書くのが遅くても無理のない範囲で宿題をこなせるようになります。
ただし、先生は良かれと思ってしたことでも、保護者に何の相談もなしに進めると、保護者は差別されていると感じ、「なぜうちの子だけ宿題の量が少ないのですか」と抗議してくるでしょう。大事なのは、保護者も一緒に考えてもらうことです。「どうすれば子どもの困り感を軽減できるのかを一緒に考えましょう」と話し、保護者の意見も聞きながら、対策を一緒に考えるのです。それにより、「先生、ありがとう。うちの子のストレスがなくなりました」と言われるような関係をつくることができます。

