誰も置き去りにしないクラス【玄海東小のキセキ 第4幕】
- 連載
- 玄海東小のキセキ
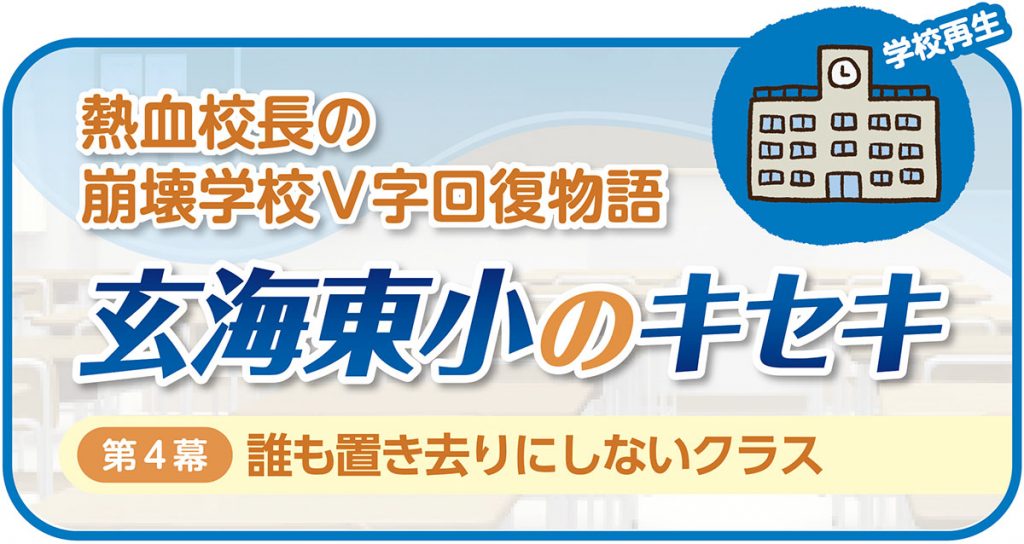
脇田哲郎は、晴れて福岡県の小学校教諭となり、4年生の担任としてその第一歩を歩み始めます。先輩から勧められた係活動の実践に邁進(まいしん)する脇田。どんなクラスを目指せばよいのか。居心地のいいクラスとは、どんなクラスなのか。その答えを求めて模索する脇田を導いてくれたのは、意外にも子供たちでした。
目次
特別支援の子が生んだみんなの笑顔
脇田が教員になったのは、1979年。初任校である福岡県宇美町立宇美東小学校から始まった。
赴任先が決まるとき、人事監理主事から「どの学校にしますか」と聞かれて鹿児島出身の脇田は戸惑った。福岡の右も左もわからなかったからである。脇田は海の傍で育ったので、同じ音の「宇美」がつく学校を選んだのだが、宇美町は福岡市よりも内陸にある太宰府市に近く、海とは遠く離れていた。
初任校では4年2組の担任を受け持つことになった。そのとき、新任の脇田が思い描いていたのは、教科の指導よりも、子供たちにとって居心地のいいクラスにするにはどうしたらいいかということだった。脇田が小学4年生のときに担任の先生がお誕生日会をしてくれたことや、大学4年の教育実習のときに実習先のクラスの子供たちがお別れ会を開いてくれたことを思い出し、そんなクラスをつくりたいと思った。
しかし、学級経営や特別活動について具体的な指導方法を知っているわけではない。見よう見まねで同僚の指導法を覚え、先輩の教員に勧められて係活動の実践に一から取り組んだ。「その指導法に食らいついた」と脇田は表現した。
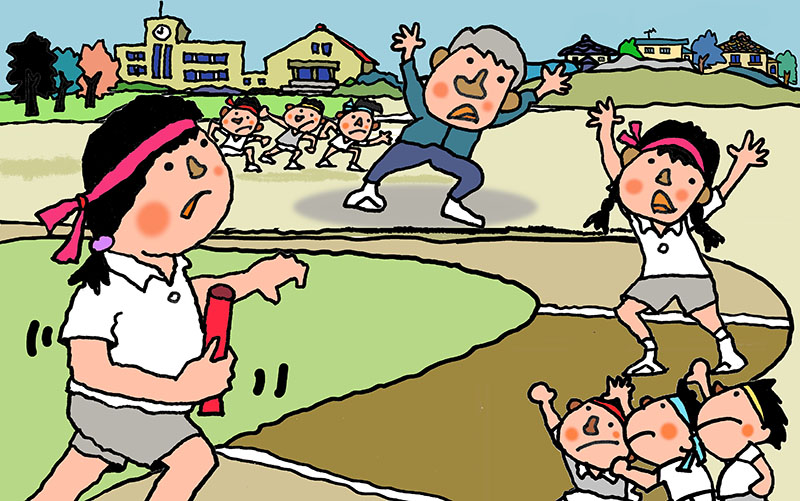
脇田のクラスには、特別支援が必要なために国語や算数の授業には参加しないけれども、音楽や図工や体育などの授業には参加する、あけみという女の子がいた。みんなは彼女のことを、あけみちゃんと呼んでいた。
体育の時間には、学年が合同して体育を行う授業があり、4年生の4クラスでクラス対抗リレーをすることになった。トラックを半周するごとに走者が交代するリレーである。
あけみは体が小さく、よたよたした走り方しかできない。
「あけみちゃんは足が遅い」
「あの子のせいでリレーに負ける」
子供たちからそんな声が上がった。脇田は「あけみちゃんをのけ者にするのか」と反論すると、子供たちはこう決めた。
「あけみちゃんの走る距離を縮めてもらおう」
しかし、脇田の一存ではできないので、こう促した。
「それは自分だけで決められないから、ほかのクラスの先生に相談してください」
子供たちはその場でほかのクラスの担任から了承を得て、あけみの走る距離を半分にしてもらった。しかし、クラスは負けた。さらにその距離を4分の1にしてもクラスは負けた。とうとう彼女の走る距離を5メートルにまで短くしたが、クラスはビリに終わった。
なぜか。あけみは一生懸命に走った。彼女から引き継いで半周まで走る子も頑張って走ったが、どの走者も相手の走者に遅れをとったからだ。
「なあーんだ、みんなの足が遅かったんだ」
誰もあけみを責める子供はいなかった。
そのすぐあとには、社会科見学の時間があった。あけみと同じ班になったじゅんという男の子が、あけみの守り役になった。
社会科見学の移動でバスに乗っていると、あけみがバス酔いして吐いてしまった。じゅんはあけみの背中を擦る。しかし、あけみの吐き気はなかなか収まらない。いつもはやんちゃなじゅんも釣られてついに吐いてしまった。じゅんが「いや~、参っちゃったよ」という照れ笑いをしたので、バス中がじゅんをねぎらうような笑いで包まれた。脇田はこの瞬間、クラスが仲間として動き出すことを直感した。
あけみをめぐって子供たちが変わった。クラス対抗リレーで何度も一緒に走り、子供たちがあけみとともに暮らすことで、あけみがクラスの一員になったと思った。その変化を見て脇田はこう心に決めた。
「これが自分の目指すクラスだ。こういうクラスをつくっていこう」
脇田の心のなかで「居心地のいいクラス」の中身が形になって見えてきた。

