「振り返りリレー」自治的な学級をつくる12か月のアイデア #1

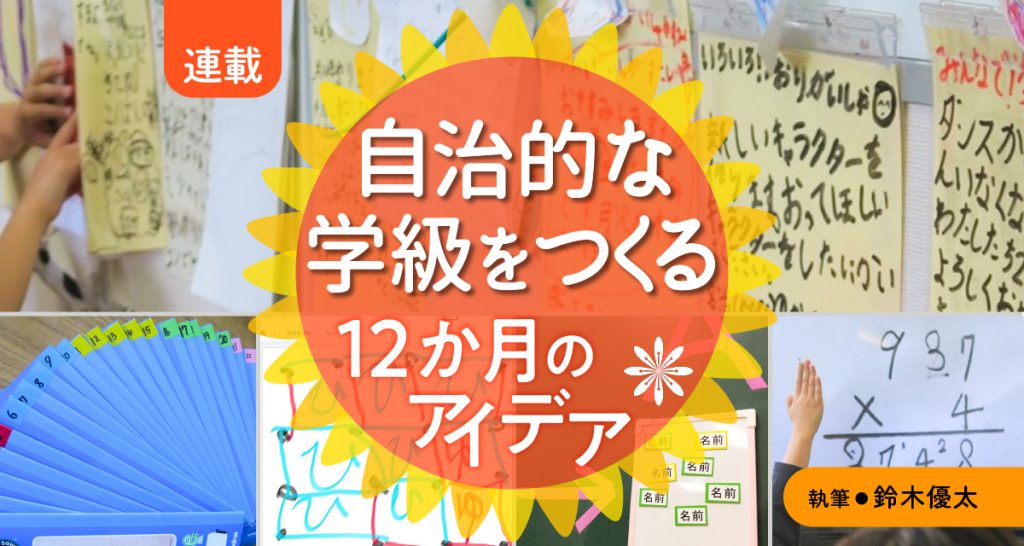
子供たちが主体的に学び合い、話合い活動を通して自分たちの力で問題を解決していく、そんな学級をめざしたいもの。この連載(月1回公開)では、『日常アレンジ大全』(明治図書出版)などの著書をもつ鈴木優太先生が、自治的な学級をつくるための授業や特別活動のアイデアを紹介します。第1回は、帰りの会で行う「振り返りリレー」です。
執筆/宮城県公立小学校教諭・鈴木優太
目次
帰りの会に「振り返りリレー」を取り入れよう
「振り返りリレー」とは、子供たちが出席番号順(席順でも可)に呼名し合い、リレーのように振り返りを全員が発表し、それを全員で聴き合う活動です。毎日の帰りの会で行います。
【手順】
①出席番号順に、子供たちがリレーのように呼名していきます。
②「はいっ!」と返事をし、その日のベストエピソードを2文程度で発表します。
③発表する級友に正対して聴きます。

「聴く」ことが重要です。座席に座っている間も体の向きをくるくると変えて、発表する級友に正対します。
次のようなイメージで、子供たちはテンポよく発表していきます。
日直「振り返りリレー!」
全員「振り返りリレー!」
日直「Aさんっ!」
A「(起立)はいっ!2時間目の算数です。Bさんの説明を聞いて、計算の仕方を私も5人に説明できました。Bさんっ!」
B「(起立)はいっ! 5時間目の社会です。調べ学習中に動画が止まるトラブルがあったけれど、その間に教科書をすみずみまで読んで、大事なことをまとめることができたからです。Cさんっ!」
C「(起立)はいっ!…パスします。Dさんっ!」
「パスします」もOKです。出席番号末尾の子の後にリトライできます。友達の振り返りをひと通り聴いた後なので、真似をして言えるようになっていきます。最後の1人まで回ったら、全員で拍手を贈り合って締めくくります。慣れてくると、30人学級でも3分間程度で全員の振り返りを聴き合うことができます。
「3つの習慣」を身に付けよう
「振り返りリレー」を毎日継続することで、「3つの習慣」が学級の子供たちに育まれていきます。
①級友の名前を呼び合う習慣
②級友の話を聴き合う習慣
③振り返りの習慣
この「3つの習慣」が、本連載のテーマとして掲げた「自治的な学級」には欠かせないのです。
①の「名前を呼び合う」ことと②の「話を聴き合う」ことの2つについては、朝の5分間が5時間につながる活動を【子供同士をつなぐ1年生の特別活動】①に詳しくまとめましたので、そちらをご覧ください。
ここでは、③の「振り返りの習慣」について説明します。
振り返りは、「リフレクション」とも表現する行為です。
リフレクションとは、自分の内面を客観的・批判的に振り返る行為です。
引用:熊平美香『リフレクション 自分とチームの成長を加速させる内省の技術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
リフレクションの目的は、あらゆる経験から学び、未来にいかすことです。
経験を客観視することで新たな学びを得て、未来の意思決定と行動に生かしていく。これがリフレクションです。
つまり、振り返りの目的は「次をよりよくするため」だと私は考えます。
「自分たちの日々を自分たちでよりよくしていこう!」
という「ムード」(雰囲気)が、学級いっぱいに充満することがまずはとても大切です。振り返りをすることが1日の中にシステム化されていることで、前向きな思考のくせが学級に浸透していくのです。

