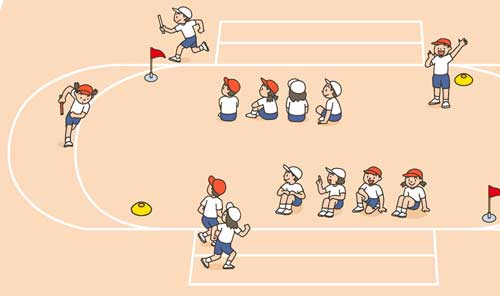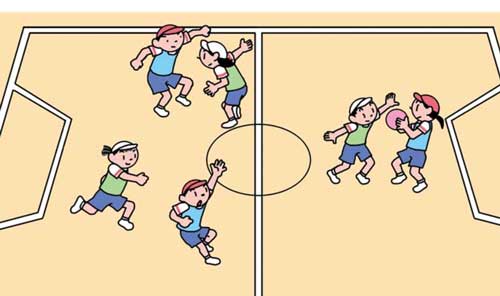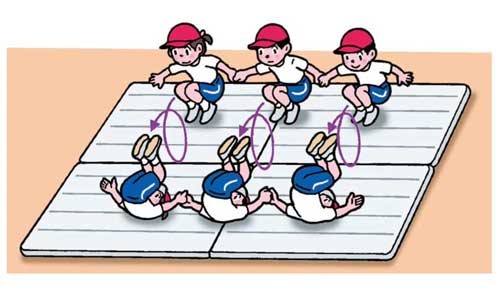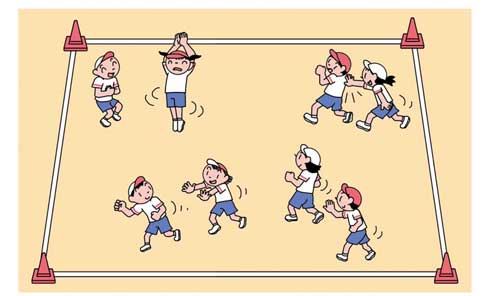小5国語「この本、おすすめします」指導アイデア
教材名:「この本、おすすめします」光村図書
指導事項:〔知識及び技能〕(1) オ 〔思考力、判断力、表現力等〕B(1)ウ・カ
言語活動:ア
執筆/東京都公立小学校指導教諭・市川裕佳子
編集委員/文部科学省教科調査官・大塚健太郎、茨城大学教育学部附属中学校副校長・菊池英慈
目次
単元で付けたい資質・能力
①身に付けたい資質・能力
相手や目的に応じて、自分の考えが伝わるように書き表し方を工夫する力を育成します。書き表し方の工夫をするというのは、効果的に本を推薦するために簡単に書くことと詳しく書くことを分けたり、相手に応じて意図的に言葉や表現を選んだりすることです。そのためには、単元の冒頭で、本を推薦する相手や目的を明確にすることが重要になります。
②言語活動とその特徴
「他学年の児童におすすめの本を推薦する文章を書く」という言語活動を位置付けます。推薦する文章には、よさが伝わるような見出し、その本の特徴、お薦めする理由などを記述します。文字の配列や大きさについては、書写と関連付けながら、効果的に情報を伝えるためにふさわしい書き方について押さえると効果的です。
書いた文章は、他学年の児童に読んでもらい、可能であれば簡単な感想を書いてもらうとよいでしょう。書き表し方を工夫することで、伝えたいことを相手に伝えることができたという実感が、次にまた文章を書くときの意欲につながります。
「書き表し方の工夫」については、推薦する学年や目的に応じて文章のどこを簡単に、どこを詳しく書くのかということや、書き換えた方がよい言葉を判断することが重要です。
どの言葉に注目し、どのように書き表し方を工夫すればよいのか、教師のモデルを参考にしたり、観点を明確にしてお互いの文章を読み合ったりしながら、書き表し方を工夫することができるような活動を記述や推敲の場面に位置付けるようにするとよいでしょう。
単元の展開(7時間扱い)
主な学習活動
第一次(1時)
◎学習の見通しをもち、学習計画を立てる。
→アイデア1 主体的な学び
・今までに読んだ本で、推薦したい本について話し合う。
・教師の作成した推薦する文章を分析し、学習の見通しをもつ。
【学習課題】他の学年のみんなにもっと本を好きになってもらうために、おすすめの本について、書き表し方を工夫してすいせんする文章を書こう。
第二次(2~6時)
◎相手や目的に応じて、おすすめの理由を明確にし、書き表し方を工夫して推薦する文章を書く。
・選んでおいた推薦したい本についてよさや特徴について書き出す。
・伝えたいことが伝わるような構成を考える。
・書き表し方を工夫して下書きを書く。
→アイデア2 深い学び
・相手や目的に応じた書き方になっているかに着目して推敲する。
→アイデア3 対話的な学び
第三次(7時)
◎推薦する文章を読み合い、感想を伝え合う。
・相手や目的に応じた書き表し方の工夫になっているか着目して読み合い、書き表し方のよさについて感想を書いて伝える。
アイデア1 児童自身が学習の見通しをもつことができるような工夫

見通しをもち、粘り強く取り組むことができるように、単元の初めに児童と何をどのように学ぶのか共有することが大切です。そのために、まず教師がおすすめの本の紹介をしながら、推薦する文章をサンプルとして提示します。
今回は下級生にもっと本を好きになってほしいという目的で文章を書くので、それを達成するために、どのような項目があるのか、どのような言葉が使われているのかということについて分析します。
どのような文章が書ければよいのかゴールイメージをもてたら、次に、学習計画を立てます。既習の「書くこと」の学習計画を基に、同じ流れでできそうか、どの活動に時間がかかりそうか、新しく付け足した方がよい活動があるのか、教師の助言を基に、児童と一緒に確認をしていきましょう。
▼推薦する文章の例
イラスト/横井智美
『教育技術 小五小六』2021年12/1月号より