リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #22 外国の靴屋さん|曽根義人先生(宮城県公立小学校)

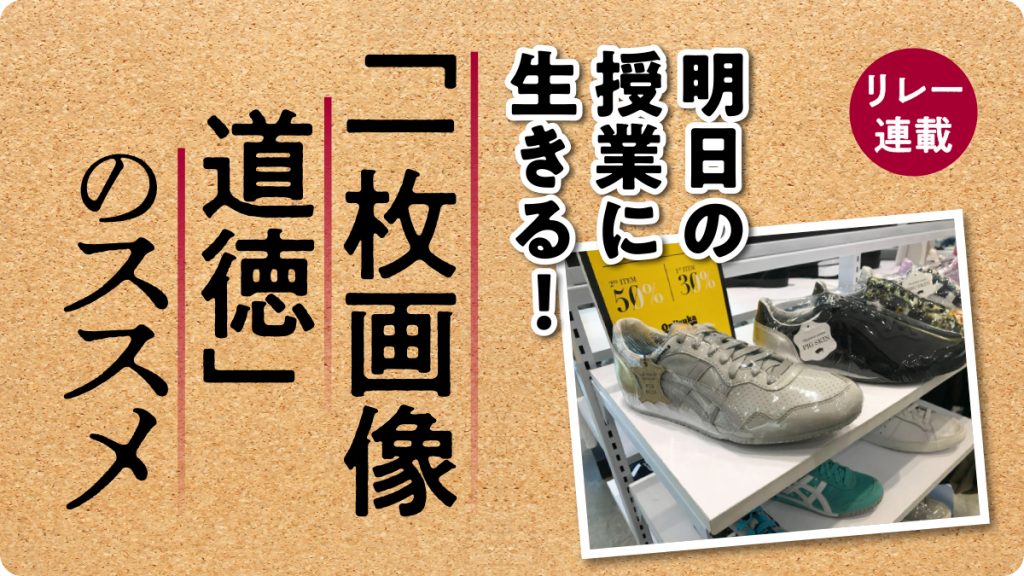
子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。第22回は曽根義人先生のご執筆でお届けします。
執筆/宮城県仙台市立愛子小学校教諭・曽根義人
編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和
目次
1 はじめに
教員生活15年、いつの間にか中堅と呼ばれる世代になっていました。
15年を振り返ると、体力が許す限り時間を忘れて授業準備をした時期もありましたし、我が子の沐浴時間に間に合うよう、時計とにらめっこしながら仕事をしていた時期もあります。
生活環境が自分の仕事への向き合い方に影響を与える経験をしてきましたが、私が最も影響を受けたのは、インドネシアでの生活です。
ジャカルタ日本人学校に勤めた3年間は他の都道府県から派遣された同僚との出会いに恵まれ、今もつながりは続いています。また、イスラム文化の中で生活すること自体が刺激的な日々でした。
中でも「Tidak apa apa.」(訳:大丈夫!)という言葉との出会いは、自分の考え方を180度変えたと言っても過言ではありません。
この言葉は、物事がうまく行かなかったときに励ましのニュアンスとして使われることもありますが、約束を守れなかった側も使う言葉なのです。
はじめの頃は開き直ったような態度を理解することが難しかったのですが、自分の想定通りになることばかりではないと捉えられるようになると、生活にも仕事にもゆとりが生まれていることに気付きました。
今回紹介する1枚の写真は、インドネシアの靴屋での光景です。
私に大きく影響を与えてくれた国での1コマを活用し、クラスの子供たちに新しい見方・考え方を育むことができるよう、以下の流れで実践しました。
2 「一枚画像道徳」の実践例
対象:小学2年
主題名:外国の靴屋さん
内容項目:C-6 親切、思いやり
以下の写真を提示します。

海外の靴屋の写真であることを伝えた上で、
『みんながよく行く靴屋さんとの違いはありますか?』と聞くと、
「なんだか、光っている。」
「ラップに包まれている。」
「キーホールダーが付いている。」
ということに気付きました。
続けて、
『この靴はどうしてラップに包まれているのでしょうか?』と、問いました。
「汚したくないから。」
「においをつけないため。」
「ウイルスが付かないようにしたいのかも。」
「高級に見せるために目立たせたいから。」
と、自分の生活経験から予想し、思い思いに発言していました。
ここで、私が住んだことのあるインドネシアの靴屋であることを伝えますが、外国に対する知識、とりわけイスラムの文化についての知識がほとんどない子供たちのことですから、キーホールダーにある豚の絵もヒントにはなりません。
そこで、なぜ靴がラップに包まれているのかを理解できるよう説明をしました。
●インドネシアの多くの人はイスラム教を信仰していること
●イスラム教の人は、豚(豚を素材に使っている商品)に触れることができないこと
●イスラム教以外の人も住んでいること
『この靴の一部には、豚の皮が素材として使われているため、ラップに包まれているんです。』と説明すると、子供たちから、
「触ることができる人と、触ることのできない人がいるんだね。」という声が上がりました。
その言葉から、この豚の皮を素材とした靴を触ることができる人が、触ることのできない人に対しての思いやりの気持ちでラップを巻いていることに気が付くことができました。
「形に見える思いやりってあるんだね…。」というつぶやきに、頷いている子がいました。
以上のやり取りの後に、一つ目の発問をしました。
発問1 みなさんの周りにも、親切にしてくれている人はいますか?
●用務員さんが授業中や帰りにほうきで掃除をしてくれています。
●○○くんが帰りに机を揃えていました。
●保健室の先生がけがをしたときに手当をしてくれました。
●今、点いている電気をつくってくれている人がいます。
近くの友達と考えを交流する様子を見ると、いつも当たり前のようにやってもらっているため、見過ごしていた親切もあったようです。学校生活を振り返ると、たくさんの親切があふれていることに気が付き始めました。
さらに、身近なところだけではなく、自分たちの生活を支えてくれている人の存在に気付いた発言には驚かされました。
仕事だからやってもらって当たり前ではなく、目には見えていない人からも親切にされているという趣旨の発言は、クラスの子供たちが日頃から受けている親切に気付き、視野を広げるきっかけになったように感じられました。
発問2 親切にしてくれている人の存在に気付き、何を考えましたか?
●自分でできることは面倒くさがらず、やるようにしたいです。
●今まで気付かなかったけど、ちゃんとお礼を伝えたいです。
●これまで親切にしてもらってきたから、自分も親切な人になりたいです。
●朝の挨拶だけでなく、「ありがとうございます」も言おうと思いました。
最初は誰かが親切でしてくれていたことに気付かず、友達の言葉に触発されて徐々に見つけていく段階を経て、「靴屋の写真」を通じて他者の思いやりを具体的に想像することができるようになり、発言が増えていきました。
さらに、子供たちは、「自分にできることは何か」を考えて、我先にと発表を続けました。
そういった姿が見られたのは、低学年という発達段階が要因だったかもしれません。それでも、「自分たちにもできることはないか」を真剣に考える子供たちの眼差しに、身近にある問いに出会うきっかけを与えることが教師の役目なのだ、と気付かせてもらいました。

