リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #18 わんこそば|古舘良純先生(岩手県公立小学校)

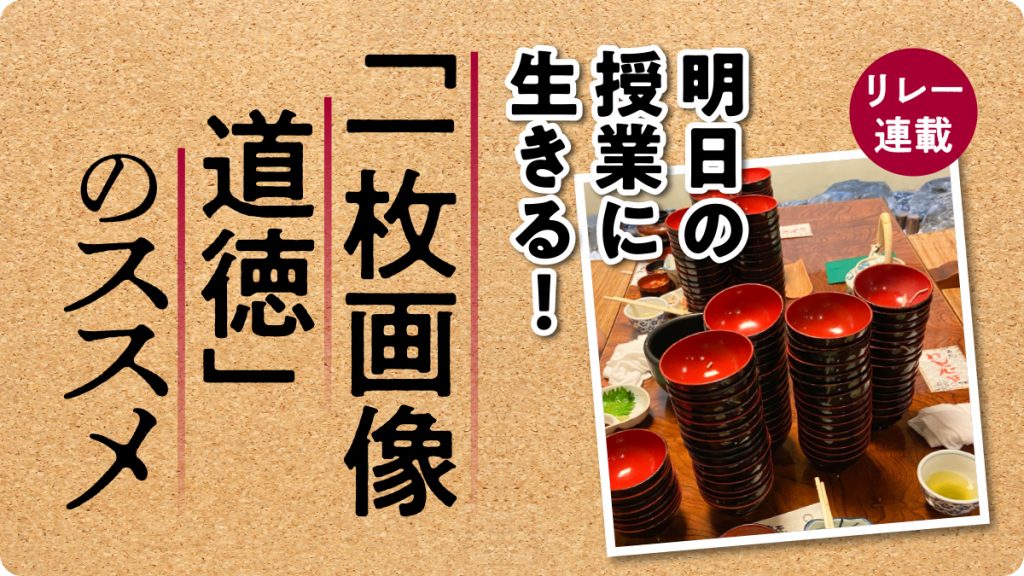
子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。第18回は古舘良純先生のご執筆でお届けします。
執筆/岩手県花巻市立若葉小学校教諭・古舘良純
編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和
目次
はじめに
現在、岩手県花巻市内の公立小学校に勤務しています。
それ以前は千葉県の公立小学校に11年間勤務していました。
長く、地元を離れて働いていました。
令和元年のタイミングで岩手県の採用試験に合格し、地元に戻って4年目を迎えています。
私は故郷岩手が大好きです。いわゆる若手時代を千葉県で過ごした私は、少しでも岩手のことを知ろうと努力しつつ、子供たちにも岩手の良さを伝えていきたいと考えています。
そんな中で、今回は岩手三大麺の一つである「わんこそば」を題材にした実践を紹介したいと思います。
1 身近な素材、地域の素材で考える実践
対象:小学6年
主題名:おもてなしの心
内容項目:B-(7) 親切、思いやり 相手を大切に思う気持ちをもち、心をこめて親切にする。
写真を見せて「やったことある人?」と尋ねます。

多くの子が「わんこそば!」と答えますが、やったことがある子は数人でした。
「何杯くらい食べたの?」「どうだった? やってみて」などといくつかやりとりをし、全員が土俵に乗ったタイミングで発問1に移ります。
発問1 「わんこそば」は、いつ誰が何のために始めたと思いますか。
●江戸時代
●明治に入ってから
●競い合うため
●みんなで分けるために小さいお椀にした
説明
実はね、みんなが住むこの花巻市では、昔はお祭り事の際に地主が大勢の村人に蕎麦を振る舞うと言う風習があったそうです。また、お蕎麦でお客さんをおもてなしする意味もあったようです。
お祭りで村人を楽しませたい、お客さんをもてなしたい。そんな親切な心の表れが「わんこそば」に詰まっているのです。
歴史的に見てみると、およそ400年前にその起源があるようです。
当時の南部藩の殿様が江戸に向かう際、花巻城に立ち寄り食事をしたそうです。
そのとき「殿様に対して市民と同じ器で食事を差し上げる事は失礼」との発想から漆器のお椀にひと口だけの蕎麦を少量ずつ出したそうですが、殿様はこれを「うまい」と何度もおかわりをしたという説があります。
その後花巻市出身の斉藤氏が盛岡で始めた「わんこや」がきっかけとなり「わんこそば」が広がったと言われています。
みんなも、岩手のおもてなしの心を大切にしてほしいと思っています。
先生は、先生に会いにきてくれる人がいたらお蕎麦屋さんに招待することが多いです。蕎麦でない場合は、岩手三大麺の冷麺を紹介することもあります。岩手のことを知ってもらいたいと思っています。
ちなみに、「やぶ屋」(学校から車で5分程度の所にある蕎麦屋さん)は、宮沢賢治さんが足繁く通った歴史ある蕎麦屋さんでもあります。ぜひ花巻人として覚えておくとよいと思います。
発問2 「わんこそば」は何杯食べたら良いと思いますか。
じつは、今みんなが知っている形の「わんこそば」の大会が始まったのは、1957年。
花巻市で始まったものです(諸説あります)。
今ではいろいろな大会があり、時間制限などのルールが違うので、どの記録が最高とは言えませんが、盛岡市で行われている「全日本わんこそば選手権」の歴代記録で言えば、632杯がトップになっているようです。
でも実は、「このくらい食べたらいいよ」という目安があります。それが「歳の数」です。年齢の数だけ食べることで長生きできると言われていました。「蕎麦好きは長生き」ということわざもあります。
地域の方やお客さんをもてなす以外に、家族も大切に思う心が蕎麦には込められていますね。
家族で年越し蕎麦を食べる家庭も多いのではないでしょうか。 自分の大切な人を思う心について、考えてほしいと思います。

