“刃を研ぐ”ことから考える、働き方を見直す意味【妹尾昌俊の「半径3mからの“働き方改革”」第16回】
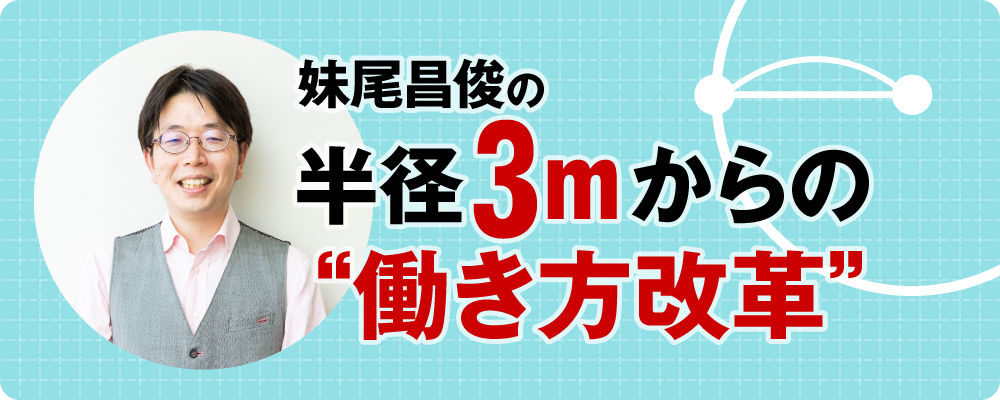
学校の“働き方改革”進んでいますか? 変えなきゃいけないとはわかっていても、なかなか変われないのが学校という組織。だからこそ、教員一人ひとりのちょっとした意識づけ、習慣づけが大事になります。この連載では、中教審・働き方改革特別部会委員などを務めた妹尾昌俊さんが、「半径3m」の範囲からできる“働き方改革”のポイントを解説します。
執筆/教育研究家・一般社団法人ライフ&ワーク代表理事・妹尾昌俊
目次
刃を研いでいる暇なんてないさ、切るだけで精一杯だ
前回は、自称“温泉理論”をもとに、有限な時間を何に振り向けるか考えよう、という話をした。今回はその続き。拙著『こうすれば、学校は変わる! 「忙しいのは当たり前」への挑戦』の一部から紹介しよう。
大ベストセラーの『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』というビジネス書では、7つ目の習慣として、“刃を研ぐ”ということを提案している。要するに自分を磨くということなのだが、次のストーリーがわかりやすい。
森の中で木を倒そうと、一生懸命ノコギリをひいているきこりに出会ったとしよう。
『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』(スティーブン・R・コヴィー著[フランクリン・コヴィー・ジャパン翻訳]キングベアー出版、2013)
「何をしているんですか」とあなたは訊く。
すると「見れば分かるだろう」と、無愛想な返事が返ってくる。「この木を倒そうとしているんだ」
「すごく疲れているようですが…。いつからやっているんですか」あなたは大声で尋ねる。
「かれこれもう五時間だ。くたくたさ。大変な作業だよ」
「それじゃ、少し休んで、ついでにそのノコギリの刃を研いだらどうですか。そうすれば仕事がもっと早く片付くと思いますけど」あなたはアドバイスをする。
「刃を研いでいる暇なんてないさ。切るだけで精一杯だ」と強く言い返す。
読者のみなさんもおわかりだろう。ノコギリの刃を研いだら、もっと効率的に仕事が片付くはずなのに、その暇がないんだよと言って、目の前のことに集中する。
これって、学校の先生たちにも当てはまらないだろうか? 小学校も中学校もとても忙しいのは事実だし、国や教育委員会のさまざまな施策がもっと必要なのは確かだ。だが、同時に、各学校や個々の教師が、「目の前のことで手一杯過ぎて、もっとうまくやる方法を考える暇もない」という状態になっているとしたら、それはそれで残念なことではないだろうか。
また、“刃を研ぐ”という意味では、自分の能力やスキル、精神力を磨いておく時間を大切にしたい。そのためにも働き方改革を進めて、余力を取り戻す必要がある。
部活動はハマりやすいから要注意
関連した話題でいうと、部活動では、生徒たちの成長する姿を見て、感動するシーンに立ち会うことができる。これは教師冥利に尽きるというものだ。しかし、だからこそ、部活は、教師も生徒もハマりやすいがゆえに、よくよく注意が必要だし、活動時間などに一定の制約が必要だと思う。
とりわけ、若手のうちは、授業準備などの本務を差し置いて部活にのめり込む教師がいることも問題だ。
中教審で働き方改革を議論しているとき、ある大学教授の委員が「若手3年目までくらいは、しっかり授業準備に時間を使ってもらうため、部活動顧問をさせないという選択があってもよい」という話をした。私はこの意見に共感する。“刃を研ぐ”ほうが大事だと思うからだ。

