最上位の目的のため、今こそ校長の行動を【木村泰子「校長の責任はたったひとつ」 #1】

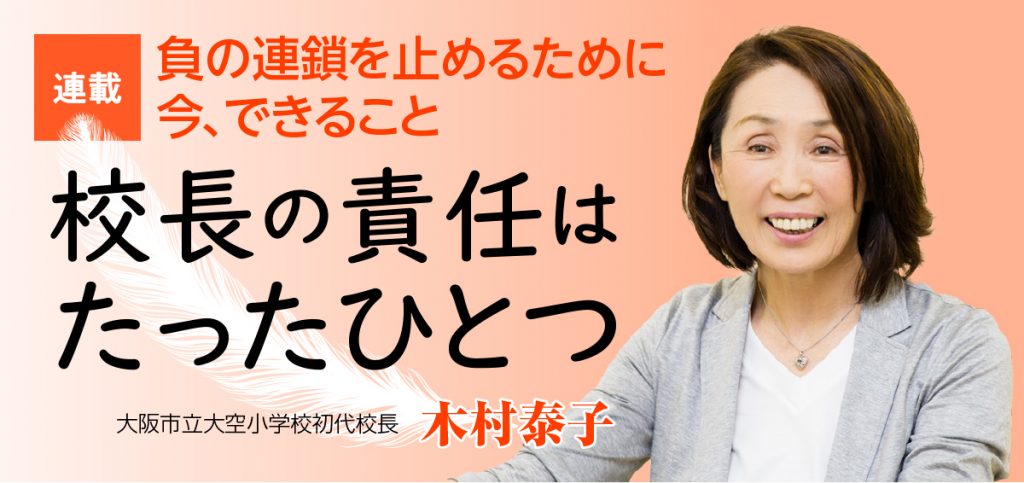
不登校やいじめなどが増え続ける今の学校を、変えることができるのは校長先生です。校長の「たったひとつの責任」とは何かを、大阪市立大空小学校で初代校長を務めた木村泰子先生が問いかけます。
第1回は、<最上位の目的のため、今こそ校長の行動を>です。
執筆/大阪市立大空小学校初代校長・木村泰子
校長のリーダーシップ論が問われていますが、その前にまず校長の「責任」とは何かを明確にする必要があります。学校という学びの場で、唯一校長にしかないもの、それは「責任」をとるという使命です。校長の仕事は限りなくありますが、校長の「責任」はたったひとつ、「すべての子どもの学習権を保障する」学校をつくることです。貧困であろうが「障害」があると診断されようが、すぐに暴力を振るってしまう子どもであろうが、地域に生きる地域の宝であるすべての子どもの居場所が、学校という学びの場にあること、つまり、誰一人取り残すことなく自校のすべての子どもの学習権を保障する学校をつくることが校長のたったひとつの「責任」です。
子どもの「命」以上に守るべきものはない
2018年から2020年の3年間で、1267人の小中高校生の「自死」が報告されました※。厚生労働省の統計によれば、2021年の1月から7月までに270人が自死しました。学校に居場所があるはずの子どもが、自らの命を絶ってしまったのです。「自殺」過去最多の事実は子どもたちの悲鳴です。また、反対に中3の生徒が同級生を殺害するという事件も起きてしまいました。自分の命を絶ってしまうか、友だちの命を奪ってしまうか、私には子どもが困り切って一人ぼっちになってしまった結果の行動としか思えません。
いじめの件数は減ったとの文部科学省の報告がありましたが、コロナ禍で子どもの困り感が今まで以上に見えなくなっているだけであり、より危機意識を高めなければならないでしょう。子どもの置かれている今の現実を自分事として捉えたときに、これまでの学校経営論が通用しないことは誰もがわかっています。今こそ、新しい発想で、誰一人取り残すことのない学校づくりを問い直し、行動に移すときです。
まずは、パブリックの学校の最上位の目的である、「すべての子どもの学習権を保障する」学校をつくることについて、全教職員で合意形成を図ることです。
2006年の大空小学校の開校当初に、校長の私は「自分一人で学級の子どもの命を守り切れる人は学級担任をしてください」と伝えたのを覚えています。当然、教員たちは(そんなことできるわけがない……)と、誰一人手を挙げませんでした。次に、「自分一人では一人の子どもの命も守れないと思う人?」という問いにも、教員たちの手は挙がらなかったのです。ここが学校の組織文化の大きな問い直しが必要なところでした。「おはよう」と学校に来てくれるから校長の責任が果たせるのです。「さよなら」と地域に帰った子どもが親に殺されてしまったら、次の日は学校にその子の姿はないのです。親が子どもの命を奪うことがあってもおかしくない社会になってしまっています。どれだけ指導力をアップしても教員一人の力で一人の子どもの命は守れない現実を、全教職員が自覚することが不可欠です。これまでは「いじめ」「不登校」「モンスターペアレント」「学力向上」などを教員の能力の問題として捉えてきました。その結果が前述した取り返しのつかない子どもの事実や「心の病」での教員の休職、「臨時講師」への依存度が高い特別支援学級の担任などの結果に表れています。負の連鎖を止めることが急務です。

