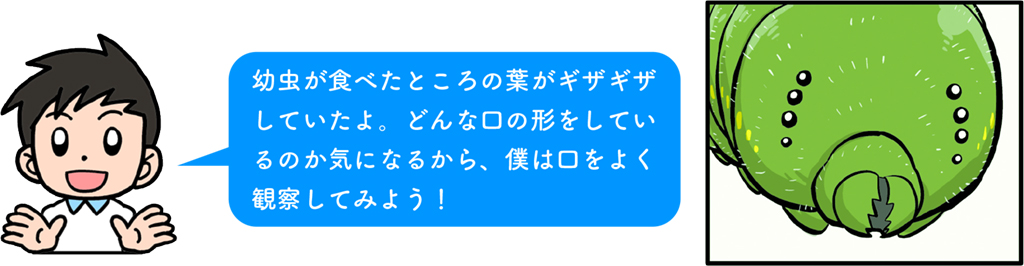主体的に観察に取り組むための教師の働きかけ 【理科の壺】

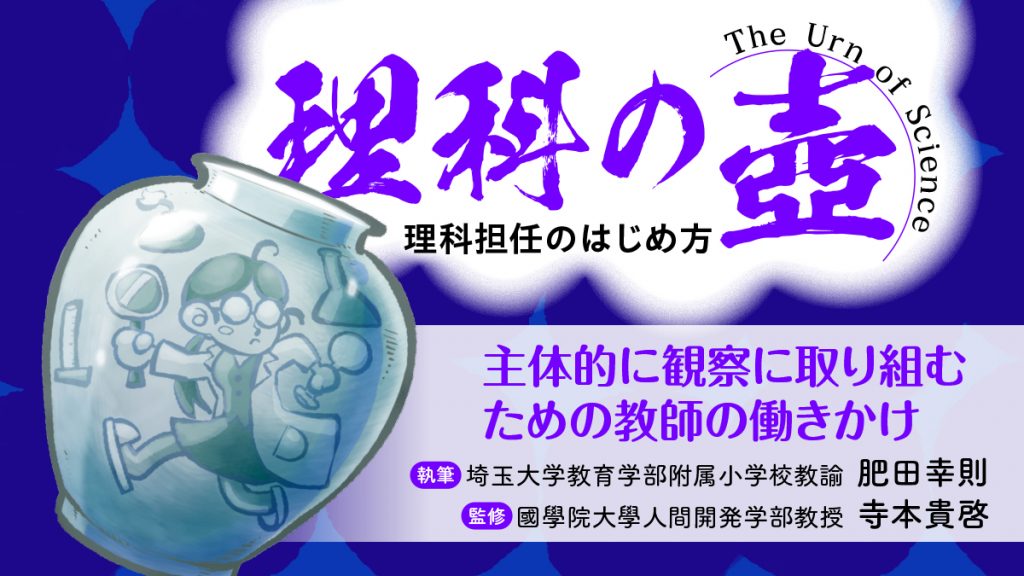
理科の学習において、「観察や実験」は問題解決の過程の中心であり、科学的に追究することが大切です。特に、観察においては、自然の事物・現象と触れ合う中で、その存在や変化の特徴を捉える必要があります。だからといって、観察の時間だけを確保していればそれでよいわけではありません。「子どもの主体性を…」といって、こんな授業をしていませんか? 第3学年のモンシロチョウの幼虫の観察を例にご紹介します。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/埼玉大学教育学部附属小学校教諭・肥田幸則
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.教師が最初から課題を提示してしまっている
1)こんな授業をしていませんか?
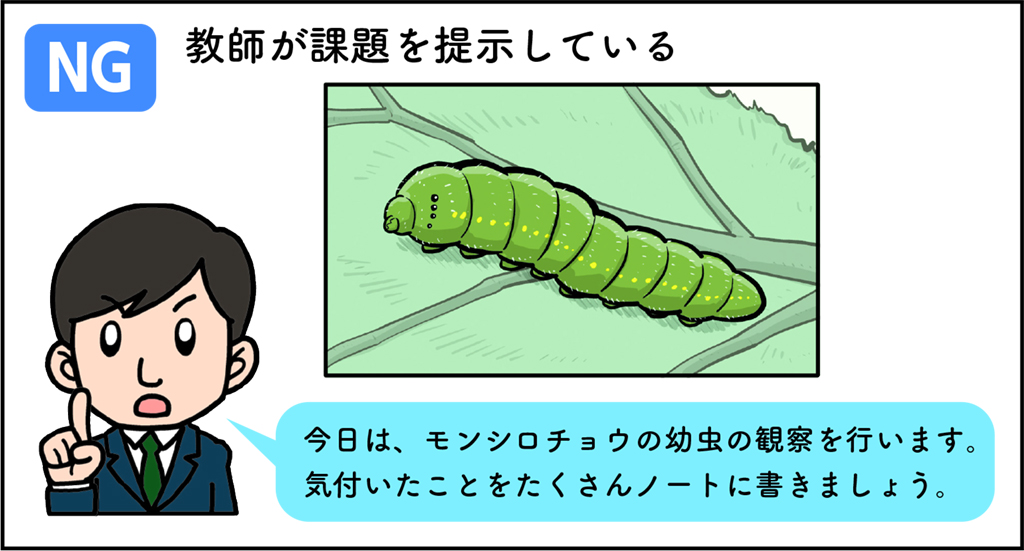
このように、教師から一方的に課題を提示するだけでは、「先生に言われたから見る」というように子どもが主体的に観察に取り組む姿は期待できません。何のために観察をするのか、その目的を明確にする必要があります。今回で言えば、子ども自ら「モンシロチョウの幼虫をよく見てみたい」という思いが持てるような、子どもの問題意識を高める教師の働きかけが大切です。
2)主体的な学びになるために、どのように働きかければよいのか?
<働きかけ> 子どもの発言を生かせるように発問を工夫する
主体的に観察を行うためには、問題を見いだす場面において、いかに子どもの問題意識を高めることができるかが重要です。
例えば、モンシロチョウの卵と幼虫を比較し差異点に着目する中で、「モンシロチョウの幼虫は動くから足がある」という子どもの発言に対しては、「脚は何本あるのかな?」と教師が問うことで、子どもは「幼虫の脚の形や数」に着目するようになります。また、「モンシロチョウの幼虫はキャベツの葉を食べるから口がある」という子どもの発言に対しては、「口はどんな形をしているのかな?」と問うことで、子どもは「幼虫の口の形」に着目するようになります。このように、教師が何を見せたいのか、子どもが何を見たいのかを意識しながら、子どもの実態に合わせて発問を変えていくとよいでしょう。