プール授業を楽しくする水慣れ呼吸法! ~続・水泳初歩指導~

最近は、コロナ禍の影響で学校プールでの水遊び・水泳指導にもかなり規制がかかり、短時間での学習を余儀なくされています。そこで、「泳力を伸ばす」というより、「水の安全」、「身を守る」ためということを重点化して取り組む学校が多いです。実は、水慣れの水泳初歩指導は、自らの命を守ることへ直結しているものもあります。とても重要な学習とも言えます。
水泳初歩指導で重要なものは、前回記事で紹介した ①水慣れ ②脱力 ですが、今回はそれに加えて、身を守るためにとても重要な ③呼吸 を紹介します。この3つのキーワードで初歩指導はばっちりです。前回に引き続き、楽しく水慣れする方法を「安全」という観点からも考えていきます。
【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~
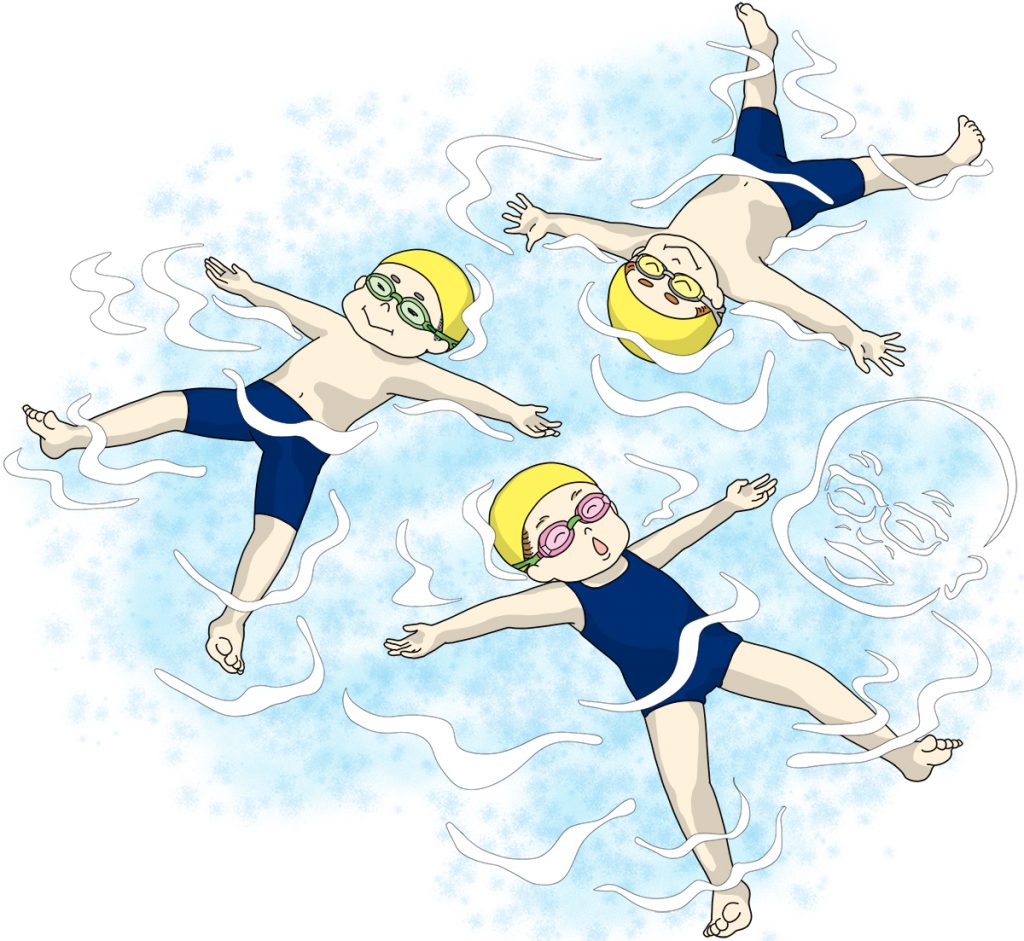
☆前回の記事もあわせてご覧ください。<プール大好きっ子にする水泳初歩指導!>
目次
1 「息つぎ」(呼吸)ができないのは…
 ポイント 洗面器が大きな武器!
ポイント 洗面器が大きな武器!
水泳の安全指導で、大事なことはいかに水中で呼吸を確保するかということです。水が怖い、恐怖を感じるということは、呼吸ができるかどうかという不安が一番大きいです。
実は泳げない子どもたちにとっては、
『水の量が恐怖心と関連する』
と言われています。つまり、お風呂、プール、海と水の量が多ければどんどん恐怖心が増してくるわけです。そこでまず初歩の初歩として、洗面器に顔をつけ、ブクブクと息だし、つまり「バブリング」をさせてみるのがいいです。慣れてきたら、洗面器を浴槽に浮かべるのも効果的です。浴槽で同じように洗面器に向かって「バブリング」させてみます。これでだいぶ恐怖心はなくなってきます。洗面器での「バブリング」は手軽に簡単に行うことができます。学校ではなかなかできませんので、ご家庭の協力が必要ですね。学級通信、学年通信などでぜひこの重要性を保護者の皆さんにお伝えしてください。
プールに入ってからは、
①鼻を出した状態で「バブリング」
②鼻を入れて目だけだした状態で「バブリング」
③顔を全部入れた状態で「バブリング」
と進めていきます。児童が水への抵抗をなくすように、「だいじょうぶだよ」と声がけしたり、腕にふれてあげたり、いっしょに潜ったりしていきます。「両手で大きな池を作って、そこに顔を入れてみよう」という洗面器での顔洗い型で指導するのもいいですね。
2 ゆっくり吐く
 ポイント 息を吸えれば鬼に金棒! 虎に翼!
ポイント 息を吸えれば鬼に金棒! 虎に翼!
水をこわがる児童にとって最大の恐怖は、水の中では呼吸ができないということです。恐怖心が取り除かれないままでは、体が硬直して動かなくなってしまいます。中には水中からプールサイドに上がってしまう児童もいます。水が顔にかかっても、水中に顔を沈めても冷静でいられるようにしたいです。冷静さを欠くことが水の事故に直結してしまいます。
そのためにぜひ時間をかけて指導したいのが、「ボビング」です。水中に沈みちぢこまり底を蹴って水中に上がっていく動作をさせます。口を「ウ」の形にゆるやかにすぼめながら、息をゆっくり鼻と口から吐かせます。上がってくる途中で息を吐いていかせるのです。そして、水面に顔を出し、口を大きく「ア」の形にさせます。そうすることで、自然と息を吸うことができます。
この、水中から水上に出ることで自然と息ができるようになる感覚を、しっかり覚えさせます。
具体的なステップとしては、プールの底を利用し、底を蹴り水面に上がっていくイメージで…。
①その場で「ボビング」
②歩きながら前への動作を入れた「ボビング」
③平泳ぎの手のうごきなどを入れて「ボビング」(上学年で平泳ぎにつながります)
といった段階で指導していきます。
息を吸うことを意識させるのではありません。
水中で息をはき、水面から顔を出すと、勝手に空気が入ってくるというイメージを持たせていきます。息を吸うということを強く意識すると、どうしても水を吸ってしまうことが多くなります。
そして、鉄則なのが、
口で息を吸って、鼻から息を出す
ということです。もちろん口から息は少し出ます。それは全然構いません。児童の中には、口から息を出さないようにするために、思い切って口を閉ざしている姿を見ることがありますが、これでは力が入ってしまい、「脱力」できません。中には、口の中に水が入ってくるのを恐れる子もいるでしょう。
そんなときは指導者が口を半開き状態にして潜ってみせて、「ほら全然水が入ってこないよ」と示してあげるといいでしょう。

