9月入学の新入生にには 「一斉切り替え案」「段階案」を提示【教育ニュース】
先生だったら知っておきたい様々な教育ニュースについて、東京新聞の元教育担当記者・中澤佳子さんが解説します。今回のテーマは9月入学の新入生における2つの案についてです。

執筆/東京新聞記者・中澤佳子
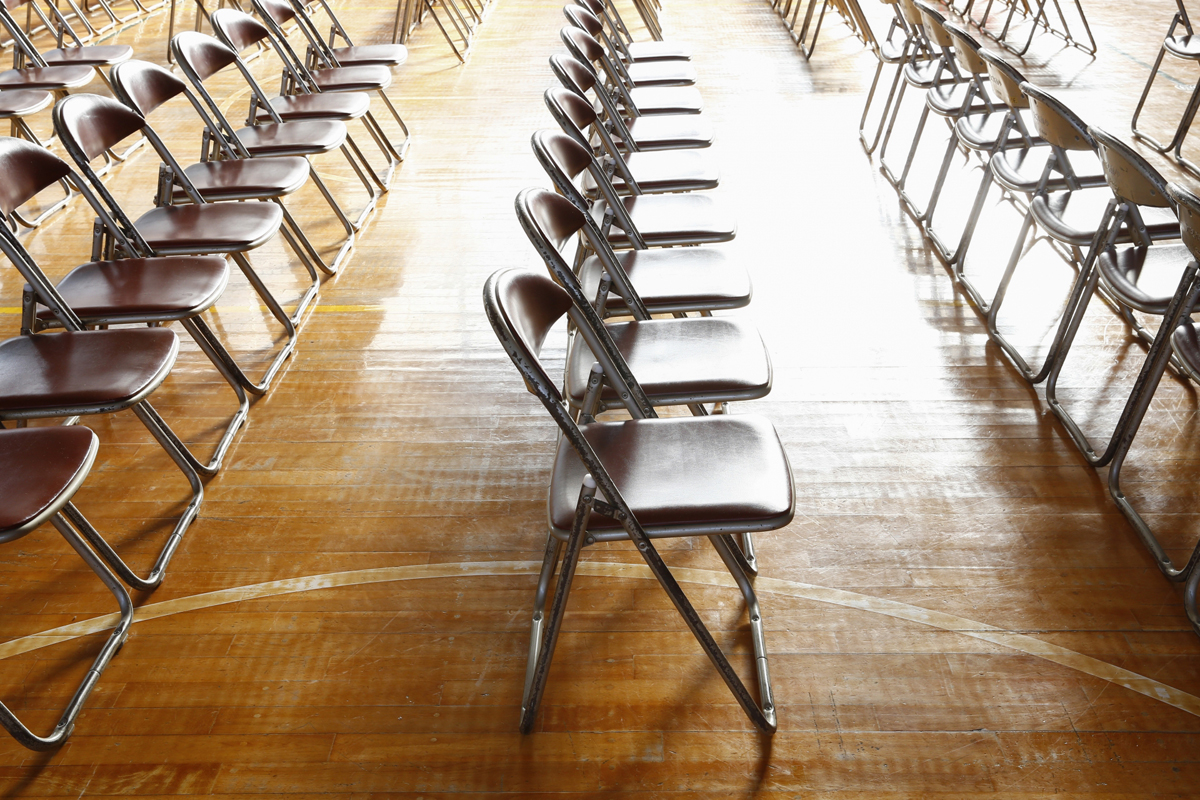
目次
コロナ禍で再び取り沙汰された9月入学
桜の花びらが舞う中、子供たちがランドセルを背負い、期待と不安を胸に学校へ。新学期や入学式の光景は、何年後かに様変わりするかもしれません。
新型コロナウイルスの影響で休校が長引き、学習の遅れを取り戻す策として、9月入学(秋入学)が話題になりました。
それを受けて文部科学省が、移行にまつわる課題などを整理し、ホームページで紹介しました。
実は、9月入学は目新しい話ではありません。文科省によると、1987年の臨時教育審議会から、2013年の「学事暦の多様化とギャップタームに関する検討会議」まで計6回議論され、答申や報告がまとめられました。
全ての教育段階での導入を検討した87年答申は、「大きな意義がある」と認めつつ、「必ずしも意義と必要性が国民に受け入れられているとは言えない」と慎重な内容。その後は留学促進や国際化の観点から、主に大学など高等教育に着目して検討されましたが、大きな変化になりませんでした。
コロナ禍で再び取り沙汰された今回、文科省は移行に伴う課題と対応策を列記しました。
例えば、学年の区切りを変えるので、幼稚園や保育園で現在「同級生」の子たちの間で、誕生月によって小学校入学のタイミングがずれ、保護者の不安や不公平感を招く。移行対応のための教職員の増員が必要。入試や資格試験、新卒採用を行う時期との兼ね合い。必要な法改正も30を超えるとしました。

