学習をあきらめてしまっているLDの子の学びを支える方法とは

教室の中に、「学習をあきらめてしまっている子」はいませんか? LD(学習障害)という特性のある子(以下、LDの子)の学びを支えることについて、 NPO法人えじそんくらぶ代表・高山恵子さんと島根県公立小学校特別支援学級教諭・井上賞子さんにお話を伺いました。
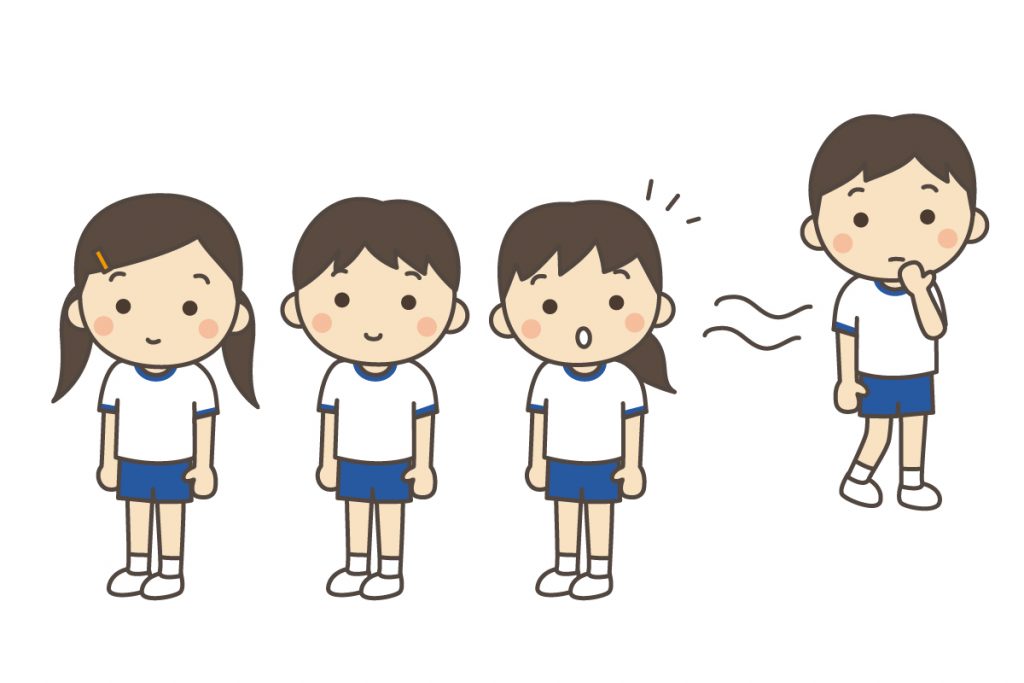
目次
「やれば、できる」が子供と教師を追い詰める
新学習指導要領では、特別支援に関する記述が充実しました。「主体的・対話的で深い学び」の実現のためには、その大前提として、教師が子供の「学びの特性」を理解し、保障する必要があります。
LDの子の学びを支える教育実践を重ねている井上先生は、こんなふうに言います。
「LDの子の学びを支える方法の一つとして、 リハビリテーション協会が提供しているマルチメディアDaisy教科書などの音声教科書の導入をご提案すると、『私は、この子の読みをあきらめたくないんです』と、おっしゃる先生がいます。その先生は、『苦手なことは、努力をして克服した』という御自身の経験に照らし合わせて考えているのでしょう。けれども、その思考回路だけだと、LDの子が抱えている困り感が、矮小化されてしまう可能性があります」(井上先生)
確かに200%の気合を入れれば、LDの子ができることは増えるでしょう。けれどもへとへとになるので、後が続かないのです。
「教師が『やれば、できる』と言うのは、『あなたには、その力がある』と励ましたいからです。けれども、200%の気合で到達したラインを、『やれば、できた』とベースラインにされてしまうと、LDの子は厳しいんです。少しでも気を抜くと、『怠けているからできない』という解釈になってしまいますからね」(井上先生)
多様な選択肢を知ることで、子供の困り感に寄り添える
「この時に大切なのは、教師の側が、学びには多様な選択肢があることを知っていることです。たとえば、『読みが厳しくても、音声教科書であれば情報のインプットが可能』というのは、学びの方法の選択肢の話です。多様な選択肢があることを知っていれば、『この子は、何に困っているのかな?』という問いが教師の側に生まれます。それは、自分の方法〜努力をして克服する〜ではなく、『その子の困り感に寄り添う』という発想が、教師の側に生まれる瞬間だと思うのです」(井上先生)

