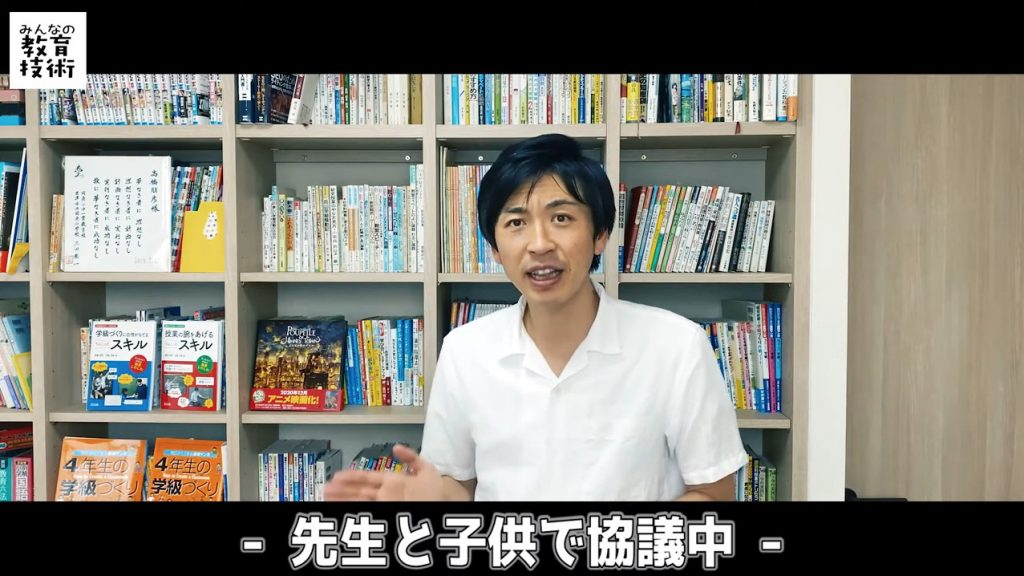自主的に行動できる子供を育てる「ルーティン表」の活用法【動画】

みなさんの学級の子供たちは自分で行動できていますか? 朝の時間や休み時間、つい遊んでしまってやるべきことができない、ということも多いのではないでしょうか。毎日の同じ行動くらいは、自分たちの力でやれるようになってほしいものですね!
そこで教育技術本誌でもおなじみのトモ先生こと髙橋朋彦先生が、子供たちが自ら行動できるようになるための「ルーティン表」の作り方と活かし方についてシェアします!
目次
毎日のことが自発的にできるようになる「ルーティン表」
皆さんの学級の子供たちは、自分たちで行動できているでしょうか?
私の学級では、朝、登校したら自分のランドセルを片付けて朝読書を始めるのですが、友達と遊んでしまって、なかなかできないことがあります。そうすると、朝読書の時間にざわついてしまって、1日中ざわついた雰囲気になってしまいます。
朝の行動は毎日決まっているので、できて当然なのですが、残念ながらできないことがよくあります。
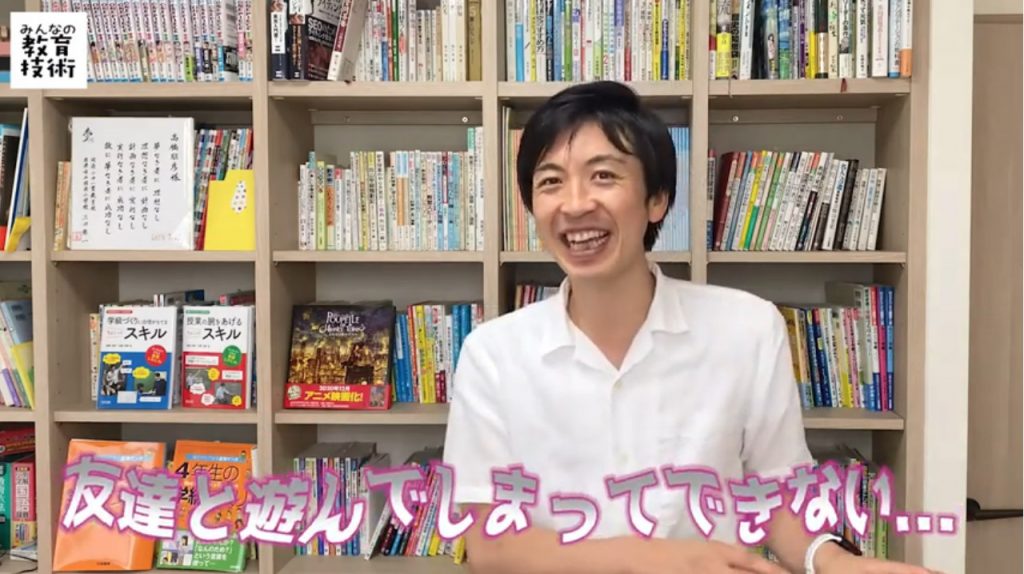
その時、「早くしなさい!」と強めの指導をしてもよいのですが、朝からそういう指導はしたくないですよね。毎日の同じことくらい、自分たちの力でできるようになってほしいものです。
そんな時、私の学級で効果的だったのが「ルーティン表」です! これを使えば、自分たちで見通しを立てて行動できる「第一歩」となります。
今回は、この「ルーティン表」の作り方を3つのステップでご紹介します!
作り方①「困り感」を共有する
1つ目のステップは、「困り感を共有する」です。
たとえば、こんな形で子供たちに投げかけます。
「ねえ、みんな、朝読書の時間、ざわついた雰囲気でうまくできてないよね? これ、どうしたらできるようになるかな?」
(子供たちから意見が出てくる)
「……あ、なるほど。
朝読書の準備を早くすればいいのか!
じゃあ、どういうふうに準備していったらいいか、みんなで考えていこうね!」
このように、みんなで「困り感」を共有します。