発表に挑戦できる学級の雰囲気づくり5ステップ【動画】
関連タグ

クラスの子供たちが積極的に発表するためには、子供が「発表するのは心地よい」と感じる雰囲気が教室にあることが大切。そうなるために、教師はどのように導いてあげればよいのでしょうか。教育技術本誌でもおなじみのトモ先生こと髙橋朋彦先生が、「発表できる学級の雰囲気」をつくる5つのステップをシェアします!
目次
発表しづらい雰囲気を払拭するには
学級の実態によっては、「発表がしづらい雰囲気」…、あるのではないでしょうか。
その大きな原因の一つは、「発表したが間違えてしまった」という、痛みを伴う経験です。
そこで、子供たちに、「発表することは心地いい」と感じてもらうことが必要です。
子供が、
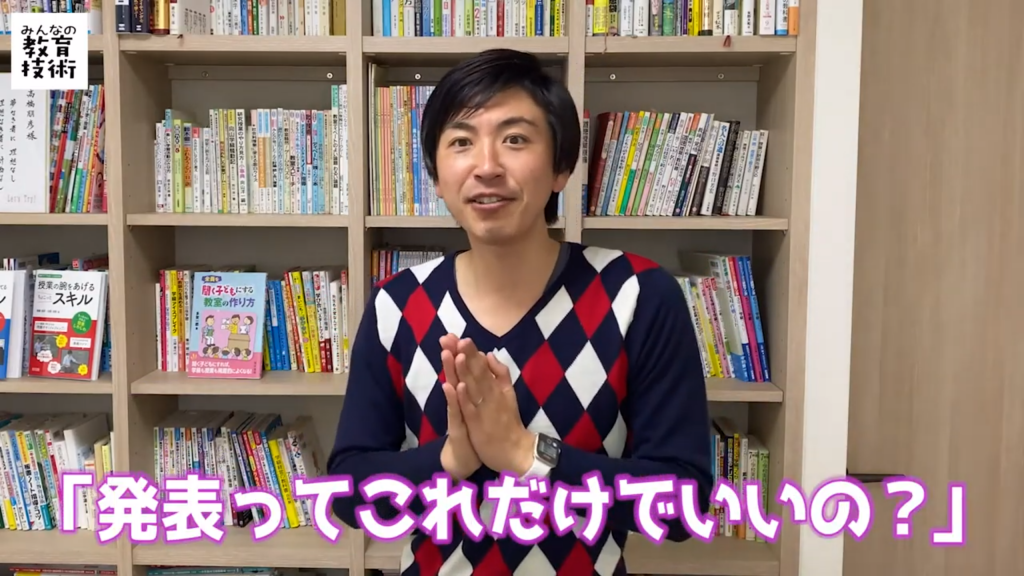
「発表ってこれだけでいいの?」なんて思ってくれたらしめたもの。
今回は、「学級が発表できる雰囲気になるための5つのステップ」の紹介です。
ステップ1 子供が発表の台本を書く
「子供が台本を一つひとつ書く」。
これは、実践している先生も多いのではないでしょうか。
時間がかかりますが、
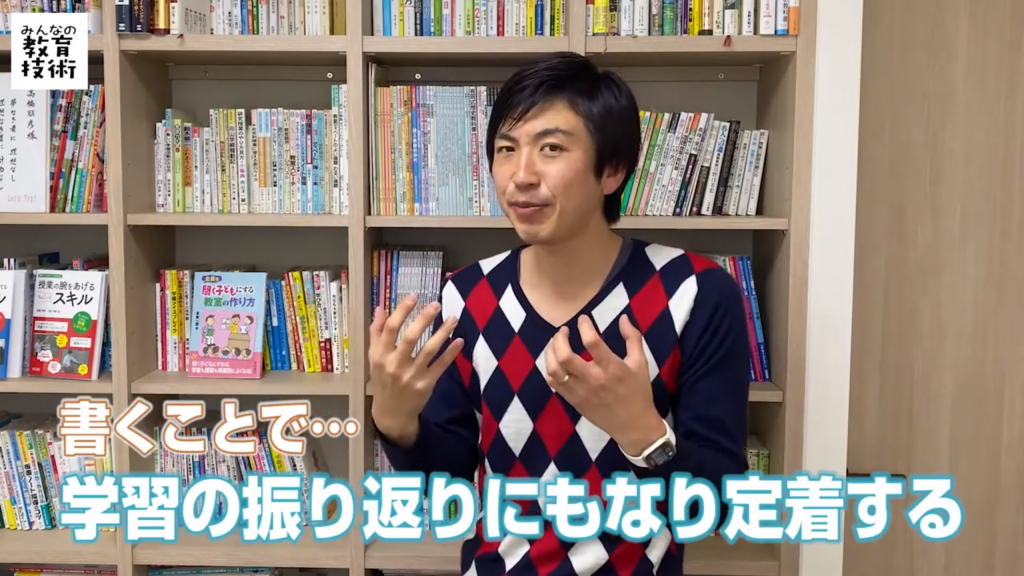
書くことで学習の振り返りになり、定着にもつながります。
慣れてきたらポイントのみを書くようにしてもいいし、台本を無しでできるようにしていってもよいでしょう。

