保護者クレームでの「言った言わない」問題と子どもの証言への対応

保護者クレーム対応の実践スキル 危機を絆に変える技術⑪
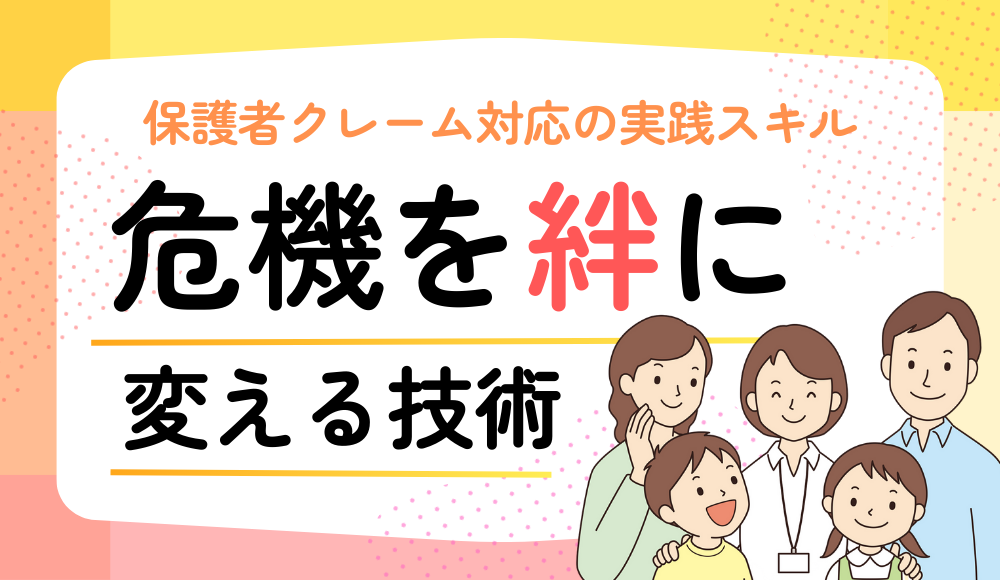
教育現場でのクレーム対応において、最も対処が困難な状況の一つが「言った言わない」の水掛け論です。教師と子ども、あるいは子ども同士の間で生じた出来事について、当事者間で認識が大きく異なる場合、客観的な事実確認が極めて困難になります。今回は、このような事実認定が困難な状況での適切な対応方法について詳しく解説していきます。
執筆/一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事・熱海康太
目次
「言った言わない」問題の構造的理解
「言った言わない」問題が発生する背景には、いくつかの構造的要因があります。まず、記憶の主観性があります。同じ出来事を体験しても、人はそれぞれ異なる角度から記憶し、時間の経過とともに記憶は変化していきます。特に感情的な状況では、記憶の歪みが生じやすくなります。
また、言葉の解釈の違いも大きな要因です。教師が「もう十分です」と言った場合、子どもによっては「もうやめていいよ」と解釈される可能性があります。同じ言葉でも、受け手の心理状態や文脈によって全く異なる意味として受け取られることがあります。 さらに、子どもの発達段階による認知特性も考慮する必要があります。子どもは大人に比べて、事実と感情、客観的出来事と主観的解釈を区別することが困難な場合があります。そのため、子どもが「先生がこう言った」と報告する内容は、必ずしも教師の発言をそのまま反映しているわけではない可能性があります。
第三者仲介による解決アプローチ
「言った言わない」問題では、当事者同士での解決は困難な場合が多いため、第三者による仲介が効果的です。直接の利害関係がない第三者が仲介に入ることで、感情的な対立を避けながら建設的な話し合いを進めることができます。 第三者仲介者の役割は、事実認定を行うことではなく、双方の認識を整理し、今後に向けた建設的な解決策を見つけることです。「○○先生はこのように認識されており、○○さんはこのように感じられたということですね」といった形で、双方の立場を客観的に整理します。
「気持ちとしては事実である」という概念
「言った言わない」問題の解決において極めて重要な概念が、「気持ちとしては事実である」という考え方です。これは、客観的事実がどうであれ、当事者がそう感じ、そう記憶しているという事実は尊重するという姿勢です。
例えば、保護者が「先生は『もうやめていいよ』と言ったそうですね」と主張し、教師が「そのようなことは言っていません」と否定する場合、「お子さんはそのように受け取られたのですね。そう思わせてしまい申し訳ありませんでした」と応答することができます。
この対応により、子どもの体験や感情は否定せずに受け入れながら、教師の名誉も保護することができます。重要なのは、誰が悪いかを決めることではなく、子どもが傷ついた気持ちを理解し、今後の改善につなげることです。
事実確認からの適切な方向転換
「言った言わない」問題では、事実確認を続けることが必ずしも建設的ではありません。むしろ、過度な事実確認は水掛け論を長期化させ、関係性をさらに悪化させる可能性があります。適切なタイミングで事実確認から問題解決に焦点を移すことが重要です。
「事実関係については認識の違いがあるようですが、お子さんが傷ついたお気持ちは理解いたします。今後、お子さんが安心して学校生活を送れるよう、一緒に考えさせていただけますでしょうか」といった表現により、建設的な方向に話を転換することができます。
複数の子どもが関わる場合の対応
複数の子どもが関わる出来事では、それぞれの子どもが異なる認識を持っている場合があります。この場合、どの証言が正しいかを決定するのではなく、それぞれの子どもの体験や感情を理解し、全体的な改善策を検討することが重要です。
複数の証言を整理する際は、共通している部分と相違している部分を明確にします。共通部分については比較的客観性が高いと考えられ、相違部分については各々の主観的体験として理解します。
また、子ども同士の関係性や力関係も考慮する必要があります。上級生と下級生、リーダー格の子どもとそうでない子どもでは、同じ出来事でも全く異なる体験をしている可能性があります。
バナーイラスト/futaba(イラストメーカーズ)

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

