「あの先生、なんで分かってくれないの?」他の先生と考えが合わないときの対処法とは

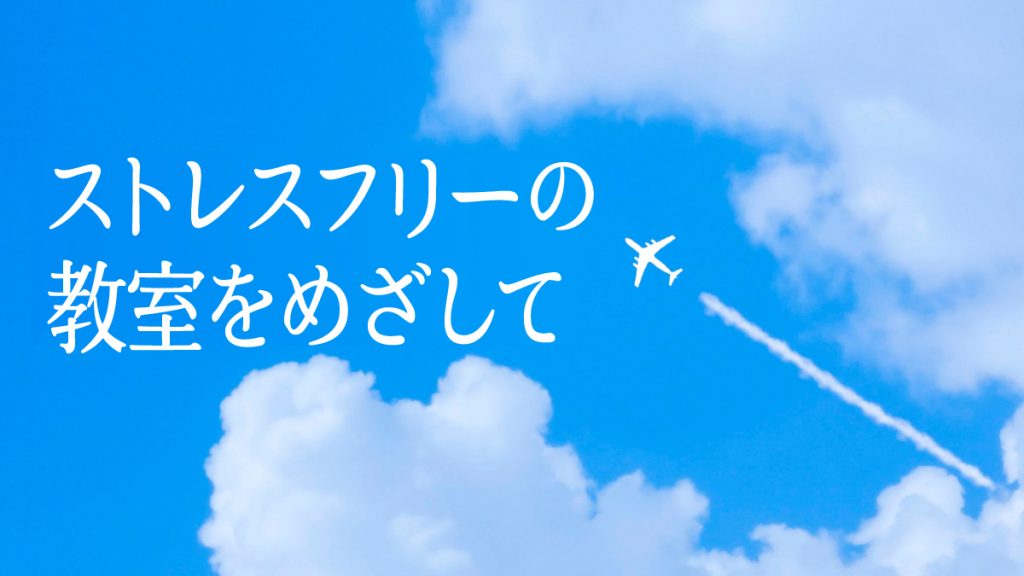
「なんでわかってくれないの?」と、心の中で同僚につぶやいたことはありませんか? 同僚との価値観や指導法の違いにイライラしたり、意見が食い違うことで気まずさを感じたりする場面は、学校現場ではよくあることです。「なぜ分かってくれないのか」「自分のやり方のほうが正しいのではないか」と感じることもあるでしょう。
しかし、ここで改めて考えたいのは、「そもそも他の教師と考えが合わないことは、そんなに悪いことなのか?」という視点です。むしろ、「考えが合わない」というのは当たり前のことであり、それを「ストレス」として受け止めるのではなく、「多様性」として捉え、様々な角度から教育を見つめる機会とすることができれば、私たちはもっと楽に、そして前向きに働けるのではないでしょうか。
本記事では、「他の教師と考えが合わない」とはどういうことなのか、その理由を探りながら、考えの違いをポジティブに受け止めるためのヒントを紹介します。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #39
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
目次
そもそも、なぜ「考えが合わない」のか?
他の教師と考えが合わないと感じるとき、その根底には「価値観」「経験」「環境」の違いがあります。それぞれの違いについて見てみましょう。
①価値観の違い
教師一人ひとりが持っている教育観や指導方針は、それぞれ異なります。例えば、「子どもには厳しく指導するべきだ」と考える教師もいれば、「子どもの自主性を尊重したい」と考える教師もいます。このような価値観の違いがあると、授業の進め方や学級経営の方針について意見が対立することがあります。
②経験の違い
新任の教師とベテランの教師では、これまでの経験が大きく異なります。新任教師は、最新の教育理論を学んできたため、新しい指導方法に積極的なことが多いです。一方で、長年の経験を持つ教師は、「過去の成功体験」を重視し、実践に基づいた指導法を大切にする傾向があります。こうした経験の違いが、教育のスタンスの違いにつながることがあります。
③環境の違い
学校ごとに教育方針や風土が異なるため、以前勤めていた学校でのやり方が、そのまま現在の学校では通用しないこともあります。また、学年やクラスの状況によっても、必要な指導方法は変わります。例えば、落ち着いたクラスでは「自由な発言を促す指導」が適しているかもしれませんが、活発なクラスでは「ルールを明確にする指導」が必要になるかもしれません。こうした環境の違いが、教師間の考え方のギャップを生むことがあります。

教育観はどこから生まれるのか?
教師の教育観は、一朝一夕に生まれるものではなく、長い時間をかけて形成されます。その基盤となるのは、幼少期からの生育環境、学生時代の経験、そして教師としての実践を通じた学びです。それぞれの段階について詳しく見ていきましょう。
①幼少期の生育環境が影響するもの
幼少期の環境は、人の価値観や行動パターンに深い影響を与えます。これは「アタッチメント(愛着)」の研究や、発達心理学の分野でも明らかになっています。教師の教育観も、どのような家庭で育ち、どのように感情を扱われたかによって大きく左右される場合があります。
例えば、家庭が厳格でルールを重視する環境だった場合、「子どもたちにもルールをしっかり守らせるべきだ」という教育観をもつことが多くなります。反対に、自由な発想を尊重する家庭で育った場合、「子どもの自主性を大切にしたい」という考え方をもちやすくなります。
また、幼少期に「怒られることが多かった」人と、「失敗しても受け入れられていた」人では、指導スタイルにも違いが生じます。前者は「厳しく指導しないと子どもは成長しない」と考えがちですが、後者は「子どもが安心できる環境こそが成長につながる」と感じる傾向があります。
②学生時代の経験と「理想の教師像」
自分が受けた教育もまた、教師の価値観を形成する大きな要素です。たとえば、小学生のころに「とても厳しい先生」に指導された経験がある人は、「自分も教師になったら厳しくしなければ」と考えることがあります。一方で、「先生が優しく接してくれたおかげで学校が好きになった」という経験をもつ人は、「できるだけ子どもに寄り添う指導をしたい」と考えることが多いです。
また、大学や教員養成課程で学んだ内容も大きな影響を与えます。最近の教育学では、「アクティブ・ラーニング」や「協働的な学び」が重視されていますが、これを学んだ若手教師と、「教師主導の一斉指導」を中心に学んできたベテラン教師では、授業に対する考え方が大きく異なることもあります。
③現場に出てからの経験
教師として実際に教壇に立つと、それまでの価値観が大きく変わることがあります。新任のころは、「子どもたちの自主性を大切にしたい」と考えていても、学級崩壊のような経験をすると、「やはり教師の統率力が大切だ」と考えが変わることがあります。
イラスト/坂齊諒一
<プロフィール>
春日智稀(かすが・ともき)
2015年より埼玉県公立小学校教諭。体育主任・生徒指導主任・研究主任・教務主任などを担当。
学校心理士/ケアストレスカウンセラー/青少年ケアストレスカウンセラー/アンガーマネジメントキッズインストラクター/アンガーマネジメントティーンインストラクター
日本生徒指導学会・日本学校教育相談学会・日本教育心理学会・NPO日本教育カウンセラー協会/所属

