【連載】坂内智之先生の 愛着に課題を抱えた子が伸びるアプローチ~学級担任にできること~最終回~愛着障害の子どもと共に生きるための、10のQ&A

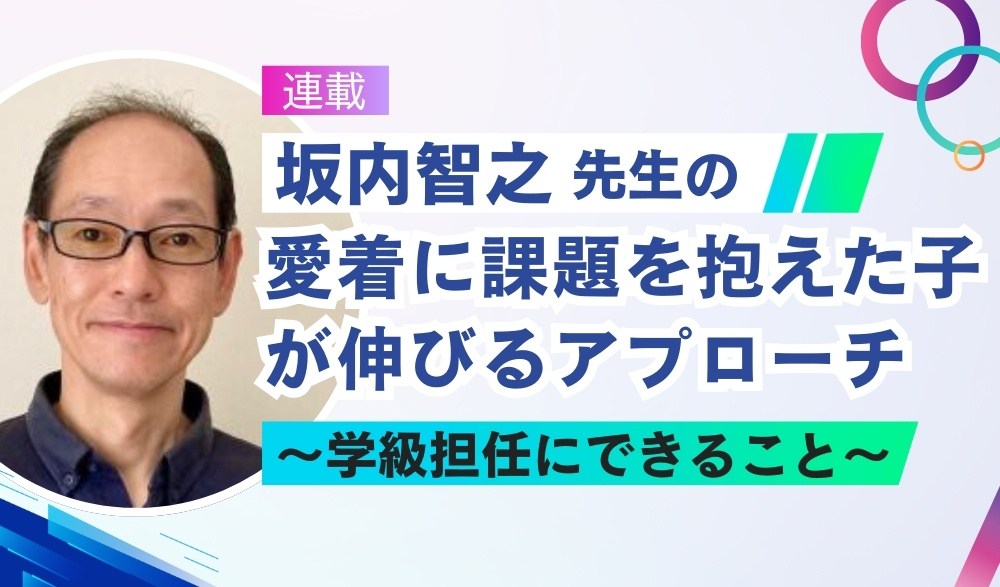
近年、教員たちが対応に苦慮し、学校現場を根底から揺るがしている「愛着障害に苦しむ子どもたち」。そうした子どもたちによって荒れた学級を何度も立て直してきた坂内先生が、今、学級担任に何ができるのかを提案し、これからの学級のあり方について考えていく連載、堂々の最終回。この連載は加筆修正の上、2026年に単行本として刊行予定です。どうぞお楽しみに。
執筆/福島県公立小学校教諭・坂内智之
目次
はじめに
連載もいよいよ最終回となりました。ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。
今回は、これまでの連載を振り返り、ここまでの内容をAI(Gemini2.5pro)に読み込ませ、連載を読んでくださったみなさんの立場に立って、「分かりにくいところ」「もっと詳しく知りたいこと」について、10個の問いを立ててもらいました。
筆者としてどれも「なるほど」と思える問いです。これらの問いに答えることで、読者の皆さんにより深くご理解いただくための大きな手助けになりそうです。
以下、10のQ&A形式でお届けします。
愛着障害の子どもへの対応、10のQ&A
Q1
連載第4回で、愛着障害と発達障害の見分け方について言及されていましたが、現場では判断が難しい場面が多くあります。例えば、状況によって行動が「変動する」ように見える発達障害の子や、逆にこだわりが強く「一定」に見える愛着障害の子もいるように感じます。
坂内先生が、最終的に「この子は愛着の課題が大きいな」と判断する際に、最も重視している子どもの姿や言動はどのようなものでしょうか?
愛着障害と発達障害の最大の違いは、「相手」による言動の違いです。
「愛着に課題を抱えている子」を別の言葉に置き換えるなら、「果てしなく自分を分かってほしい子(人)」だと言えます。
ですから、愛を求めている相手(学校内では担任である場合が多いのですが)の言動にとても敏感で、それ次第で大きく揺れ動きます。愛着に課題のある子をほめると、その行動を何度も繰り返します。例えば、家庭学習についてその頑張りをほめると、毎日何時間もやってきてしまいますし、持久走の走りをほめると、授業が終わっても走り続けるというような行動が見られます。
反対に否定的な言葉にも敏感で、つながりたいと思う相手から否定的な言葉を受けると、何時間も固まったままでいたり、その相手を強く避けるようになったり、激怒したりします。
一方、発達障害の場合は、相手による心の変動はそこまで大きくはありません。通常は相手の言動に大きく左右されず、一定の困難さを抱えているという印象です。
Q2
キーパーソンの重要性は理解できましたが、担任自身が子どもとの相性の問題でキーパーソンになれなかったり、子ども側から強く拒絶されたりすることもあると思います。
その場合、他の教職員(例えば連載第8回の学校司書や養護教諭)にその役割を託すことになると思いますが、担任としてその「セカンドキーパーソン」をどのようにサポートし、連携していけばよいのでしょうか?

坂内智之プロフィール
ばんない・ともゆき。1968年福島県生まれ。 東京学芸大学教育学部卒業。福島県公立小学校教諭。協働学習の授業実践家で「学びの共同体」から『学び合い』の授業を経て、20年以上にわたり、協働学習の授業実践を続ける。近年では「てつがく」を取り入れた授業実践を行う。 共著に『子どもの書く力が飛躍的に伸びる!学びのカリキュラム・マネジメント』(学事出版)、『放射線になんか、まけないぞ!』(太郞次郎社エディタス)がある。

