【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第73回】今どきの教育と敗戦前の教育(その1) ─戦後80年の教育の功罪吟味─

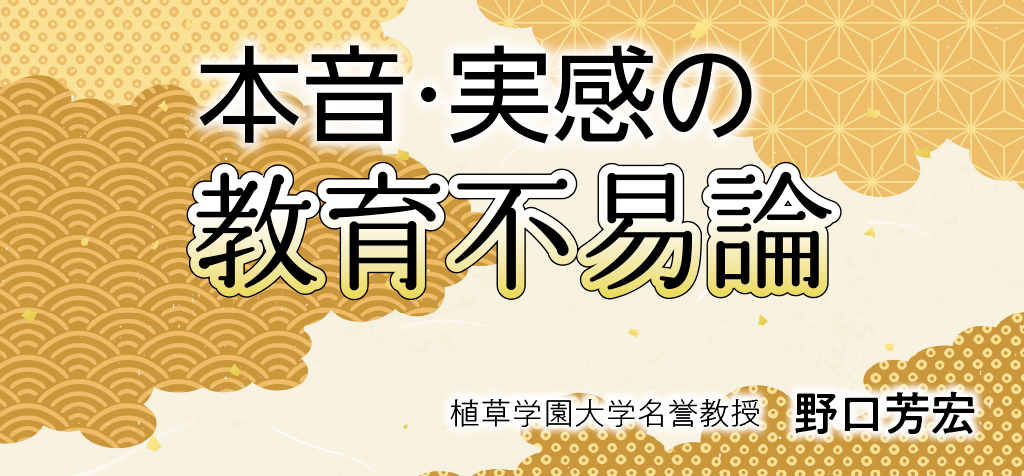
国語の授業名人として著名な野口芳宏先生が、65年以上にわたる実践の蓄積に基づき、不易の教育論を多様なテーマで綴る連載。筆者自身が「遺言連載」だと言うこの連載も、今回から新シリーズに突入。今どきの教育と戦前の教育とを比較吟味し、戦後80年の教育の功罪について考える、渾身の論考と提案です。
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、65年以上にわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。

目次
1、史上最良の時代――戦後80年
戦後80年、昭和100年という日本国にとって重要な一つの区切りとなるのが、令和7年、2025年である。最も新しいビッグニュースは、日本国で初めての女性総理が誕生することになったことに異論を挟む人はあるまい。千葉県の教育長は今年から初めて女性になったし、過去に女性の県知事も誕生している。私の住んでいる君津市でも、市長は女性の石井宏子氏で、広い支持を得て二期めを務めている。戦前の「良妻賢母」「夫唱婦随」という言葉が「通念」だった時代には考えられないことだったが、時代は大きく変わってきた。
個人的な日常の実感としては、日本のこれまでの長い歴史の中で、「最も幸せ」な時代を我々は生きてきたのではないかという思いが強い。正しくは、「生かされてきた」「生かせて戴いた」という思いが強い。
戦争に従事した人はもう殆ど例外的にしかこの世にはあるまい。私は昭和20年8月15日(終戦記念日)には、国民学校の4年生、満年齢では9歳、数え年では10歳の子供であったから、戦争という戦いそのものは知らない。
戦争には行かず、家や郷里で生活をしていた人々は、「戦場の後方。直接戦闘に加わらない一般国民」という意味で「銃後の守りをする一員」であった。女性、子供、老人などで構成されていた。兵隊に行く年齢に該当する人々は在郷軍人などとも呼ばれていた。
食べる物や着る物は極度に乏しく、空襲は毎日のようにあり、学校は授業どころではなかった。そういう時代を潜ったので、令和の「今どき」は本当に、心の底から、「良き時代」だと思っている。
平和で、豊かで、自由である。それが、日常なのだ。まさに「日々好日」である。
唯々有難い。良い国に生まれ、良い人々に囲まれ、良い時代を生きて楽しんでいる。
2、戦後教育の功、三点
私的な管見ではあるが、戦後の教育によって明らかに前進、成長、高度になったこととして、次の三点を挙げてみたい。読者の皆さんのご意見も伺いたいと思う。
① 男女共学
「男女七歳にして席を同じゅうせず」という教えは長く守られて、4年生になると男子組と女子組とに分かれるのが戦前、戦中の常識であった。私は4年生が敗戦の年になったので一年間だけ男女別学を経験している。5年生からは共学になった。
男女七歳にして云々の由来は、中国の礼記にあり、その原文は「七年男女不同席」だそうである。ある解説では「七歳までは子供期であり、大人に求められるような倫理性や道徳性や社会性は必ずしも強調されていなかった。その天真爛漫な姿が子供らしい姿であり、暗黙の了解であり理解であった。そして、七歳以降の人間には倫理性や道徳性や社会性が求められるようになる。男女七歳云々はそのような社会風土の諺である。」と解かれている。
敗戦によって、男女別学は、男尊女卑の考えや孤立主義との見地から、またGHQの指示による学制改革の影響もあって共学制になった。
これは素晴らしい改革であり、戦後教育最高の快挙と私は考えている。女性の選挙権も戦後からのことであり、今なら当然の男女同権思想も日本の新たな大きな前進の一歩として評価すべきだろう。
農地改革も、小作者と地主の差別を解消する上で大きな改革として評価すべきだろう。但し、教育とは直接の関係はないのでこれ以上は触れない。
② 福祉教育
第二に取り上げたいのは福祉教育の前進である。私は「座敷牢」という言葉を知っている。精神障害や知的障害の子供達は世間に知られないように、学校に行かせず、親にとっても、悲しく辛い待遇を余儀なくされていた。座敷牢というのは、人に見られたくないような子供や大人を、外に出られないように部屋の中に監禁しておくことである。子供心にも、ひどく可哀想に思われたことである。
今は、特別支援学校と呼ばれる仕組みの中で、そのような子供達も、のびのびと楽しく、大切に守られ、育てられるようになり、その中で差別的偏見も大きく改善され、そのような子供を持つ家庭も、親も、そして本人も、胸を張って生きられるようになった。まことに嬉しいことである。
③ 音楽科教育
第三には、戦後の教科教育の中で目覚ましい発展、充実を見たのは音楽教育だというのが私の考えである。
私が4年生まで過ごした国民学校では、音楽は専ら「歌唱」であり、オルガンに合わせて歌って楽しむという授業に終始した。さすがに、教科の名称としての「唱歌」という言葉は使われてはいなかったが、そして、戦時下であった国民の日常生活は日を追って窮乏を避けがたい中にあったこともあってか、楽器などというものは絵でしか見たことがなかった。あったのは、せいぜい祭りの「太鼓と笛」ぐらいのものだった。
今は、多くの子供がピアノ教室に通い、音楽の時間に子供が実際に用いる楽器も豊富になり、音楽専科の教員も置かれるようになり、日常生活の中に「音楽を楽しむ」という文化も定着した。
田舎育ちを明かすようだが、「歌」というものは、「酒」の席でこそあったが、酒のない所で大人が「歌って楽しむ」などという姿はついぞ見たこともないような子供時代だったから、現在の音楽の普及は、まさに隔世の感を深くするのである。 以上、まさに私的管見の域を出ないが、実感を伴う戦後教育の功を挙げれば、上記の三点である。むろん、このほかにもその人、その人によって挙げればいろいろとあろうけれど、それらを教示して貰えれば幸いである。

3、戦後80年の教育は、成功しているか
いろいろの場で、「日本の教育はこのまま進めていけばいいと思うか」と問い、「いい、と思う人は◯を、いけないと思う人は✕を書いて下さい」と指示をすることがある。ぜひ、読者の皆さんも、いろいろの場で、多くの人に問うてみてほしい。
これは、直感的な印象を問うている問いである。「どんな規準で決めるか」とか、「どんな立場で◯✕を決めればいいのか」などという分析は要らない。それぞれの、今の単純な印象で十分なのである。
多くの人が、その日、その日の多忙の中で、このようなことは殆ど自問することはないだろうと思う。そうであればこそ、こういう問いが必要なのだ。立ち止まって、身の廻りを眺め、来し方を振り返り、今のままでよいのか、よくないのか、それらは、どんな根拠や理由でそう言えるのかなどなどを、自分なりに考え、友達とも話し合ってみることが大切ではないか。
さて、私のこれまでの経験、体験からすると、「このままでよい」と答える人数は、寥々たるもので、殆どの場で10%未満である。「そんなことはない」という人もあるかもしれない。楽観的な人はそう思うだろう。それはそれでよい。
だが、私の親しんでいる仲間は、私と同様の実感を報告してくる。
身近な学校場面で言えば、次のようなことが指摘される。
a、子供の問題
ア、授業中に歩き廻る。注意を聞かない。
イ、ノートを取らない。求めると反抗する。
ウ、私語が多い。
エ、姿勢が悪い。
オ、宿題をしない。
b、保護者の問題 ── 一部の親だが──
ア、クレームが多い。一方的に話す。
イ、個人的関心に合わないと賛同を要求する。
ウ、担任を越えて管理職や教委に訴える。
エ、親同士が電話やメールで繋がる。
オ、役員を引き受けない外野意識が強い。
c、同僚、若者の問題
ア、共に学ぶという向上心に乏しい。
イ、自分の考えで実践したがる。
ウ、進んで学ぶ姿や意欲に乏しい。
エ、本を読まない。自分を語らない。
オ、引き籠って独りを楽しむ感じが強い。
カ、パソコンなどには詳しい力がある。
d、上司、先輩の問題 ──身近な例から──
ア、おおらかでいつも明るく、穏やか。
イ、保身色が強くて、万事は先例通り。
ウ、上から目線で管理色が強い。
エ、保護者本位、教委本位、子供心本位
オ、理想や夢を語らない。現状維持派。
このように書くと、私の教員仲間は「不平分子」の集まりのようにとらえられかねないが、それは私の伝え方が悪いのだろう。私と一緒に学ぼうとしている面々は、掛値無しに「一級教員」だと私は確信している。よく本を読み、学び、誠実で熱心だ。
自分にとって大切な休日なのに、身銭を切って学びに参加し、発言もし、実践を公開し、レポートも作ってくる。そういう仲間であって、少なくとも自己中心的で批判好きなどという類いには属さない。
先のようなことを、口先で言って済ますのではなく、積極的に他者に働きかけ、サークルを作り、誘い、そしてよりよい教師たらんと努め続けている人達ばかりである。
それなりに、理想を持ち、目指すものがあるからこそ「現状満足」という訳にはいかないのだと思う。私は、こういう仲間との繋がりを、私自身の大きな喜びとも、誇りともして今日まで歩んできた。これからも、そうしていくつもりである。
以上のような現状認識に立てば、「日本の教育」は、「このままでよい」という訳にはいかない」という考えになり、先の問いには×をつけたくなるのであろう。同感である。
4、戦後80年を生きて思う
私は昭和11年2月の生まれで、昭和、平成、令和を生きてきた。満で89歳、来年2月17日で満90歳、卒寿を迎える。幸い健康に恵まれ、もうちょっとこの世で暮らせそうだ。22歳で教師になり、67年をずっと教職に関わらせて戴いた。
どこへ出かけても、私が最年長になり、乾杯の音頭は私になることが多い。そこで、この連載は、恐らく遺言連載になろうから、絞りこんだことだけを書こうと考えている。もはや昭和も遠くなりつつあるのだが、戦後80年の教育は、一言で言えば、「先へ、先へ」という歩みだったように思う。常套句のように「これからの時代を生きる子供は」という前提の下に、先行き不透明(それは常に当然のことだ)の時代の備えにふさわしかろう教育策をとってきた。
その結果が、不登校、苛め、暴力、自殺が「過去最多」となったのだ。「何が足りないのか」「何が欠けていたのか」という「振り返り」「反省」を欠いた(進行中の改訂指導要領指針にもこの片鱗もない)策だったのではないか。昔の日本の教育、伝統の価値との比較と吟味をしつつ、本音・実感・我がハートの提言をしたいと考えている。率直な御批判を期待しています。

イラスト/すがわらけいこ 写真/櫻井智雄

