「探究」の充実と情報活用能力の育成を実現する【次期学習指導要領「改訂への道」#特別版02】

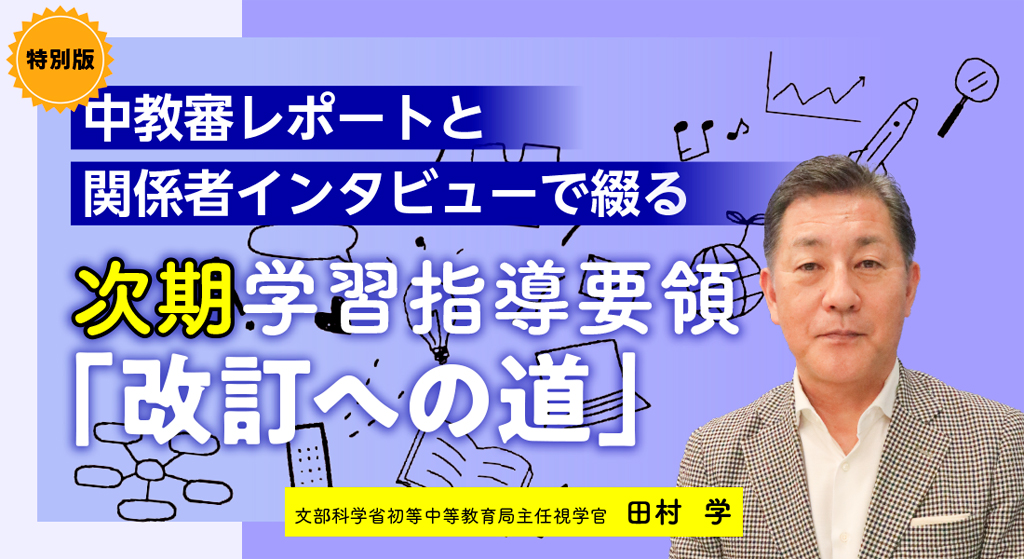
前回から、この連載の特別版として、文部科学省の田村学主任視学官に、「探究」と次期学習指導要領というテーマでお話を伺っています。今回は、情報活用能力の育成を「探究」の中に位置付けることなどについて、お話を伺います。
▶「探究」への意識変革には「インパクトと手立てと手応え」の 3 点セット【次期学習指導要領「改訂への道」#特別版01】
目次
「探究」の充実を実現していくために、デジタル学習基盤機器を積極的に活用していく
「探究」と情報活用能力の相性がよいということは読者の方々もお感じになると思います。何かを調べるときに「ちょっとネットで調べよう」とか、データ分析もデジタルを活用したほうが簡単だとか、人に発表してプレゼンするときも、紙芝居を作るよりスライドショーにしたほうが分かりやすい、手軽に作り直しもできるなどと考えられます。「探究」との親和性が高いということは多くの方が実感できることでしょう。ですから、この両者を一体的に育成することを目指そうとしているわけです。
教育課程企画特別部会で多く出ていた意見には、情報活用能力というデジタル学習基盤の利活用や、リテラシーの習得のために「探究」があるのではないという考えです。そもそも子供自身が「探究」し、「追究していきたい」という真剣な学びがあって、それを行うときにデジタル学習基盤を活用すると、とても便利だし親和性も高いし、それを使って「探究」することでデジタルを活用する情報活用能力も身に付いていく可能性も高まるということでしょう。
あくまで目的は「探究」を充実、実現していくということで、その学習過程において、デジタル機器を便利な方法の1つとして積極的に活用していくということです。その関係のほうが両者にとって好ましいとの考え方です。デジタル学習基盤の利活用スキルやリテラシーも、それだけを単独で取り出してやってしまうだけだと、子供にとって楽しい学びになるとは思えません。
一般的な情報活用能力の獲得過程を考えてみても、順序よく学んだことも一定程度はあるかもしれませんが、多くの場合は目の前の問題を解決していく過程で使っているうちに獲得していることが多いはずです。そのようにアウトプットしていく活用過程で試行錯誤しながら獲得するからこそ、別の場面でも使えるのかもしれません。そのような学習をしていったほうが、情報活用能力にとっても、「探究」にとってもWin-Winになるわけで、その意味でも、目的と手段が逆転するような本末転倒な学習にならないことがポイントとなりそうです。

