11月の学級の荒れを未然に防ぐ4つの手立て|新任教師のための学級経営講座 #10

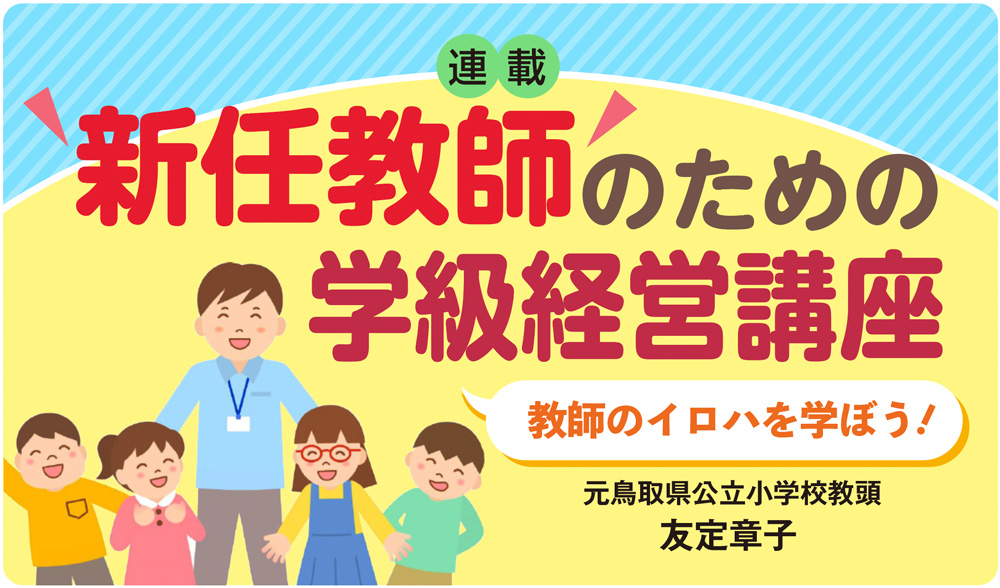
初めて学級担任になった新任教師にとって、「学級経営」は不安なもの。そこで、学級経営の基本が学べる連載をお届けします。毎月の準備や進め方などをその月の学校行事なども絡めながら紹介。鳥取県の公立小学校で、若手教師の育成に尽力してきた友定章子先生が、新任教師でも分かりやすいように解説します。今回は、11月に起こりがちな学級の荒れを未然に防ぐ手立てについて解説します。
執筆/元鳥取県公立小学校教頭・友定章子
目次
はじめに
前にお伝えしたように、6月と11月は、“学級の荒れ”が起こりやすい月として挙げられます。先生方の学級の今の状態はどうですか? 学級担任としてどの子にとっても楽しくて心地よい学び合う集団づくりを目指していても、集団であるからこそぶつかり合いや軋轢があることも事実です。また、個性の相乗効果はよいほうにばかり働くとは限りません。だからこそ学級経営は、一人一人の子供を把握するだけでなく、学級の状態や子供たちの関係性にも配慮する必要があるのです。
ところで、インクルーシブ教育という言葉をご存じでしょうか。SDGsにも掲げられている“だれ一人取り残さない”という理念とも関連しています。インクルーシブ教育とは、障害の有無やその他の違いにかかわらず、全ての子供たちが同じ場所で共に学び合い、互いに尊重して支え合い、多様性を認め合える社会を目指す教育です。そのためには、一人一人の教育的ニーズを把握し、合理的配慮が必要になります。
これらのことを踏まえて、11月に“学級の荒れ”が起こらないための手立てについて、具体的に考えてみたいと思います。
1.学級の実態を把握する
Q-U(Questionnnaire-Utilites)の実施
学校生活における児童生徒の意欲や満足度、学級集団の状態を把握するための心理テスト Q-U(早稲田大学の河村茂雄教授が「楽しい学校生活を送るためのアンケート」として開発)があります。このテストは、多くの自治体、学校が採用していると思います。
このQ-Uは、学校生活における児童生徒の意欲や満足度、学級集団の状態を把握するための心理テストです。所要時間は15分程度で1年生でも答えることができます。具体的には、学校生活意欲として、授業や学校生活への意欲を測る尺度と、クラスの雰囲気や友人関係への満足度を測る尺度から構成されています。個人の結果を座標にプロットしていくことで、現在の学級集団の中のルールとリレーション(子供たちの関係)がどのような状況なのかを知ることができ、学級の状態(満足型の集団、硬さが見られる集団、ゆるみが見られる集団、荒れはじめの集団、崩壊した集団)を捉えることができます。また、どの子が不満足を抱えているのかも把握することができ、支援の必要な子が浮き彫りになります。
Q-Uを実施することによって、曖昧に捉えていた学級の状態を冷静に捉え直すことができるでしょう。
共通の目標をもつ学校行事で学級をまとめる

2学期は、運動会や学習発表会、文化祭や音楽祭など、学級の力を合わせて取り組む学校行事がたくさんあります。みんなで協力して充実感や達成感を味わうことで、学級全体をまとめるチャンスがあります。
目標やゴールイメージについて共有して学校行事に取り組んだり、その中で教師が子供同士の関わりを意図的に仕組んだりすることで、日ごろ気付かなかった友達のよさを認め合うことができます。
また、学級でその行事の目標に対する話合いをしたり、子供が自分の目標を可視化したりすることで、学級の一員であることを再確認します。

