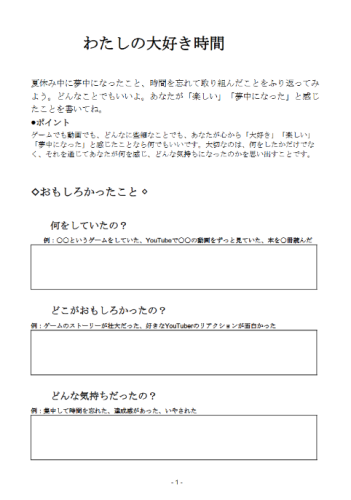どこにも行かなかった夏休みだっていいじゃない!「思い出の共感」から始める、ステキな2学期のスタートアップ

「夏休みの思い出は?」と尋ねられ、「どこにも行かなかった」と答える子が増えています。猛暑や物価高、デジタル化が夏休みを変えました。特別な体験がなくとも、ささやかな日常を肯定的に語らせるには? そして、その語りを通して、夏休みで弱まったクラスの絆を再構築するにはどうすればいいでしょうか。
【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~
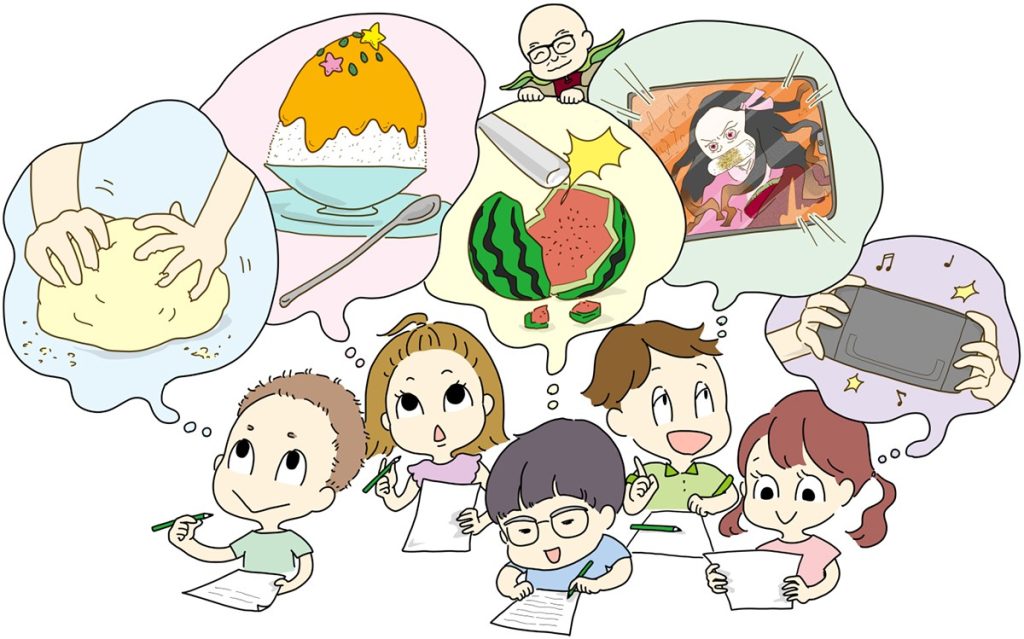
目次
夏休みの変化「移動の夏」から「滞在の夏」へ
それぞれの夏を過ごした児童たちが、再び学級に帰ってきました。かつて日本の夏休みは、家族そろっての帰省や旅行、お祭りなど、屋外での活動が中心でした。しかし、現代っ子たちの夏休みは、「家に滞在する夏休み」へと変わった感があります。
災害級の猛暑、昨今の物価高と、インバウンドによる観光地の混雑激化が最も直接的な要因でしょうか。さらに保護者は、パンデミックによってステイホームが習慣化している、という要因もあるでしょう。
教員の意識をアップデートしよう
昔の夏休みを知っている大人からすれば、「滞在の夏」は少し物足りないものに感じられるかもしれません。しかし、エアコンの効いた部屋で動画を見たり、SNSで友人とつながったりする時間は、決して物足りないものではありません。むしろ、現代の子どもたちにとっては、自分なりの居場所や楽しみを深く掘り下げ、心を豊かにする大切な時間であり、これこそが新しい夏の形と言えるでしょう。
夏休みが変化している今、わたしたち教員も「夏休みはこうあるべき」という固定観念を見つめ直す必要があります。夏は外で遊び、特別な思い出をつくるもの、そうした無意識の思い込みが、児童の語りを狭めてしまうことがあるからです。
夏休み明けに「どこに行った?」と尋ねて、答えに詰まる子がいるとしたら、それはその子の経験が乏しいからではありません。わたしたちの問いかけが、その子が過ごした「滞在する夏」の生活に合っていないと考えるべきです。
たとえば、「家でおじいちゃんと囲碁をした」「冷たいスイカを種を飛ばしながら食べた」「新しい料理に挑戦して焦がしてしまった」といった、日常の小さな出来事も、その子にとってはかけがえのない大切な体験です。特別な場所へ行った経験だけが「価値ある思い出」ではありません。
令和の学級経営で求められているのは、特別な経験を自慢できる子を育てることではなく、自分の体験をどのようなものであれ価値あるものとして言葉にし、他者と共有できる子を育てることです。
「語りにくさ」をなくす指導の言葉
児童に「夏の思い出を話してごらん」と尋ねたとき、すぐに語り出せない子は少なくありません。とくに「どこにも行かなかった」と感じている子どもにとって、この問いかけは「自分には話せる思い出がない」という引け目やプレッシャーにつながることがあります。
そこで重要になるのが、担任が投げかける指導の言葉です。これらの言葉は、児童が安心して自分の経験を語れるための土台となります。
安心させる言葉
夏休みの思い出って、どこかに出かけた話じゃなくても大丈夫だよ。家でYouTubeを見て大笑いしたことや、ゲームに夢中になったことでも、それは立派な思い出だからね。
等身大の言葉
わたしも今年は旅行に行かなかったんだ。部屋でエアコンを効かせながら、大好きなアイスを食べてマンガを読んで過ごしたよ。
価値を引き出す言葉
『どこにも行かなかった』と思っているかもしれないけれど、その中にもきっと宝物があるはずだよ。何にいちばんハマってた? どんなときにいちばん笑った?
寄り添う言葉
何もしなかったって思う子もいるよね。でもね、その余白の時間こそが、実は新しい発見や次のステップにつながる大事な時間なんだよ。
大切なのは、特別な出来事だけでなく、日常のささやかな体験にも価値があることを伝えることです。
語りを促すための活動アイデア<ワークシートダウンロード可>
児童が安心して語り、表現する土台を整えるには、具体的な「仕掛け」も必要です。ここでは、誰でも参加できる、負担の少ない活動を2つ紹介します。「誰でも語れる入り口をつくる」という視点から、児童それぞれの心の耕しを行います。
わたしの大好き時間シート
夏休み中に夢中になったこと、時間を忘れるほど熱中したことを書き出すシートを作成します。ゲームや動画、読書、料理の手伝いなど、どんな小さなことでも構いません。重要なのは「何を体験したか」だけでなく、その体験を通じて「どこが面白かったか」「どんな気持ちになったか」を記録させることです。この活動は、内面にある感情や思考を掘り起こし、言葉にする訓練になります。