小学校の教室で実践するポジティブ行動支援(PBS)~子どもが安心して学べる環境づくり~(後編)

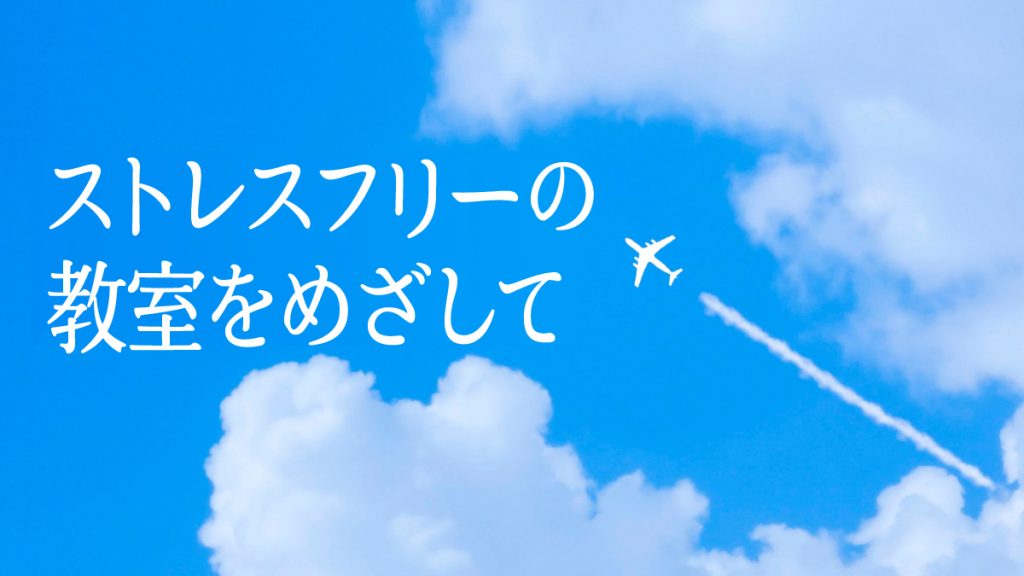
前回の記事では、ポジティブ行動支援(PBS)の基本的な考え方や、応用行動分析(ABA)のABCモデルを紹介しました。PBSは、子どもの良い行動を増やし、問題行動を減らすための科学的なアプローチであり、「子どもを叱ることなく適切な行動を増やす」ことが目的です。
では、実際にどのような形でPBSを教室で活用すればよいのでしょうか? 今回は、小学校の現場でPBSを効果的に実践するための具体的な支援方法を紹介します。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #33
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
小学校の教室で実践するポジティブ行動支援(PBS)~子どもが安心して学べる環境づくり~(前編)
→ https://kyoiku.sho.jp/396077/
目次
前回のおさらい
応用行動分析では、「ABCモデル」と呼ばれる考え方で人の行動を整理すると、その行動の背景が理解しやすくなります。
A(Antecedent:先行条件) … ある行動が起こる前の状況やきっかけ
B(Behavior:行動) … 子どもが実際にとる行動
C(Consequence:結果) … その行動の後に何が起こるか
応用行動分析では、「人の行動にはかならず理由(目的)がある」と考えます。仕組みはいたってシンプルで、行動の後にメリットがあればその行動は増加し、行動の後にデメリットがあればその行動は減少します。
行動の後にメリットがある場合:例「おなかが空いた」
A(先行条件):おなかが空いた。
↓
B(行動):戸棚を開けてお菓子を食べる。
↓
C(結果):空腹が満たされる。
こうした場合は、戸棚を開けてお菓子を食べることにより空腹が満たされるというメリットがありますので、次に空腹になった場合にも戸棚を開けてお菓子を食べるという行動が繰り返されることでしょう。
行動の後にデメリットがある場合:例「信号を無視する」
A(先行条件):急いでいる。
↓
B(行動):信号を無視する。
↓
C(結果):車にひかれそうになる。
この場合には、信号を無視した結果、あやうく車にひかれそうになるというデメリットがありますので、次に急いでいたとしても信号を守ることでしょう。
PBSと従来の指導法の違い
では、PBSと従来の指導法は、どのように違いがあるのでしょうか。PBSは、「子どもの行動を改善する」という点では従来の指導法と共通していますが、そのアプローチが異なります。
| 項目 | PBS(ポジティブ行動支援) | 従来の指導法 |
| アプローチ | 望ましい行動を増やす (問題行動を相対的に減らす) | 問題行動を減らす (良い行動とは切り離して考える) |
| 強調する ポイント | 望ましい行動の強化 | 問題行動の抑止 |
| 対応方法 | 望ましい行動に注目し、肯定的なフィードバックを行う | 問題行動が起きたときに罰を与える |
| 結果 | 子どもが主体的に行動を変えるようになる | 罰を避けるための行動が増える |
従来の「罰を与えて行動を抑制する指導」は、一時的な効果はありますが、子ども自身が「どうすればよい行動ができるか」を学ぶ機会を奪ってしまうことがあります。一方PBSでは、「この行動をしたら褒められる」「良い行動をすると気持ちがいい」という成功体験を積ませることで、長期的に望ましい行動を定着させることができます。


