小学校の教室で実践するポジティブ行動支援(PBS)~子どもが安心して学べる環境づくり~(前編)

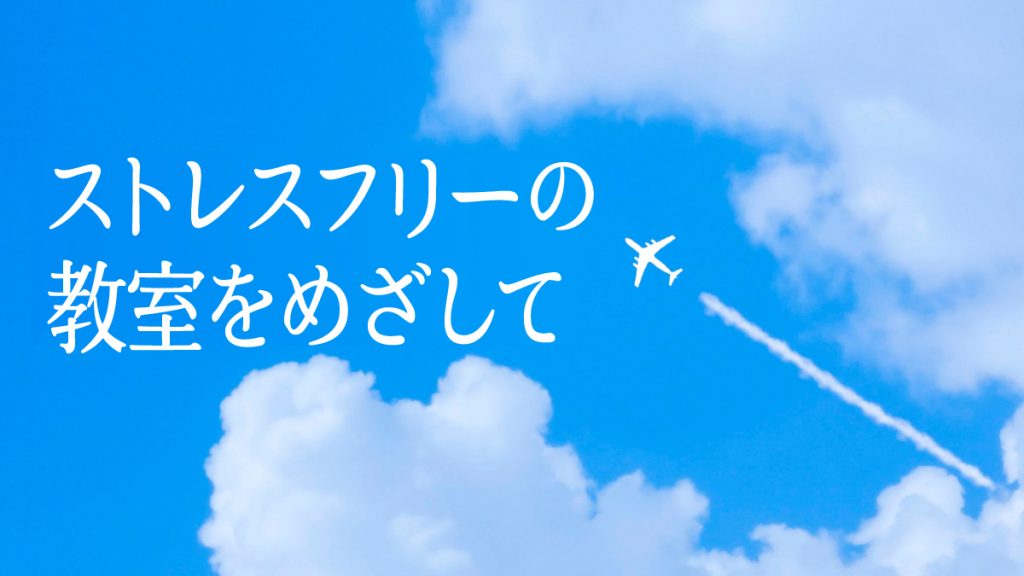
教室での子どもたちの行動をどのように支援し、より良い学びの環境を作るかは、教師にとって大きな課題です。叱ることが増えると、教師自身もストレスを感じ、学級経営が難しくなることがあります。しかし、子どもたちの問題行動に焦点を当てるのではなく、「望ましい行動を増やす」ことに注力するアプローチが「ポジティブ行動支援(Positive Behavior Support=PBS)」です。
今回から、「前編・後編」の2回にわたって「ポジティブ行動支援(PBS)」についてお届けします。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #32
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
目次
ポジティブ行動支援(PBS)って?
ポジティブ行動支援(PBS)は、子どもたちの良い行動を強化し、困った行動を減らすことを目的とした教育的アプローチです。単なる「叱らない指導」ではなく、科学的な理論に基づき、教師が環境を整えながら子どもたちを支援する方法として注目されています。特に、小学校では「ルールを守る」「友だちと協力する」「授業に集中する」などのスキルを身につけることが重要になります。
なぜポジティブ行動支援が大切なのか。それは、子どもたちは「叱られる」よりも「認められる」ことで成長するからです。問題行動を減らそうとするだけではなく、子どもたちが積極的に良い行動を取れるように促すことが、学級経営を円滑にし、子どもたちの自己肯定感を高めることにつながります。
ポジティブ行動支援の理論的背景
ポジティブ行動支援の理論的な枠組みとして、「応用行動分析(Applied Behavior Analysis=ABA)」があります。これは、行動には必ず「理由」や「きっかけ」があり、それを理解することで行動を変容させることができるという考え方に基づいています。
応用行動分析では、「ABCモデル」と呼ばれる考え方が基本になります。
A(Antecedent:先行条件) … ある行動が起こる前の状況やきっかけ
B(Behavior:行動) … 子どもが実際にとる行動
C(Consequence:結果) … その行動の後に何が起こるか
例えば、授業中に立ち歩いてしまう子どもがいるとします。
「A(先行条件)」として、難しい課題が出され、子どもがストレスを感じたとします。
「B(行動)」として、子どもは集中できずに教室内を歩き回ります。
「C(結果)」として、教師が注意し、クラスメイトが注目します。
このような場合、注意を受けることで子どもが「注目を得る」結果になっているため、同じ行動を繰り返す可能性があります。そこで、教師が「先行条件(A)」を変え、「適切な行動をとることで注目を得られる仕組み(C)」を作ることで、立ち歩きを減らすことができます。
応用行動分析を活用すると、「なぜこの行動が起こるのか?」を考えながら、より効果的な指導を行うことができます。PBSは、この理論に基づき、子どもの行動を「問題」と捉えるのではなく、「どうすれば望ましい行動が増えるか」という視点でアプローチする方法です。

