昔、誰かに読みや解釈を押し付けられることが嫌だった【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #41】
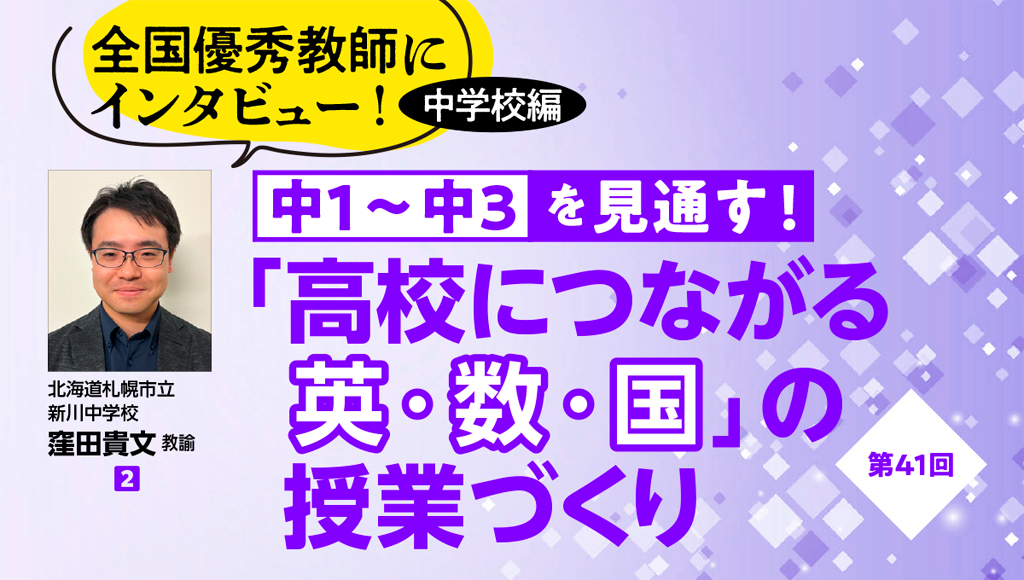
前回から、今年(令和7年)10月9・10日の両日に、全日本中学校国語教育研究協議会の全国大会で授業公開を行う、札幌市立新川中学校の窪田貴文教諭に、単元や授業づくりの考え方とその考えを象徴する単元・授業について伺っています。今回は、前回伺った、2年生の「走れメロス」のような単元・授業の背景となる、窪田教諭の単元・授業づくりの考え方について紹介をしていきます。
上記の北海道札幌市での全国大会の詳細は、以下URLよりご覧ください。
https://www.zenchukoku.com/第54回全中国北海道大会/
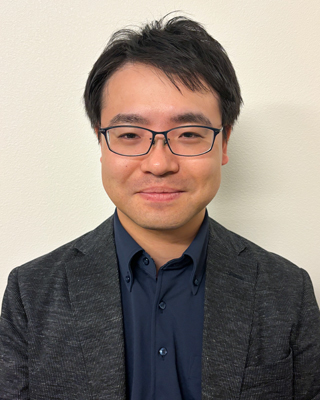
窪田貴文教諭
目次
子供たちの考えを拾い上げながら「問い」を設定することが大事
前回紹介した単元も、次回紹介する単元も、文学的教材の「読むこと」の領域なのですが、そこには窪田教諭自身が、子供時代から非常な読書家だったことも影響していると話します。そして、そこに窪田教諭自身の単元・授業づくりの考え方も強く表れていると話します。
「私の子供時代は、ちょうど『ハリー・ポッター』シリーズが毎年発刊されていた頃で、私も読みましたが、映画化されたとき一番驚いたのは、登場人物のハーマイオニー役がエマ・ワトソンだったことです。エマ・ワトソンはよい役者さんですが、私が本からイメージしたハーマイオニーとは異なっていました。そのため、『この物語はこうなんだよ』と、違った解釈を無理に押し付けられているようで嫌だったのです。大人になった今では、映画と原作は異なるということを重々承知しているのですが、子供のときには納得できなかったのでしょう。
それと同様に昔、文学的教材の授業を受けていて違和感があったのは、『この物語の主題はこうなんだよ』『この教材はこういう意味があるんだよ』と、先生から読みや解釈を押し付けられることでした。もちろん今、教師という立場になると、『限られた時間の中で授業を行い、定期テストでの教材の読みに対応するために、仕方ない部分もあったのだろう』と想像することはできます。しかし、私はあくまでも教え込むのではなく、子供たち一人一人が自ら深く読むことを助けるような授業づくりをしたいと考えているのです。
ですから私の『読むこと』の授業では、必ず0時に初発の感想を書かせるのですが、そこから『みんながこう感じたのなら、これを考えるのがよいんじゃないかな?』と、子供の声を拾って『問い』を設定し、その解決を図ることで、子供が主体的な読み手として学習を進め、終えるような単元・授業づくりを心がけています。
そのような形の単元構成をすると、子供たちは自ら文章に触れていきます。『自分はこう思う』という思いがあるので、私や友達から『それはなぜ?』と問われたときに、本文の中から根拠を探し始めます。もちろん、私自身も『どうして?』と問われたら、本文の描写を根拠として、『こう書いているから』とか『こうは書いてないから』と説明するように話しています。そのように本文の描写を根拠に説明をすることは、『言葉による見方・考え方を働かせる』国語としては重要なポイントですし、それを子供たちが自ら行っていくためには、主体的に読もうとしたくなる『問い』があることが大事だと思うのです。
もちろん、子供たちは(特別な指示がなくても)初発の感想は書けるのですが、それがなぜなのか、説明できないことがあります。それがなぜなのか、本文の描写を根拠に対話できるようにするためには、子供たちの考えを拾い上げながら『問い』を設定することが大事だと考えています」

教材研究を行った上で明確なねらいをもって、初発の感想を子供たちに聞いていく
では、子供の思いに沿った「問い」が設定されれば、よい単元・授業になっていくのでしょうか。窪田教諭は、次のように事前の教材研究と「問い」の関係を説明します。
「各教材には、それぞれ配置されているねらいがあります。例えば、文章構成に着目するものもあれば、現在と回想という時系列に着目するものもあるでしょうし、心情の変化を読み取らせるものもあるでしょう。そのような教材の適材適所を考えた配置がなされています。
当然、そのようなことについても事前の教材研究の中で考え、『ここに着目させたいな』という思いをもっているわけです。ですから、初発の感想を書かせるにも、漠然と『どう思う?』と聞くのではなく、ねらいに沿って少し絞るのです。例えば、登場人物に着目させたい場合は、『この物語は誰が何をする物語ですか』ということを聞いておくのです。
あるいは先日行った『大人になれなかった弟たちに……』という戦争教材では、あえて『あなたはこの教材を読んでどのような気持ちになりましたか。それはなぜですか』と気持ちを聞いて書かせました。それは当然、大多数の子供が初発の感想で『悲しい』と書くことが予想できたからで、そこから『ではなぜ、悲しいと思ったの?』と問い返すことで、本文の表現を改めて深く読んでいくことにつなげたのです。
そのように、事前に教材研究を行った上で、こちらが明確なねらいをもって、初発の感想を子供たちに聞いていくことが大事だと思います。どの教材でも同様に初発の感想を書かせて、『問い』を立てさせるということになると、どの教材をどんな着目点で読んでもよくなってしまいます。そうではなく、事前に教材研究を行い、その教材に合致する目的に沿って、子供たちが自ら『問い』を立てられるような導入の工夫が必要でしょう」


