【昭和100年記念リレー連載】昭和世代の教師として、20~30代の教師に伝えたいこと ♯7 宇野弘恵 ~出会いを大切にし、日々豊かな感性をもって生きよう

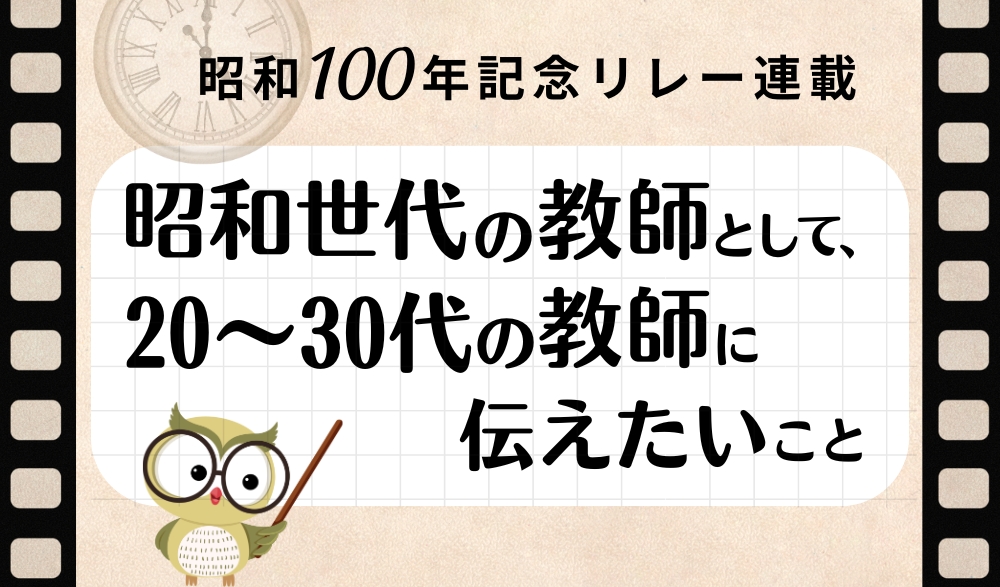
今年は昭和100年。 昭和100年を記念して、今夏、昭和世代の、昭和世代による、令和時代に向けてのセミナーを開催することになりました。開催に先立ち、登壇者たちから現在教職に就く皆さんへのメッセージを綴ったリレー連載をお届けします。 昭和世代の熱い想いをお読みいただければと思います。第7回は北海道旭川市の有名実践者、宇野弘恵先生によるご寄稿です。これまでの教員人生における実感のこもったメッセージです。
執筆/北海道公立小学校 宇野弘恵
編集委員/堀 裕嗣(北海道公立中学校教諭)
目次
1 「先生、このままの授業じゃ、だめよ」
初めて教壇に立った30数年前。私は、5年生の担任になりました。
何をどうすればよいのか全く分からぬまま4月の新学期を迎え、その後は日々の忙しさに忙殺されててんやわんやの毎日。国語、算数、理科、社会、図工、音楽、家庭科、学活、道徳の授業をどうやってつくればよいのだろう(体育は学年の先生がT1で行なってくれていた)と戸惑いつつも、授業づくりに正対できる時間などありません。当時は学校5日制開始前で土曜授業もあり、一週間の仕事が終わればもうぐったりです。おまけに「若い」「バレーボール経験者」というだけでバレーボール少年団担当となり、土曜の午後と日曜の午前は練習、大会があれば土日がまるまる無くなりました。ヘロヘロになりながら月曜に出勤し、なんとか授業をこなすという毎日でした。
それでも私はこの仕事が大好きでした。教師になってよかったと思いました。子どもとの毎日が楽しかったし、子どもたちがかわいくて仕方ありませんでした。子どもたちは、自分たちと年齢が近く「先生然」としていない私を慕ってくれました。休み時間ごとに一緒に遊びましたし、放課後も体育館やグラウンドで遊びました。
この年の家庭訪問でのことです。その日の最後のおうちは、ご両親共に教員のSさんのおうちでした。S家ではお母さまが出迎えてくださいました。お子さんのお話もそこそこに、S先生は、
「先生、このままの授業じゃだめよ。このままの授業じゃ、いつか子どもの心は離れていくわよ。だってね、授業が面白くないの。心が揺り動かされ、どうしてだろうって考えることがないのだもの。これじゃあ、そのうち、みんな勉強が嫌になっちゃう」
とおっしゃったのです。
その時の私の衝撃といったら想像できるでしょうか。自分の授業がこれでいいとは思っていなかったけど、何とかしなくちゃとは思っていたけれど、それでもそんなにダメだとは考えてもいませんでしたから。もう、金槌で頭をがあんと殴られたような感じでした。自分の無能さを恥じ、消え入りたい思いでした。
S先生は、その場で私に国語の教科書を出すように言い、『木登り』という教材を解説してくださいました。どんなふうに読めばよいのか、どんな問いを出せば子どもの思考は揺さぶられるのかを見せてくださったのです。そして、
「国語なら、学校にK先生がいるでしょう。社会ならM先生、算数はN先生。授業を見せてもらうといいわよ。そして、どんなふうに授業をつくったか教えてもらうといいわ。若いうちはいい授業をたくさん見て勉強して。そのうちに自分なりの授業ができるようになるわよ」
とおっしゃいました。
それから、私は、校内の先生方の授業を見せていただくようになりました。特に、K先生の国語の授業に魅了され、子どもたちが夢中になって考えるその授業に憧れました。私もあんな授業がしたいと思い、放課後、教えを請いに教室も尋ねました。私の授業を見ていただき、指導していただいたこともありました。
また、本を読んだり校外の先生の授業を参観に行ったりもしました。2校目へ異動したころには、同年代の同僚が足を運んでいた外のセミナーにも参加するようになりました。自分で満足できる授業はなかなかできませんでしたが、それでも、授業づくりの難しさと愉しさを実感できるようになっていきました。
2 「誰のための指導なんだろうね」
ある年の研究セミナーで、私は自慢の掃除システムについて発表しました。講師には、当時長野県の小学校教諭でいらした平田 治先生がおられました。平田先生は、長く「自問清掃と教師成長」について研究、実践されてきた方です。
私の掃除システムとは、毎日輪番で立つリーダーが全てを指示し、みんなはその指示に従って掃除をするというものです。リーダーは掃除をせず、教壇の上に立って全体を見渡し、滞っている部分に指示を出します。返事は「はい」一択。
「○○さん、机を運んでください」
「はい」
「○○さん、ここを拭いてください」
「はい」
といった具合に、リーダーの指示に従って掃除をします。リーダーは一生懸命考えて指示を出すのだから、理不尽なものではない限り従うのが協力というものです。
全員がリーダーとして指示を出しますから、自分がリーダーでないときに掃除をさぼるわけにはいきません。普段さぼっているのに今日はリーダーだから言うことを聞け! では筋が通りません。ですから、必然的に全員がリーダーの指示に従いまじめに掃除をすることになります。
この掃除システムを使えば、ものすごく早く掃除が終わります。サボったり遊んだりする子はおらず、みんな一生懸命に働きます。低学年でもあっという間に掃除が終わるので、同僚からも随分褒められました。
私は動画を見せながら、効率よく掃除が終えられること、誰もが一生懸命に働くこと、リーダーを経験することで積極性や責任感、リーダー性を培えること、同時にリーダーの大変さを経験することがよりよき協力体制をつくることを嬉々として語りました。その間、平田先生はずっと黙ってお聞きになっていました。そして、発表が終わった後、ぽつりと
「誰のための指導なんだろうね」
とおっしゃいました。この瞬間、私は脳天をかち割られたような衝撃を受けました。誰のための指導かなんて考えたこともなかったからです。そもそも「誰のための指導か?」だなんて、そんなの子どものための指導に決まっている。子どもが責任感とリーダー性を身に付けるためのシステムなのだ。子どものためという以外に、いったい、誰のためだっていうのだろう。そう思いました。
この日から、自分はいったい誰のために指導していたのかということを繰り返し考えるようになりました。この指導は本当に子どものためなのか。子どものためといいながら、実は自分の都合のため、自分の栄誉心を満たすための指導なのではないか。そう考えだすと、これまでの自分の指導はすべて自分のためのものだったのではないかと思えてきました。「勉強しない子に勉強させたい」も「引っ込み思案な子に発言させたい」も、自分の都合のため、自分の指導のおかげという自己満足のため、自分がほめられたいという名誉欲、自己顕示欲のためだったのではないかと。無意識のうちに、独りよがりの善意、正義感、常識、熱意だけで、「~すべき」「~ねば」と指導してきたのではないだろうかと、自分の指導を省みるようになりました。
3 「さびしいって、どういうこと?」
平田先生からは、その後も、教材解釈や合唱指導、自問清掃などを教わってきました。まだ初期のころの研修会で、「おさるがふねをかきました」を題材に教材解釈をしたことがありました。
おさるが ふねを かきました
まど・みちお
ふねでも かいて みましょうと
おさるがふねを かきました
けむりを もこもこ はかそうと
えんとつ いっぽん たてました
なんだか すこし さみしいと
しっぽも いっぽん つけました
ほんとに じょうずに かけたなと
さかだち いっかい やりました
表記は全てひらがな。知らない言葉などありません。小学校1年生の教科書にも載る詩ですから、大人が分からないはずはありません。意味もちゃんと分かります。それなのに平田先生は、「へんだ おかしい」を問います。この詩の変だ、おかしいと思うところはどこかと訊くのです。
「さるがふねを描いて、えんとつ、けむり、しっぽを描き足して、上手に描けて喜んでいるのでしょ?」としか思えなかった私は、どうにか「山にいるだろうさるが、どうして海での乗り物のふねの絵を描いたのだろう」ということをひねり出しました。
平田先生は、ふねにしっぽをつけることの異常性を問いました。ふねにえんとつを描くのは普通の発想。でも、普通はふねにしっぽなどつけない。なぜしっぽをつけるなどとさるは発想したのか、その異常性に気付けなければこの詩を読むことはできないとおっしゃいました。
さて、なぜ、さるはふねにしっぽを描いたのでしょう。詩の前後に目をやると、「なんだか すこし さみしいと」とあります。「さみしいと」の後には「思って」が省略されており、
・なんだか すこし さみしいと 思って しっぽも いっぽん つけました
となるのではないか? そうか。さるはさみしいからしっぽをつけたのだ。しかし、平田先生はさらに、
「さみしい(さびしい)って、どういうこと?」
とおっしゃいます。どういうことと言われたって、さびしいはさびしいでしょ……。それ以上、何があるのでしょう……。
平田先生は、「さびしい」にはいくつかの意味があることを教えてくださいました。
①心の通い合う相手がなく、楽しくない。(友だちがいなくて寂しい)≒ 孤独
②あるべきものが欠けていて満足できない。(お正月に息子が帰省しないのは寂しい)≒ 残念
③金銭的に乏しく不安である。(懐が寂しい)≒ 心細い
④人のいる気配がなく静けさに包まれている。(子どもが帰った後の公園は寂しい)⇔ にぎやか
⑤華やかさや活気がない。(おかずが少なくて食卓が寂しい)≒ 物足りない
この場合の「さみしい」は、どれなのでしょう。どの意味として捉えると詩を読むことができるのでしょう。
「仲間がいなくて寂しい」と捉えれば、ひとりぼっちで寂しかったから、異質の存在であるふねにしっぽをつけて仲間に仕立てたと読むことができます。姿かたちは違っても仲間であると見れば寂しくないと思って満足したという解釈が成り立ちます。
「残念」と捉えれば、ふねにしっぽがついていなくてかわいそう、自分と同じしっぽをつけてあげようと考えたと読めそうです。船に自分と同じしっぽを描くことで、ふねを完全なものとし、欠けた部分に自分の存在を重ねているという解釈が成り立ちそうです。
「物足りない」としたならば、しっぽをつけてにぎやかになって満足したと読めるでしょう。自分と異質なものに自分の要素を付け加えることで満足を得ると解釈できるでしょうか。
「自分で書いたり話したりするときには自然と使い分けているのに、読むときには安直に理解した気になってしまうもの」と平田先生はおっしゃいます。普段は「さびしい」を場面に応じて使い分けているはずなのに、いざ読むとなれば妥当な意味を考えずに分かってしまう。詩は、私たち凡人には気付けない稀有なことを天才たちがことばで表したもの。選び抜かれたひとつひとつのことばの真意を読むことができれば、そこに隠された天才たちの世界に触れることができる。たった一つの語の見方で親和的だった文章が新奇的になるのです。何と奥深くおもしろい世界なのだと思いました。
また、平田先生は、絶対に「答え」をおっしゃいません。解釈は常に進化するもので、今日の読みが絶対ではないと考えていらっしゃるからだと思います。ましてや、「これが答えか」と満足してしまったら、そこで思考停止になってしまいます。「ああ、もう読み切った」と思っても、またあるとき新しい解釈に辿り着く。答えは誰かが授けてくれるものではなく、自分で探し出すもの。それが「学ぶ」ということであり、学びの愉しみでもあります。
平田先生と学びの時間を共にするようになって、子どもたちに学ぶことの愉しさを実感させられるような授業がしたいと強く思うようになりました。
4 出会うべき時に必要な人に出会う
私は時々考えます。もし、保護者であるS先生に出会っていなかったら。もし、平田 治先生に出会っていなかったら、と。
もし、S先生に出会っていなければ、授業づくりの難しさや楽しさを知らずにいたかもしれません。授業づくりは難しいだけで大変だと、マイナスイメージだけで今日まで来たかもしれません。あるいは、なあなあの授業で自省できないままでいたかもしれません。
また、校内の先生たちから教わるという経験もなかったでしょう。校内に素晴らしい先生がたくさんいることにも気づけなかったでしょう。身近なところに素晴らしい授業実践をされている先生はたくさんいます。著名な先生から学ぶことも益がありますが、同じ学校で実践を積んでいる先生から教わることはたくさんあります。名の知れた先生ブランドだけを正解とせず、色々な先生の実践から学べる心で在ることが大切だと思います。
もしかするとS先生のことを「保護者の立場で担任教師に説教するなんて」と眉を顰める方もいらっしゃるかもしれませんが、私は、S先生にとても感謝しています。あのとき苦言を呈していただけて本当によかった、有難かったと心の底から思っています。他者から学ぶこと、自分から学びに行くこと、そして、子どもの心を揺さぶる授業づくりに憧れを抱かせてくださったのはS先生です。何より、S先生が私の心に撒いてくださった種があったから平田先生に出会えたのですから。
きっと、みなさんの近くにも、S先生のような教師観を大転換してくださる方がいらっしゃるはずです。まずは、校内の先生方の授業をたくさん見せてもらってはいかがでしょうか。そして、余力があれば、学校の外の色々な先生の授業を見せていただいてはどうでしょうか。
もし、平田先生に出会っていなければ、私はずっと自分のために指導をする教師でいたかもしれません。中身を考えず、外側だけを整えることに躍起になる教師でいたかもしれません。
また、教材を深く解釈することも知らずにいたと思います。教材を解釈することは、単に「どうやったら教材を読むことができるか」という技術だけを指しているのではありません。教材解釈をすることを通して、ものの見方や感じ方、考え方を学んでいるのです。いえ、教材解釈だけではありません。合唱指導や自問清掃も同じです。誰も気づかぬ小さなことに気がつけるか、その小さなことに心を動かせるか、意味を見いだせるかという根本は同じです。
これは、日々の学校教育にも通ずることです。何かを見て、聞いて、触れて、人に出会って――そのたびに心を動かせるような感性を育てる土台を、私たちは日々の教育活動の中でつくっているのではないでしょうか。
目を肥やすためには知識が必要です。だから、学校では勉強するのです。数々の教育活動も、人と触れ合い心のひだを増やすために在るのです。一つの教材を通して感性を磨く、一つの事例を通して感性を育てる。感性が磨かれれば見えることが増え分かることも広く深くなる。そうした喜びこそが学ぶ愉しさであることを、平田先生は教えてくださいました。
人は、必要な時に必要な人に出会うものです。未来あるみなさんは、これからたくさんの人に出会うことでしょう。その中にきっと、この人から学びたいと思う人がいるはずです。それは教師に限りません。保護者や異業種の方、友人、そして子どもであってもよいのです。考え方に共鳴する、その人の感性に強く惹かれる――そんな人との出会いがきっとあるでしょう。そうした誰かの考え方や感性に触れることで、人としても教師としても、私たちは成長し続けられることができるのだと思います。
教師は、子どもの人生のほんのひととき関わる人に過ぎません。けれども、もし、教師自身が日々豊かな感性をもって生きようとしているならば――その姿が、いつか子どもの中で「何かの種」となるかもしれません。
<引用、参考文献>
「おさるがふねをかきました」まど・みちお
『追求の授業に生きる』宮坂義彦著 平田 治編/解説 一莖書房 2022年
『基礎日本語辞典』(12版) 森田良行 角川学芸出版 1989年
『ベネッセ表現読解国語辞典 特装版』 沖森卓也 中村幸弘 ベネッセコーポレーション 2003年
『教職の愉しみ方 授業の愉しみ方』堀裕嗣・宇野弘恵著 明治図書出版 2023年

<今回の執筆者のプロフィール>
うの・ひろえ。北海道公立小学校教諭。民間教育研修などに参加、登壇し、今日的課題や教員人生を豊かにすることを学んでいる。著書に『あと30分早く帰れる!子育て教師の超効率仕事術』(学陽書房)、『スペシャリスト直伝!小学校高学年担任の指導の極意』『伝え方で180度変わる!未来志向の「ことばがけ」』『生き方を考える!心に響く道徳授業』(以上、明治図書出版)など多数。

