コロナ後の課題と取組とは?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #25

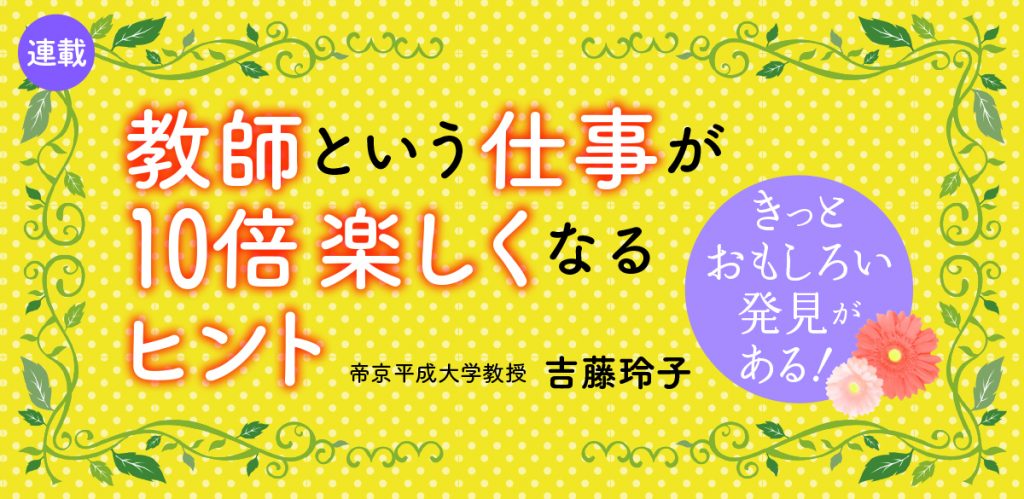
「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」の24回目のテーマは、「コロナ後の課題と取組とは?」です。まだ完全には終わったとは言えないかもしれませんが、新型コロナウィルス感染症が世界中に猛威を振るった数年間があり、学校教育に大きな影響を与えました。今回は、そのことを振り返りながら、学校生活が変わった点、残された課題などについてお話しします。
目次
学校の日常生活が変化
2020年3月、突然全国の公立小学校が休校になりました。感染症の拡大を防ぐために仕方のないことは言え、今まで準備していた謝恩会はどうなるのか、卒業式をどうしようとか、授業はどうしたらよいのかなど、各校に激震が走りました。学校では子供が密を避け学年別に登校し、家庭学習のプリントを渡され、家庭での待機を余儀なくされました。そして、この問題を受け、学校に行かなくても学習ができるように一気にICT端末の普及が進み、子供には1人1台のICT端末が配付され、オンラインでの家庭学習が普及しました。
子供たちは、今では当たり前のようにランドセルの中に家で充電したICT端末を入れて登校してきています。社会科の研究授業などを見に行くと、ICT端末を活用していない授業に出合うほうが難しくなりました。急速にICT端末の活用が進み、ノート替わりにICT端末を使うようになりました。記録に残せるノートと並行して活用している場合もあります。いずれにせよ、毎日の学習の中で子供が常にICT端末を使うようになりました。
コロナ禍が収まっても昨年はインフルエンザが猛威を振るっていました。学校へ行かなくてもオンラインで学校と家をつなぎ、授業をすることも当たり前になりました。教師同士の研究会議も遠隔地の場合、オンライン参加と併用で行われるようになりました。この急速なICT端末の活用が何よりも学校現場での大きな変化でしょう。
また、コロナ禍で移動教室の様子も変わりました。宿泊数を減らしたり、大規模な学校は2回に分けて移動教室に行ったりするなど、常に消毒と適度な空間が保てる工夫を学校外でも行いました。移動教室先の場所が変更になった自治体もあります。行程も余裕をもって組むようになりました。だいぶいろいろなことがもとに戻ってきましたが、遠足や宿泊行事についてはまだ完全に復活していないところもあります。
かつては保護者が校庭の周りに密集していた運動会の形式や音楽会などの形式も変わりました。学年で入れ替えを行い、保護者の密集を避ける工夫がされるようになりました。運動会も種目の検討が行われ、プログラムが精選されて、最近では、昼食前に終わる学校も多くなりました。かつての校庭で各々の家庭がレジャーシートを敷いてお弁当を食べるような光景はあまり見られなくなりました。

残された課題
ICT端末の課題
ICT端末の支給が始まってそろそろ今年はレンタルした機種が入れ替わる時期になる頃です。精密機器は使えば故障が多くなります。本来であれば毎日家に持って帰って充電して、緊急の学級閉鎖などにも備え、すぐにオンライン授業に取り組めるようにすべきでしょうが、子供や家庭の実態として難しいところもあります。
私の知っているいくつかの学校では、自宅へ持ち帰るとインターネットなどの使用についての歯止めが利かないことや機械が破損しやすいことなどから学校の教室で充電しているところもあります。充電したICT端末を子供が学校へ持ってくるのを忘れたら、授業で活用することができません。先生や学校はその地域の子供の実態に合わせて工夫して管理しています。故障して修理に出してもすぐに直してもらえなければ、授業に支障が出ます。予備の機械がある自治体は少ないようです。しかもこのICT端末は子供が卒業したときに返却しなくてはいけないので、そこに子供が作成したデータがある場合は、教師の側できちんと集約し保管しなくては、記録に残りません。機械は普及したものの、その管理についてはまだまだ課題があります。子供の家庭の事情を考えれば購入という形は難しいのでレンタル形式は続くでしょう。
ICT端末を持ち歩きやすいように、ランドセルを従来の重いものから軽いビニール素材のリュック型に替えた学校もあります。ICT端末を使うことのメリットは大きいので、どのようにデメリットを減らしていったらよいかということについてこれからも検討が必要でしょう。今、皆さんが現場で直面しているこのような課題は、多くの先生方が感じていることです。あきらめないでよい対応の道を模索してください。
管理面の他、ICT端末のもう1つの大きな課題は自治体によって使用している機種やソフトが違うということです。1つの企業に偏らないようにしようという考えからなのでしょうか。しかし先生たちは、異動したら、自治体によってはまた1から機種の取扱いやソフトの活用を勉強し直さなくてはいけません。パソコンが得意な先生はよいでしょうが、一般の先生にとっては時間も必要で厳しいものがあります。日頃からパソコンの操作に慣れておくことが大切です。
紙ベースの教科書と電子教科書
教科書が電子教科書になると、令和2年より以前の改訂でも言われていました。しかし、紙ベースでの教科書づくりはなくなりません。社会科の電子教科書は動画もあり、調べ学習をする際の活用にも適していると思います。しかし、多くの学校で国語、算数、外国語活動の電子教科書が普及していますが、教科書が完全に電子版に代わるまでにはまだ長い道のりがあると思われます。同時に紙ベースの教科書や教材のよさも見直されているのではないでしょうか。何よりも記録に残せること、ページの見直しがしやすいこと、電子教科書に書き込むより、鉛筆を使って紙に書くほうが書き込みやすいこと、資料の掲示やワークシートへの書き込みなど、紙ベースのよさは見直されています。私も長年、教科書の編集に関わっていますが、次の改訂でも紙ベースの教科書はなくならないでしょう。

