学級会の話合いが活性化する座席の工夫【自治的な活動を促す 学級経営の極意Ⅱ⑧】


子供たちが自治的な活動を行えるようにするためには、教師はどのような指導をしていけばよいのでしょうか。学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に特別活動の本流を踏まえて、学級活動の基礎基本を解説します。第8回は、学級会の座席の配置について解説します。
執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者
城西国際大学兼任講師
日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章
学級活動(1)学級会の話合いの座席配置は、いわゆる「コの字隊形」で行うことが多く見られます。この座席配置は、子供たちが互いの表情を見合いながら話し合うことができることから効果的な場の設定と言えます。講義形式で全員が前面を向いて話し合うと、前の席の子供は後ろで挙手する友達の様子が分からない上に、表情を見ながら話を聞くことが難しいというデメリットがあります。そこで、コの字の隊形での話合いの実践にあたって、3つのキーワード「コの字隊形の意図」「計画委員の配置場所」「コの字隊形の活用法」でチェックしてみましょう。
目次
CHECK① コの字隊形の意図
講義形式での話合いは、全員が黒板を見ながら集中して話し合いやすいというメリットがあります。しかし、聞く側が発表者の表情を見にくいというデメリットがあることに留意する必要があります。学級会での話合いは、互いのよさを生かし合い、相手の考えを尊重しながら合意形成を目指すものです。ゆえに、発言者の表情を見ながら話し合うように場の工夫をしましょう。
相手の思いや願いを確認しながら合意形成を目指します
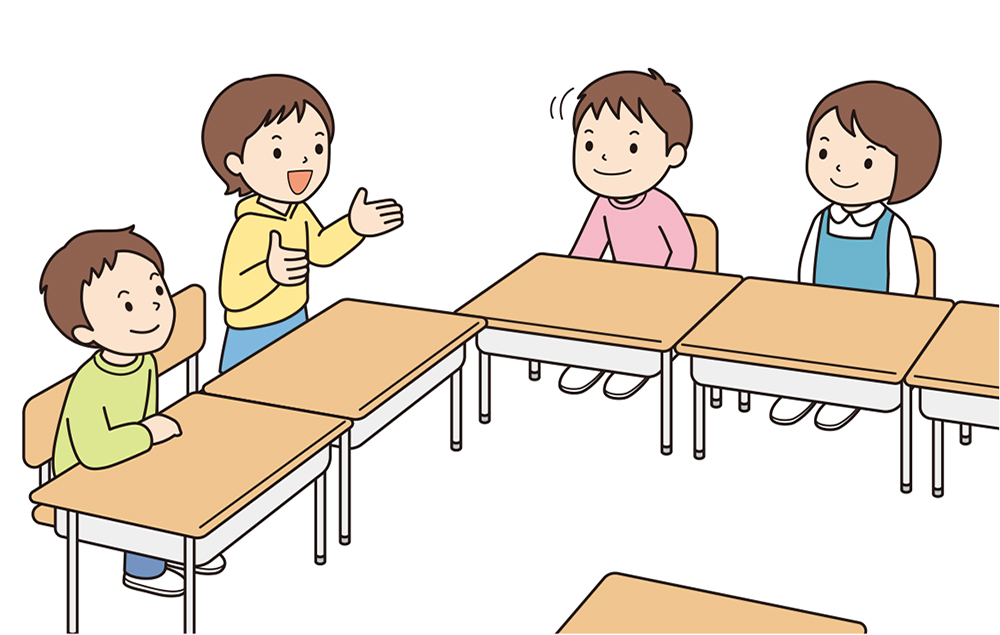
学級会での話合いは、ディベートとは異なります。相手の思いや願いをくみ取りながら「自分もよく、みんなもよい」という合意形成を目指すものです。そのためには、発表者の音声だけではなく、表情や表現方法などを見ながら話し合うことが求められます。「関連発言」による話合いも、コの字の隊形で行うことで効果的に進めることが可能となります。まずは、互いの表情を確認できるコの字隊形での学級会ができるように配慮していきましょう。
CHECK② 計画委員会の配置場所
学級会の話合いで、司会等の「計画委員」が果たす役割は重要です。一般的には、司会者や記録者が黒板に平行した座席配置で話合いを進行する授業が多いように思います。しかし、学級会の研究を推進している学校の中には、黒板の前を空けるように、計画委員が黒板に対して斜めの位置に座席を配置するケースがあります。この場合のメリットについて考えてみましょう。
計画委員も黒板を見ながら話合いをします
計画委員が、黒板の前を空けて斜めの位置に座席を配置している学校があります。この配置にしている学校では、司会者が挙手等の合図を示す参加者の様子を把握しつつ、黒板を見ながら進行できるようにするという視点をもって実践しています。計画委員として、どのような座席配置が進行しやすいのかを子供たちと相談しながら、よりよい話合いになるようにしていきましょう。
CHECK③ コの字隊形の活用法
学級会での「コの字隊形」は、互いの表情を見合いながら、話合いができるというメリットがあります。その他のメリットとして、中央部分が空いていることが挙げられます。その空間を活用して効果的な話合いになるように工夫していきましょう。
中央部分の空間を効果的に活用します
例えば、コの字の隊形の中央部分を活用する方法の1つとして、提案理由を説明する際に、ロールプレイングを活用するという方法をとる実践があります。また、話合いでの意見のイメージを共有しにくい場合には、中央部分を活用して実際にその意見の内容を演じてみるという実践も行われています。この空間は、イメージの共有化等、様々な動きを行う場合に活用できるので、効果的に取り入れて充実した話合いになるようにしていきましょう。
イラスト/池和子(イラストメーカーズ)

