次の学習指導要領は、コンセプトについては現行と大きくは変わらない 【中教審レポートと関係者インタビューで綴る 次期学習指導要領「改訂への道」#11】

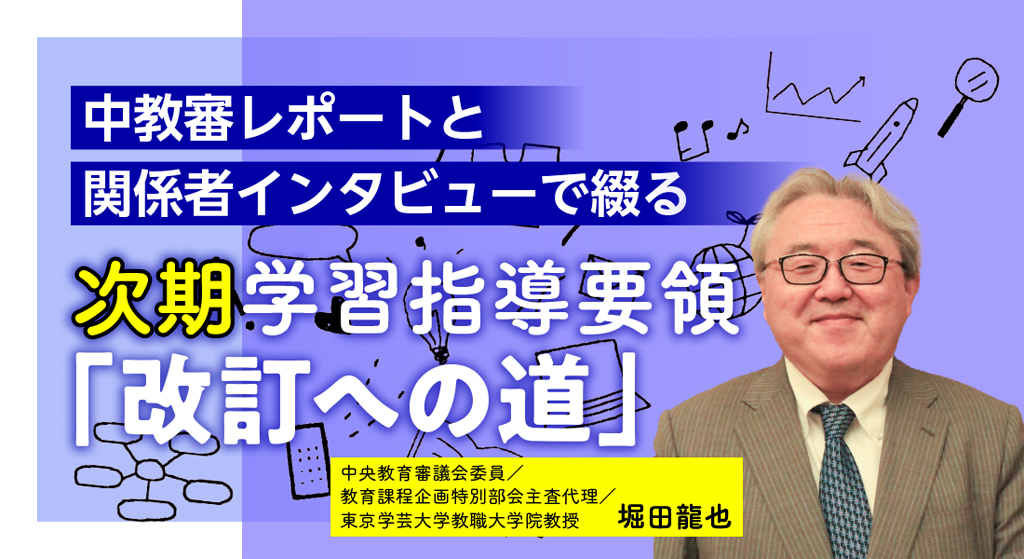
教育課程企画特別部会の主査代理として学習指導要領の方向性に関する審議に携わる、堀田龍也教授(東京学芸大学大学院)に、次の学習指導要領とデジタルの関係を中心にお話を伺ってきたこの企画。最終回となる今回は、諮問文にも示されている「デジタル人材育成」と、それに携わることになる先生の役割や、次の学習指導要領も視野に入れた上で、今から先生方が準備できることなどについて伺っていきます。
なお、学校教育とデジタルの活用を考えていく上で、非常に大きな示唆を与えてくれる、堀田龍也教授と田村学主任視学官(文部科学省)による、「リーディングDXスクール」特別講座、「これからのGIGA!!!教科の学びをどう深める!?」も、ぜひ下記URLよりご参照ください。
https://www.youtube.com/watch?v=IbvS65qEMo4&t=2048s
目次
「先生よりも子供たちのほうが端末を上手に使える」ということは当然
諮問文の中に、多様な課題として「デジタル人材育成」が示されていますが、「デジタル人材育成」とは、意外に漠然とした言葉でしょう。それを解釈してみると、私は大きく2種類あるのではないかと思っています。
一つは、デジタルでビジネスをやっていくくらいの専門的な知識・技能をもっている人材を育成するということ。もう一つは、国民のデジタルリテラシーがこぞって底上げされるというようなことです。当然、こぞって底上げされるためには、少なくとも義務教育段階でしっかりと教えられ、高校教育でも教えられているように、情報活用能力育成の体系化や、それを実施するための態勢がきちんとできていることが大事です。
専門的な知識・技能をもってデジタルでビジネスをやれる人材の育成というのは、専門高校や大学、企業が取り組むべきことで、主として高等教育以降の話です。初等中等教育の義務教育段階で取り組むべきことは、底上げのところであり、前回お話をしたように、小学校ではしっかりと端末を活用して学び、加えて中学校では少し専門的なことも学び始め、高等学校では必履修になっている教科「情報」を体系的に学び、大学入試を受ける人はしっかり習得していくことになります。
こうした人材育成過程の後半はできているわけですが、前半はまだ弱いところがあるでしょう。しかし、小学校段階でデジタル端末を持って、ネットにもアクセスしているわけですから、早期に教えておいたほうがよいことがあるだろうと思います。それは、「デジタル人材育成」の喫緊の課題の一つではないでしょうか。
学校の先生が、そのようなデジタルリテラシー向上の一端を担っていくために行うべきことは2つあると思います。まず一つは、先生方自身が日常からデジタルを使って仕事をすることです。日頃からクラウドで多様な仕事をすることになっている地域の先生は、かなりデジタルリテラシーが高く、そういう人たちは「何でこんな便利なものを授業で使わないのだろう」ということになるし、授業で子供たちとどんどん活用しています。
しかし残念ながら、相変わらず学校の業務は紙ベースで行われていることが多いようです。教育委員会が固くて、先生方の仕事の仕方をデジタルに切り替えていないところもあったり、場合によっては教員用端末にワイヤーを付けて持ち歩けないようにしているところもあったりします。それでは先生のデジタルリテラシーも向上しません。ですから、まず先生が日常の仕事で活用する、教育委員会が先生方の仕事で端末を活用しやすくすることが大事だということです。
もう一つ意識していただきたいことは、「先生よりも子供たちのほうが上手に使える」ということは、ジェネレーションの関係からすれば当然、ということです。実際に個々のデジタル技術に関しては、私自身、私の子供から「お父さん、本当に情報活用能力あるの」と冗談を言われることもありますが、彼らのほうがデジタルに親和性の高いジェネレーションなのです。もちろん、世の中全体を見て、デジタル技術のもつ意味や役割を考える力は、私のほうが確かだと思っていますが、個別の技術について若い世代のほうが詳しいのはごく当たり前のことです。ですから、何でも先生のほうが知っていなければならない、できなければならないという考え方は、少なくともこの分野には合わないと思います。
先生は、よほど情報モラルに抵触することを除けば、子供たちがやることを見て、「なるほど、そんな技術があって、そんなことができるんだね」と言ったり、「それは何のためになるの?」「それは誰の役に立つの?」「あなたはそれでいいの?」と投げかけたりしてあげればよいのです。そう思えるかどうかが大事です。
私自身も小学校の教員だったのですが、担任している学級には、私よりも習字が上手な子や、水泳が上手な子は何人もいましたし、そういう子を認めて、他の子の見本になってもらうことはごく当たり前に行っていました。それは見本になった子の自己有用感も高めるし、他の子にとっても分かりやすい見本になるわけです。そのような柔軟なマインドを教師がもてるかどうかが、重要なポイントです。
これまでは学校が頼られすぎてきて、先生自身もすべて自分でできなければならないと抱え込みすぎてきたところがあるように思います。そこを割り切って発想を変えると、先生はもっと楽になるし、本当に力を入れるべきことに時間を割けるようになるのではないでしょうか。

デジタル端末を使うことを前提に、次の学習指導要領が組まれる
最後になりますが、次の学習指導要領は、コンセプトについては現行と大きくは変わらないと思います。それは、現行学習指導要領がすでにコンピテンシーベースになっており、個別の知識よりもむしろ学び方などが重視されているからです。それは、ネットやデジタル技術が日常にあり、個別の知識について容易に学び直せるような時代にも合致しています。しかし、すでに個別の知識よりも学び方などのほうが重要だとなっているのに、現場の授業はそのように力点を変え切れていないし、保護者の考え方もそのように変わっていないという課題があると思います。
しかし、次期学習指導要領が小学校で実施になる5年後は、もう少し柔軟になっているのではないでしょうか。次の学習指導要領は現行とコンセプトは変わらないにしても、見え方は変わるでしょう。しかも、デジタル端末を使うことが当たり前になっているし、それを前提に学習指導要領が組まれているという状況でしょう。
さらに、学校はより柔軟に多様性を包摂する方向に動くはずですから、「学校って、いろんな人がいて、いろんなことをやって、いろんなことが起こるからいいよね」というようになっていくでしょう。旧来型の「これができないとダメ」「あれもできないとダメ」というようなチェックリスト型ではなく、「あれもあるし、これもあるし、それもある」「そういう見方をしてみると、そっちもいいよね」というふうに、多様なものを受け入れていく形になるのではないかと思います。
ですからあと5年の間に、「先生は自分の既存のやり方、教え方だけではなく、いろんな人のやり方、軽重の置き所を変えたやり方を試してみておいてはどうでしょうか」と提案したいと思います。そのほうが、余裕をもって新しい学習指導要領を迎えられるのではないでしょうか。
執筆/教育ジャーナリスト・矢ノ浦勝之
【中教審レポートと関係者インタビューで綴る 次期学習指導要領「改訂への道」】
次回は4月17日公開予定です。

