【シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯5 教職員、保護者、外部機関との連携をどうするか?
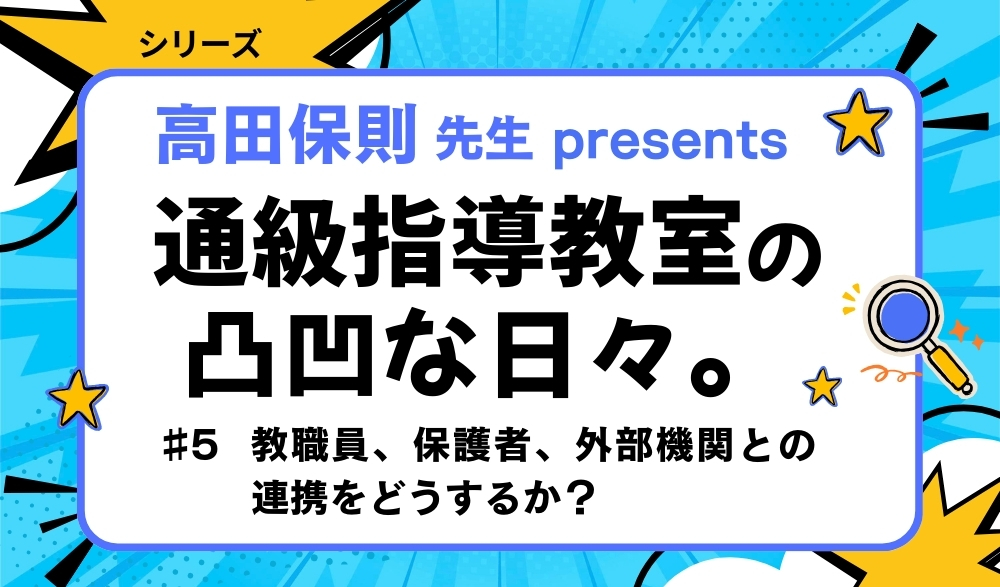
通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性をもつ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポート。アイデアあふれる実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。今回のテーマは「教職員、保護者、外部機関との連携」です。
執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則
目次
はじめに
北海道のオホーツク地方の小学校で、通級指導教室の担当をしている高田保則(たかだやすのり)です。日々、子どもたちと向き合ってきた中で、感じた事や考えた事を記していきたいと思います。
なお、通級指導教室で出会った子どもたちの事例は、過去の事例を組み合わせた架空のものであることをご承知おきください。
今回は、『連携について』というテーマで記してみました。通級指導は単体では機能しません。学級担任や保護者と情報共有をして、その子の理解を更新していく営みを続けることが不可欠です。
また、ケースによっては、外部機関の関係者との情報共有が必要になる場合もあります。エピソードを通して、連携についての思いを綴ってみました。ご感想をお寄せいただけますと、嬉しいです。
1.指導記録を記す
通級指導教室を利用する子どもたちは、ほとんどの時間を通常学級で過ごしています。通級指導の個別指導で垣間見えるその子の学び方の特徴を、保護者や学級担任を始めとした関係職員と情報共有する営みは、とても大切になります。私は、通級指導で知り得た情報を指導記録にまとめて、お伝えしています。
特別支援教育が始まった当初、医療や福祉や療育の関係者との多職種連携が必要だと強調された時期がありました。今まで学校の中しか知らなかった教員にとって他の職種の方との連携は、刺激的で示唆に富む情報が数多く得られる場でした。一方、外部の専門家と日常的に情報共有を続けるケースは稀です。お互い忙しくて、連携に多くの時間を割けないのです。
機能する連携は、毎日顔を合わせる職員の間で行われる営みだと思います。病院なら、ドクターと看護師と検査やリハビリの担当職員。介護施設なら、ケアマネジャーとヘルパーと栄養士と調理員。学校ならば、学級担任と学習支援員と養護教諭などの教職員になります。
一方、共有される情報は、常に更新していかなければなりません。落ち着きがなくて、授業に乗れないAさんがいました。当初は、Aさんが生まれながらに持っている集中や注意の弱さが、授業の参加を難しくしている要因と見立てられていました。ある日、Aさんは、朝ご飯を食べていないことが明らかになりました。すると、Aさんの見立ては、全く違うモノに変わります。Aさんの家庭環境に注目が向くようになるのです。
だから通級指導の記録は、毎回記して、その子の情報を更新する必要があるのです。

