【連載】坂内智之先生の 愛着に課題を抱えた子が伸びるアプローチ~学級担任にできること~♯4 学校が愛着障害を悪化させている!
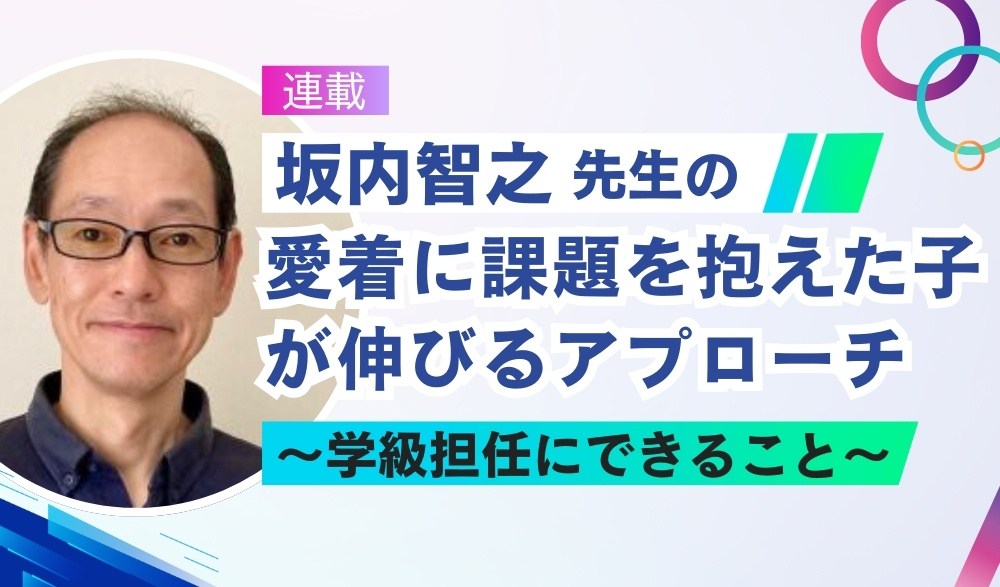
近年、教員たちが対応に苦慮し、学校現場を根底から揺るがしている「愛着障害に苦しむ子どもたち」。そうした子どもたちによって荒れた学級を何度も立て直してきた坂内先生が、今、学級担任に何ができるのかを提案し、これからの学級のあり方について考えていく連載第4回。今回は、子どもたちの愛着の課題を増幅させてしまう学校側の要因について考えていきます。
執筆/福島県公立小学校教諭・坂内智之
目次
はじめに
愛着障害は、子どもや家庭だけが原因で起きるのか。私はそう考えてはいません。
今の学校には、子どもの愛着障害を悪化させるような要因がたくさんあります。学校に悪化させるような要因がなければ、子どもは学校で不適切な行動をとったり、学校を休んだりはしません。学校にも原因があるからこそ、学校内で子どもたちの状態は悪くなるのです。
しかし、残念ながら私たち教師の多くは、そうした学校側の原因に気づいていません。そのため、子どもや親だけにその原因を求めてしまったり、解決方法が見えず途方にくれたりしてしまいます。
今回は、子どもの愛着の課題を増幅させてしまう学校内部の原因について解説していきます。
1. 「不安」を動力源としている学校
小学校入学直前の幼稚園や保育所で、子どもたちにはどんな語りかけがなされているでしょうか。明るく希望に満ちた素敵な言葉をかけられる子どもがいる一方で、「小学校はとても大変だよ」「もっとしっかりしなければ」「1日中ちゃんと席に着いていなければいけないよ」、そんな言葉を受けてきた子も多いのではないでしょうか。
その言葉通り、子どもたちは学校に入学すると行儀良く席に着き、背筋を伸ばし、腕はピンと真上にあげることを指導されます。こうして子どもたちは入学した途端、集団で揃えることや、数多くのルールを守ることに徹しなければならなくなります。この流れは学年が上がってもさらに続き、「そんなんじゃ2年生になれないよ!」「もっと勉強をしっかりやらないと5年生になれないよ!」など、常に「今のままではいけない」という不安を煽る言葉が繰り返されます。
そして6年生ともなると、今度は「中学校では」と指導されます。中学校では「いつまでも小学生気分ではいけない」「これまでとは違う」「受験に向け、このままではいけない」と続いて聞きます。こうして子どもたちは、義務教育の期間中「不安」を基盤とした学校生活を送ることになります。
その中に、幼いころから愛着形成に課題のある子どもが入ってきたら、どうなるか、この連載をここまで読まれてきたみなさんには、はっきりと想像できると思います。
ではなぜ学校は、私たち教師は、こうした「不安」を投げかけてしまうのでしょう。
それは、子どもの行動をコントロールしたいという欲求に理由があります。学級という集団を束ねている教師は、「子どもが自分の指示を聞いてくれないかもしれない」「勝手なことをされるかもしれない」というような不安を常に抱えているのです。ですから、子どもたちを揃えること、そしてそうできないことへの不安を投げかけ、勝手な振る舞いを防ごうとします。子どもたちに「もっとしっかりとしなければ」「今の自分ではだめだ」と感じさせておいたほうが、指導する側にとっては都合がよいのです。
こうした言葉が全ていけないとは思いませんが、学校内、学級内の子どもの問題行動が悪化すればするほど、こうした言葉は増え、口調もより強くなります。こうして教室は不安の悪循環に陥ってしまいます。
また、学校は競争が大好きです。競争することは子どもにとっても、とても魅力的なものです。その最大のイベントは運動会でしょう。紅白に分かれて大声で声援し、競技で大盛り上がりを見せる姿はとても微笑ましいものです。一方で、こうした競争は学校のあらゆるところに存在します。特に体育の授業では、縄跳びや持久走、水泳なども順位やタイムなど、昨年と比べ、どれだけ向上し、速くなったかを比べるイベントが多くあります。
また、学習(宿題)の到達度をシールにし、教室に貼って可視化したり、生活の動作(準備や並ぶのが速いなど)を競ったりすることも日常的です。こうした見えにくい競争も学校生活の中に多くあります。
こうした競争は、子どもの行動を素早く的確にコントロールするのにとても効果的です。しかし、そうした働きかけの中に「不安を煽る要素」も内在していることを知らなければいけません。「もっとやらなくちゃ」「負けてしまう」「みんなより自分はできていない」というように、子どもの不安を高めてしまう反作用もあるのです。心の基盤がしっかりとした子どもなら、競争を楽しみ、自己成長につなげ、自分を高めていくことができます。しかし、幼いころから安心や安全が確保されていない子どもにとって、競争することはマイナスに作用するのです。
実際に現場で、こうした競争から「あきらめる」「投げ出す」「逃げ出す」子どもが増えてきていることを実感している方も多いと思います。愛着の形成がしっかりとしていない子どもは、競争し、みんなの前で負けてしまうことをとても恐れます。競争で負けることは自分の価値(有能感)が大きく下がってしまうことになるからです。
子どもたちはこうした不安でいっぱいの学校の中で過ごすことで、愛着の課題をより強化してしまうことになります。こうした学校側の働きかけが、不適切な行動や登校しぶりや不登校が増大していく一つの原因となっているのです。
2. 大きく偏った学力観

坂内智之プロフィール
ばんない・ともゆき。1968年福島県生まれ。 東京学芸大学教育学部卒業。福島県公立小学校教諭。協働学習の授業実践家で「学びの共同体」から『学び合い』の授業を経て、20年以上にわたり、協働学習の授業実践を続ける。近年では「てつがく」を取り入れた授業実践を行う。 共著に『子どもの書く力が飛躍的に伸びる!学びのカリキュラム・マネジメント』(学事出版)、『放射線になんか、まけないぞ!』(太郞次郎社エディタス)がある。

