「読書推せん文コンクール」選考で重視されるポイントとは【PR】
小中学生が参加できる”お気に入りの一冊をあなたに”「読書推せん文コンクール」をご存じですか? 今年で5回目になる取り組みで、全国の小学校でも参加校が毎年増えています。夏休みの課題としての参加も可能で、参加しやすいと学校からの評判も上々です。前回に続き、このコンクールでの選考ポイントや過去の入賞作品について、主催団体・博報堂教育財団の常務理事にお話を伺いました。
前回記事:子どもが“お気に入りの一冊”を薦める「読書推せん文コンクール」の魅力とは
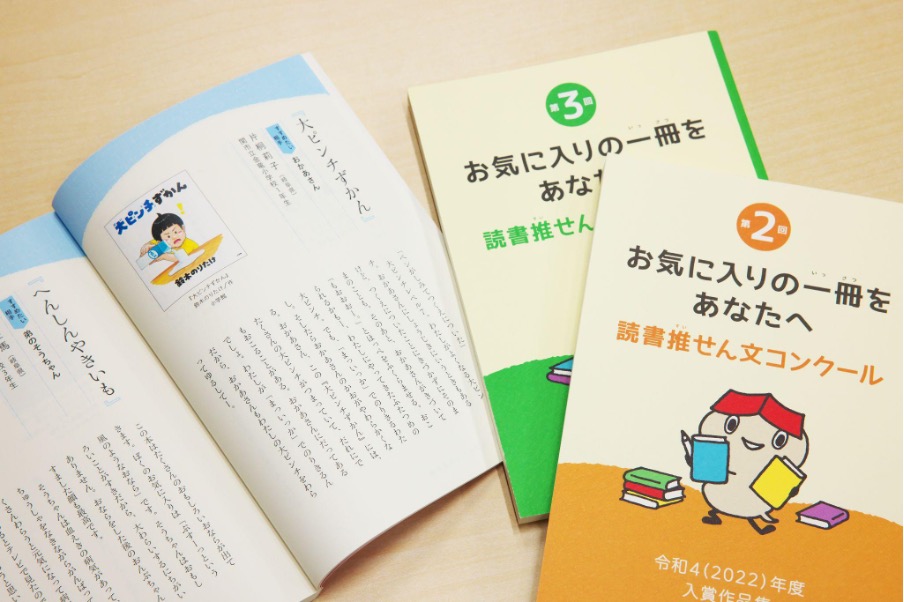
提供/博報堂教育財団

お話を伺った人:公益財団法人 博報堂教育財団
常務理事 中馬淳さん
1985年博報堂入社。PR局、研究開発局、経営企画局、人材開発戦略局長を経て、2021年より現職。博報堂では企業内大学である「博報堂大学」の運営など、人材開発を牽引してきた。「読書推せん文コンクール」では選考委員も務める。
目次
コンクールの選考基準は文章スキルよりも”伝えたい”熱い気持ち

――”お気に入りの一冊をあなたに”「読書推せん文コンクール」では、毎年100作品前後と、大変たくさんの入賞作品が選ばれるそうですね。選考基準や選考委員について教えてください。
選考基準は、厳密には設けていません。「自分の思いを相手に伝えること」を大事にしたいからです。ただ、この本を、誰に、どういう気持ちで伝えるか?というロジックについては、きちんと成立していることを求めています。
国語能力の評価だけではないので、文章スキルや、誤字脱字よりも、自分の素直な思いが前面に出ている作品を積極的に評価しよう、ということにしています。
選考委員は現在7名ですけれども、文部科学省の視学官でいらっしゃった方や、児童文学作家さん、書店で働いていらっしゃった方など、様々な背景を持つ多ジャンルの方々にお願いしております。それも全員合議で決めるのではなくて、選考委員それぞれの視点で評価いただくスタイルです。結構みなさんの意見が違っていて、評価がばらけるのが面白いですよ。いろんな価値観で選出されることが、多様性の担保となり、とてもいいことだと思っています。
「読書推せん文コンクール」選考委員のご紹介
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/okiniiri/#person_wrap
入賞作品も、今回(第4回)で言うと120作品ほど選びましたが、 順位はつけていません。全員入賞です。 毎年、だいたい100名ぐらい選出しているのですが、人数も厳密には決めていません。小学1年から中学3年まで合わせて100名前後です。
個人賞と団体賞があり、それぞれに表彰状と図書カードをお渡ししています。団体賞は10万円分の図書カードです。受賞された団体さんの方に伺うと、図書館の書籍購入などに使われているようです。参加団体は、公立や私立の小・中学校のほか、学童、読書サークル、海外の日本人学校などがあります。
「読書推せん文コンクール」入賞団体の声
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/okiniiri/voice/
素直な自己開示と思いにあふれた作品を待っています!

――中馬さんが個人的に印象に残っている作品はありますか?
個人的には結構、自分をさらけ出している作品が好きなんです。なかなか人前で言えないようなこと。例えば以前、「学校のトイレで、う○こ」をみんな我慢しているけれど、我慢するのをやめよう、みたいな作品がありましたが(笑)、そういうことを正々堂々とみんなに伝える勇気みたいなものが、私はすごく好きだったりします。自分の正直な考えをさらけ出す勇気にあふれた作品って、素敵ですよね。
でも、先ほども申し上げましたように、選考委員によって好みがあって、選ばれる作品も多様です。そして、それが大変面白いところです。
――推薦文を書くにあたってのアドバイスはありますか?
注意点としては、どうしても読書感想文や、純粋な本の推薦文に慣れている子どもが多いので、いわゆる「感想文」との違いを意識することでしょうか。自分の感想だけを書いたり、あらすじを書いたりするのとは違い、あくまで伝えたい相手のことを思い浮かべながら、伝えたいことを書いていただければと思います。そもそも文字数が少ないので、あらすじを書く余地自体が少ないかもしれません。
――過去の入賞作品を見ることはできますか?
はい、入賞した推薦文はオンラインでご覧いただけます。部門別にまとめているので、該当する学年ごとに推薦文の実例を見ていただけます。選考委員のメッセージも載っていますので、これから書こうとしている子どもたちにも、指導される先生にとっても、具体的な参考になると思います。作品集としてまとめた小冊子のPDFもダウンロードしていただけますので、タブレットなどでデータごと子どもたちに共有いただくのもよいでしょうね。

2024年度(第4回)の入賞者・入賞団体のまとめページはこちら
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/okiniiri/winners/
――どんな本を選べばよいか、参考になる資料はありますか?
今ご紹介した、オンライン上にある「お気に入りの一冊ライブラリー」をご覧いただくと、これまでに実際に推薦された本をその中から探すことができます。また実際の推薦文を紹介していますので、最初にどんなふうに書いているのかを、先生と子どもが一緒に確認してから、実際に探したり書いたりしてみるのもよいかもしれません。
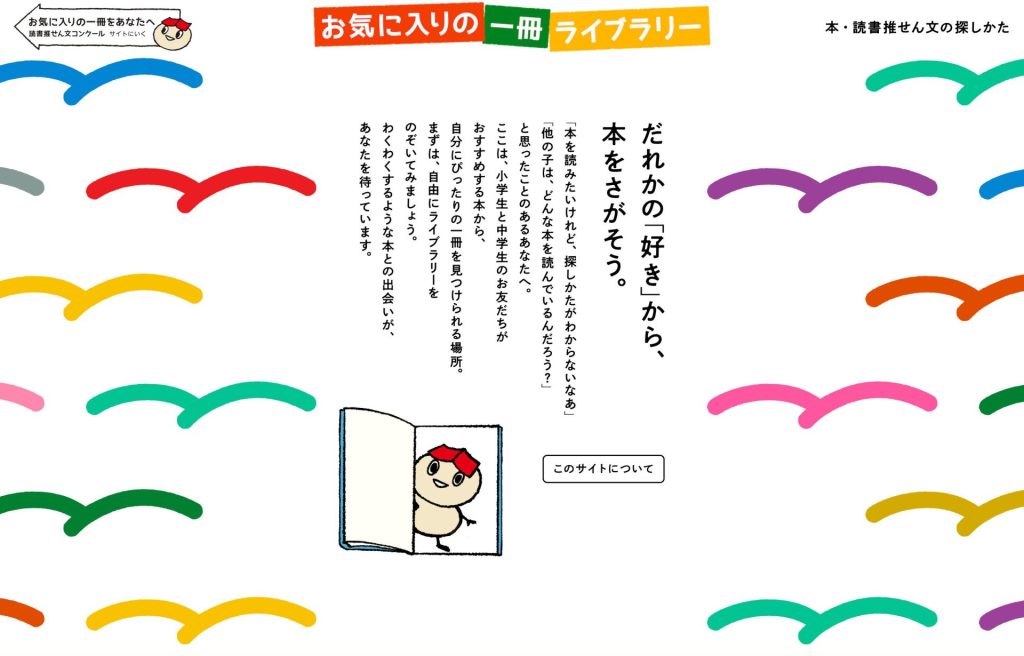
「お気に入りの一冊ライブラリー」はこちら
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/okiniiri/library/
以上、今回は「読書推せん文コンクール」の選考ポイントと参考事例について、主催団体である博報堂教育財団の中馬常務理事にお話を伺いました。小学生でも全校で参加できる「読書推せん文コンクール」。今年も4月から応募書類の配布が始まっているので、ご関心ある先生方はぜひご参加ご検討ください。
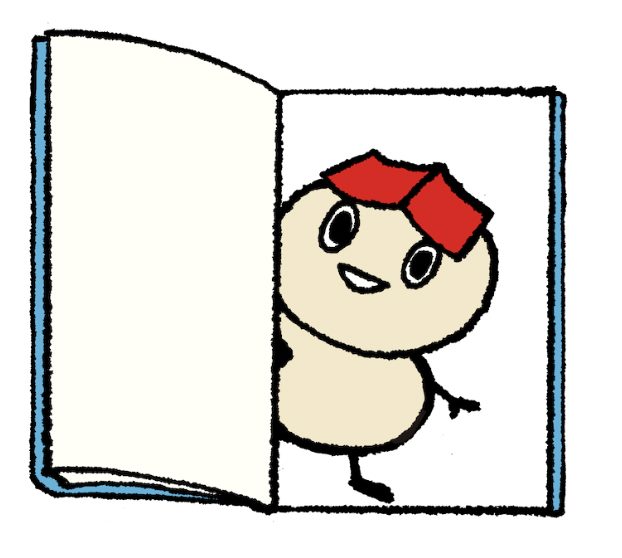
短い文章なので、学年や得意/不得意に関係なく全校で参加できるね。「この人にこれを伝えたい!」という素直な熱い気持ちを待っているよ!
――コンクールキャラクター:もちぽん
コンクールの詳細情報は公式サイトでご確認ください
↓↓↓
リンク先:https://www.hakuhodofoundation.or.jp/okiniiri/#top
次の記事では「読書推せん文コンクール」に参加することで期待される、学校教育としての具体的なメリットや、導入にあたってのアイデアについて、さらに詳しくご紹介いたします。こちらもぜひお読みください!
取材・文/田口まさ美(Starflower inc.)

