「生き物好き」を育む先生の取り組み方【理科の壺】

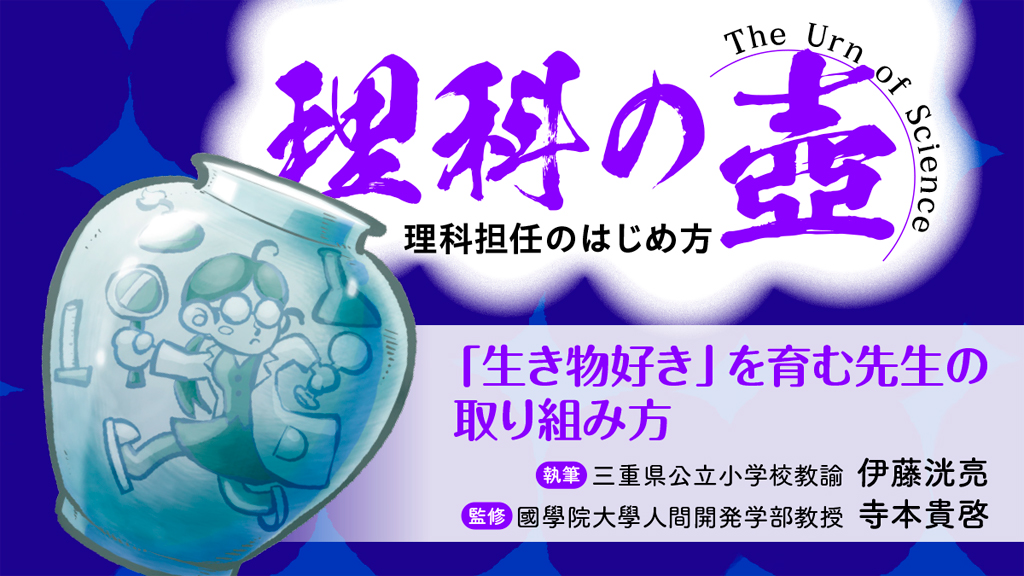
子どもたちは生き物をよく捕まえてきます。一方で、生き物にあまり触れてこなかった子どももいます。理科としては多くの子どもたちに生き物にも関心をもってもらいたいわけですが、その手立ての最適解が分からない、というのが困ったものです。先生自身もあまり生き物に関わってこなかったということもあるかもしれません。今回は、子どもの「生き物好き」を育む先生の取り組み方のアイデアです。まずは、先生が生き物好きになって、子どもたちにも広げていただきたいです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/三重県公立小学校教諭・伊藤洸亮
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
はじめに
みなさんは、日々の教育活動の中で、子どもたちの「生き物好き」を育むためにどのような工夫をされていますか? ご自身があまり生き物が好きではないために、生き物を扱った授業では、教科書に載っている方法だけ行っている、という先生もいらっしゃるのではないでしょうか。それは少しもったいないですね。
実は、特別な専門知識や経験がなくても、子どもたちの好奇心を刺激し、生き物への興味を深めることができるのです。そこで今回は、子どもたちの「生き物好き」を育むためのアイデアを、具体的な事例とともに紹介しています。生き物との触れ合いを通して、子どもたちが主体的に学び、発見する喜びを体験できるよう、少し取り組んでみませんか。
1.先生も一緒に学ぼう!生き物への苦手意識克服法
低学年の生活科では、1年生の「生きものとなかよし」や2年生の「身近な生き物の観察や世話」、中学年以降の理科では3年生の「植物の育ち方と生き物の観察」、4年生の「季節と生物」など、生き物を題材とする単元はたくさんあり、子どもも先生も植物や昆虫といった自然と触れ合う機会がたくさんあります。しかし、先生方の中には「専門的な知識がないから、上手く教えられる自信がない」という声を聞きます。ご安心ください。全てを完璧に知った状態で授業に臨む必要はありません。それよりも、子どもたちと同じ目線で「へぇ、そうなんだ!」と新しい発見を楽しむ気持ちがあることが大切だと考えます。
例えば、子どもたちから「この虫の名前は何?」と聞かれたとき、もしすぐには答えられなくても「先生も知りたいから、一緒に図鑑で調べてみよう!」と提案すれば良いのです。
そうやって、子どもたちと一緒に知識を広げていく姿勢が、子どもたちの学びを深めます。もちろん、事前に少しでも知識があれば、さらに深い学びにつながるのは事実です。具体的な生き物の名前まではわからなくても、「トンボの仲間」や「チョウの幼虫」など、大まかな情報でももっておくと、「さすが先生!」と親近感や好奇心を高めてくれます。
もし時間に余裕があるのなら、春休みやゴールデンウィークなどの長期休暇や普段の休み時間、放課後のちょっとした時間にでも、スマホやカメラを持って学校を散策し、季節や場所によって、よく見られる生き物を調べておくことをお勧めします。
また授業実践の前に自然観察をしておくことで、子どもたちが興味を持ちそうなポイントや、生き物に関する豆知識について準備ができたり、危険な個所の下調べ、指導への不安感を軽減できたりします。さらに、子どもたちと一緒に学ぶことで、先生自身も成長できます。「知らなかった!」という驚きを共有することで、子どもたちとの距離も縮まるでしょう。また、これらの体験的な記憶は本や図鑑で見ているよりも、とても印象に残りやすいので、何度も繰り返すうちに生き物について自然と詳しくなっていきます。

