「面白い!」は最高の動機づけ ~自分の足で歩く子どもを育てるために~

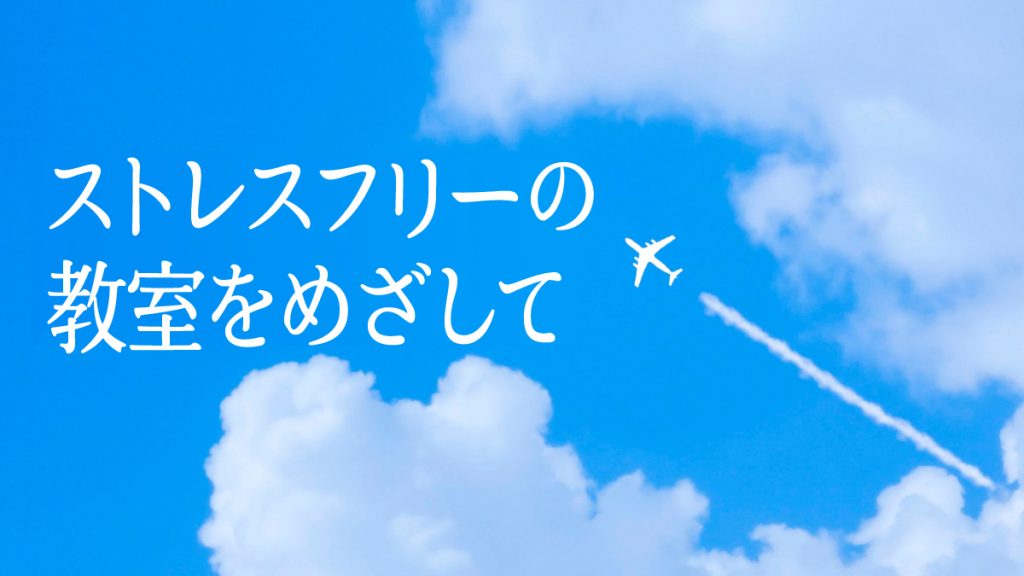
先生たちの子どもの頃を思い出してみてください。自発的な行動を起こす源は、「面白そう!」というワクワクした気持ちだったはずです。本章では、子どもの「面白い!」について、学級経営とのかかわりから考えていきます。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #20
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
目次
「面白い」は最高の動機づけ
「もっと分かるようになりたい」、「詳しく知りたい」、「上手にできるようになりたい」という気持ちを、人は誰しももっています。こうした気持ちが原動力になり、人は努力をしたり、何かに没頭したりして、その活動の面白さを実感していきます。こうした気持ちは、よく「やる気」と言われ、心理学では「動機づけ」とも呼ばれます。教師が子どもの行動をどのように動機づけるか、つまりどうやって子どもの「やる気を導くか」は大きなポイントであると言えるでしょう。アメリカの心理学者であるデシとライアンは、動機づけ(モチベーション)に関する研究を行い、そこから導かれた理論を「自己決定理論」として発表しました。この理論では、人が動機のない状態から自発的な行動に至るまで、どのような道筋をたどるのかについて示しています。
3種類の動機づけ
自己決定理論によれば、動機づけを、「無動機づけ」、「外発的動機づけ」、「内発的動機づけ」の3種類に分けて整理しています。
まず無動機づけとは、「自分の意思がなく、やる気のない状態で活動している状態」のことを指しています。この状態では、自分の存在や価値をポジティブに捉えることはむずかしくなります。
次に外発的動機づけとは、「何か他からの報酬を得るための手段として、ある行動を動機づけられること」を指しています。アメとムチに例えられることが多いです。例えば、「今度のテストで100点を取ったら好きなものを買ってあげる」などのご褒美が与えられるタイプや、「先生に叱られるから学級のルールを守る」などの罰を回避するタイプなどが挙げられます。いずれの場合も、行動そのものが目的ではなく、手段であることが特徴です。
そして内発的動機づけとは、「他からの報酬や罰に依存せず、活動そのものが楽しい、面白いと感じることで生じる動機づけ」のことを指しています。例えば、「校庭で虫の観察をしているうちにもっと調べたいという意欲が湧き、図鑑で詳しく調べる」「算数の難しい問題を解くことにやりがいを感じ、自力で解けたときの達成感を楽しむ」などが挙げられます。
自己決定理論では、より良い成果と行動の継続は、内発的動機づけが導くとしており、内発的動機づけを導くためには、①自律性(自分の行動を自分で決めることができる)、②有能感(自分の能力を実感することができる)、③関係性(他者のために行動したい)という3つの心理的欲求を満たす必要があると言われています。

