「できないことがダメなことではないよ」 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す! 「高校につながる英・数・国」の授業づくり #23】
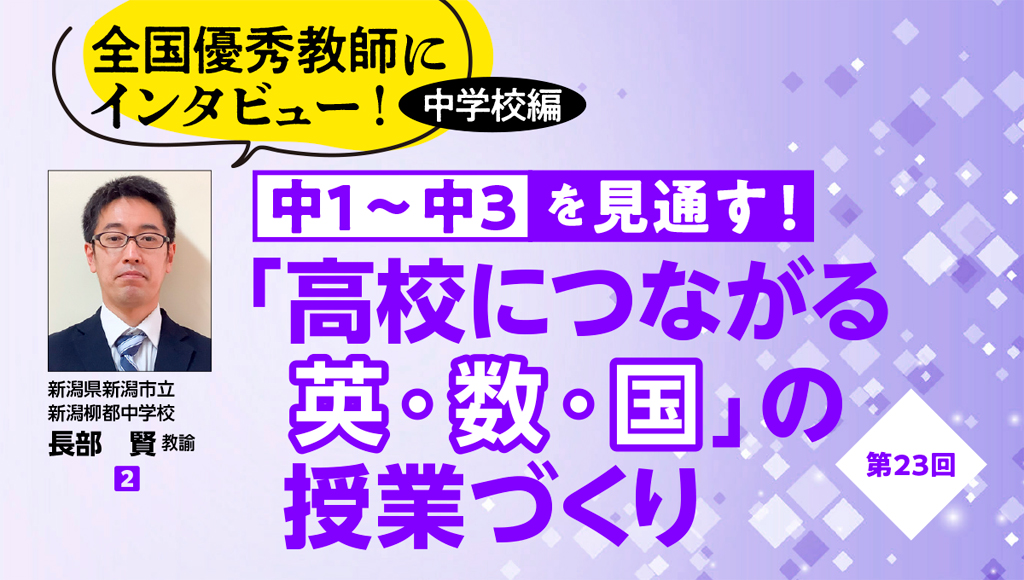
前回は、新潟市の授業マイスターである新潟市立新潟柳都中学校の長部賢教諭(数学)に、ご自身の授業づくりを象徴する実践事例を紹介していただきました。今回は、そのような授業の裏側にある、授業づくりの考え方について聞いていくことにしましょう。

目次
「単純に法則だけを教えても、子供たちに定着していかないな」
まず、長部教諭は数学の教員であるものの、自身が中学校の前半は数学が苦手な子供だったと話し、そこから次第に数学のおもしろさに気付いていく過程を話してくれました。
「私は中学校後半から高校にかけて、学校の教員になりたいと考え、その後、大学の数学科に入ったのですが、中学校時代には、5教科の中で一番苦手なのが数学で、最もテストで点が取れませんでした。それが中学2年の時の数学の先生が、とても分かりやすい授業をしてくれる方で、『ああ、こんなふうに学習すればよいのか』と思えるようになり、そこから次第に数学が好きになっていったのです。
それでも、まだ中学校時代にはそれほど得意と言えるほどでもなかったのですが、高校に入って自分で『なぜそうなるんだろう?』と原理を考えていくようになって、次第に数学のおもしろさにハマったというか、魅了されるようになっていきました。やがて、高校を出る時には数学科に進んで教員になろうと思っていたのです。そして、大学卒業時には、小学校の免許ももってはいましたが、採用試験も中学校の数学で受けて、数学の教員になりました。
ただし、実際に教員になってみると、最初の学校評価では、校内で評価が低いほうで、決して順風満帆に教員生活を過ごしてきたわけではありません。今から考えてみても、教科書の内容を教えることで精一杯でしたから、仕方ないという気もしますが(笑)。その後、異動した2校目の頃から、『単純に法則だけを教えても、子供たちがなぜそうなっているのか理解できなければ、定着もしていかないな』と思い始め、その頃から授業づくりを考えていくようになりました」
実は、こうした中学時代に数学が苦手だったことや、高校時代に「なぜそうなるんだろう?」と考えることで、数学のおもしろさにハマっていったということが、その後の授業改善の方向性にも関わっているようです。
「2校目以降で授業の在り方を考えるようになり、次第に課題を設定していくまでの導入場面で、『なぜ、そうなるのかな?』と子供たちが思って学習に入っていけるようにすることを、大事にするようになっていきました。私が一方的に授業を進めるのではなく、子供たちが主体的に学習を進めていけるようにしていくということです。例えば、『以前の学習ではこうだったけど、この学習はどうだろう?』と、既習とのズレを意識できるような問題を提示することから学習がスタートし、課題を設定し、学習を進めていくわけです。
そうした既習とのズレを生かした授業展開についても、先にお話をした通り、初任校の頃にはよく分かっていませんでした。しかし、経験を積んで3学年すべてを一通り教え、『ああ、こことここがつながっていくのか』と、3年間の学習全体の系統性が見えるようになってから、そのズレをどう生かして課題設定をしていくかが、より明確に見えてきたように思います」


