小1特別活動「1年1組 友達集会をしよう」指導アイデア

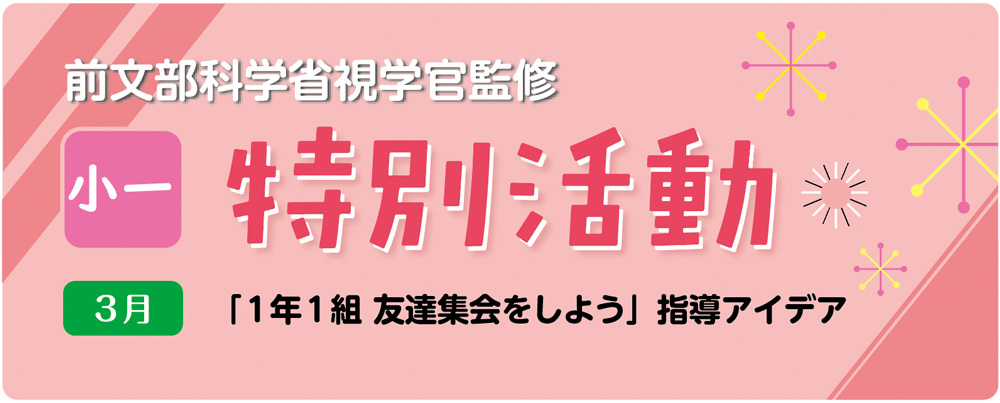
前文部科学省視学官監修による、小1特別活動の指導アイデアです。3月は、学級活動(1)「1年1組 友達集会をしよう」の実践例を紹介します。
執筆/鳥取県公立小学校教諭・氏橋 愛
監修/帝京大学教育学部教授(前文部科学省視学官)・安部恭子
鳥取県公立小学校校長・太田敦弘
目次
年間執筆計画
04月 学級活動(1) 学級会を始めよう!(学級会オリエンテーション)
05月 学級活動(2)ア 元気にあいさつ
06月 学級活動(2)ウ 上手な歯の磨き方~6歳臼歯は歯の王様~
07月 学級活動(3)ウ 楽しさ発見 学校図書館
09月 学級活動(1) わくわくハッピー係活動をしよう
10月 学級活動(2)イ みんな仲よくーふわふわ言葉とちくちく言葉ー
11月 学級活動(1) 1年〇組 ジャンボかるたを作ろう
12月 学級活動(3)イ きれいな教室~よりよい掃除を目指して~
01月 学級活動(2)エ 楽しい給⾷
02月 学級活動(3)ア もうすぐ2年生
03月 学級活動(1) 1年1組 友達集会をしよう
本実践のねらい
3月は学年を締めくくり、次の学年への準備をする時期です。この頃の1年生は小学校生活にもすっかり慣れ、学級・学校のことがよく分かるようになります。また、多くの活動を経験する中で、交友関係も広がり、みんなで何かをするよさや喜び、意義を感じ始めています。
今回の実践では、これまでの学校生活で経験した、楽しかったことやがんばったことなどについて振り返ることで、互いの成長を喜び合い、次の学年へ進級する意欲付けとなることを目指します。

