「指導と評価の一体化」とは?【知っておきたい教育用語】
授業では子どもに身につけさせたい力を明確にして指導の目標を設定し、実現のための手立てを講じます。その結果、指導目標がどの程度実現したかを評価し、その状況に応じてまた指導を工夫します。つまり、指導→評価→指導→…を繰り返して、子どもの成長を促していきます。いま、子どもの発達状態に応じた指導を工夫することや、個別最適な学びおよび協働的な学びの実現が学校教育に求められています。そこで注目されているのが「指導と評価の一体化」です。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴
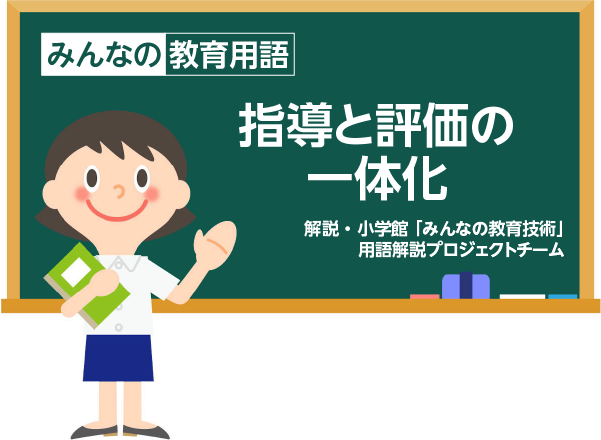
目次
指導と評価の一体化とは
【指導と評価の一体化】
学習指導と学習評価を別々のものとして扱うのではなく、「指導した状況を評価し、その結果を次の指導に生かし、その成果を再度評価していく」というように、指導と評価が循環しているイメージで捉える考え方を指す。
学習指導は、目標→指導→評価→改善→新たな目標→…といった、いわゆるPDCAサイクルと同様の過程を経て、よりよいものになっていくと考えられています。現行の学習指導要領では、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体的に学習に取り組む態度」の3つの資質・能力をバランスよく育成することの重要性を示しています。
各教科・領域の指導目標は、この3つの観点でそれぞれ設定されています。それらがどの程度実現されているかを評価するための拠り所として評価規準を設け、子どもの学習状況を3つの観点から把握し、十分な状態であるか、不足している状態でないかなどを教員が判断し、より高次な状態に導くために指導の工夫を講じます。
学習指導要領には、教科・領域ごとに目標と内容、指導の方法例などが「解説」として編集され、学校は、この「解説」を拠り所として指導を行うというしくみになっています。一方、評価規準の設定にあたっては、「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」が国立教育政策研究所から教科・領域ごとに出されています。
学習評価の重要性
学習指導要領では学習評価の重要性を次のように示しています。
児童(生徒)のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し、学習したことの意義や価値を実感できるようにすること。また、各教科(・科目)等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して、学習の過程や成果を評価し、指導の改善や学習意欲の向上を図り、資質・能力の育成に生かすようにすること。
文部科学省(ウェブサイト)「4.教育課程の実施と学習評価」
学校では日々の授業で子どもの学習状況を評価し、その結果を子どもの学習活動や教師自身の指導改善に生かしていくことが大切です。学校における教育活動は、学校組織として意図的・計画的に行い、その質の向上がそのまま子どものより望ましい成長へとつながります。
学校として評価活動を機能させること、つまり、「評価の結果によって次の指導を改善し、さらに新しい指導の成果を再度評価する」という、まさに「指導と評価の一体化」が日々実現している組織であることが求めれられているのです。
子どもは、評価によって学習の意義や、その結果として自己の成長を自覚することで次の学習意欲を高揚させます。指導と評価が一体的に行われることで、主体的・対話的で深い学びのある授業、教育活動が実現されるといえるのです。

