「教職調整額」とは?【知っておきたい教育用語】
教員の職務は、子どもへの教育指導・支援、学級事務や学校全体に関わる分掌の仕事、保護者や地域への対応など多岐にわたり、出勤して退勤まで途切れることなく続きます。授業時間と定例の会議時間以外の時間調整は、教員の自発性・創造性によるところが大きいので、日常的な時間外勤務の時間を規定することは難しいとされています。このような教職の特性を踏まえ、いわゆる「残業手当」に相当する手当はどのように考えられ、変わっていこうとしているのでしょうか。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴
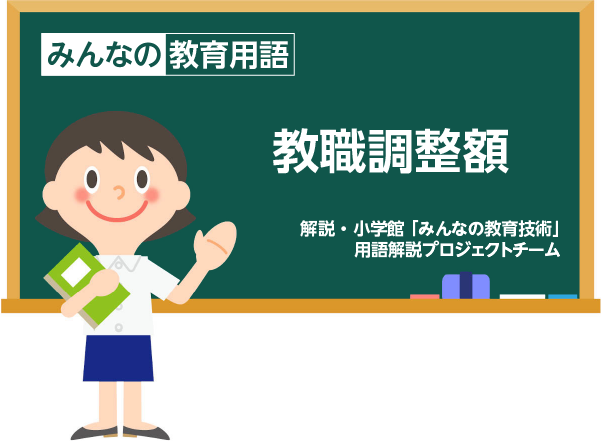
目次
教職調整額とは
【教職調整額】
「公立の義務教育諸学校等の給与等に関する特別措置法」、いわゆる「給特法」と呼ばれている法律の第3条に「教育職員には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない」と示されている。
まず、教員の時間外勤務についての取り扱いの変遷について考えてみましょう。
戦後の公務員の給与制度の改革(昭和23年)では、教員の職務時間を数値で表すことの難しさから、他の公務員に比べて有利に設定することで、超過勤務手当は支給しないとされました。しかし、社会の変化に伴って、学校教育に求められること、つまり教員が果たすべき役割が多くなり、超過勤務が増え、多くの都道府県で時間外勤務手当の支給を求める声が社会問題化しました。これがいわゆる「超勤問題」です。
国は昭和41年に1年かけて教員の勤務実態調査を全国で実施しました。その結果を踏まえて昭和43年には、教職の特性を踏まえて月額給与の4%(100分の4)に相当する教職特別手当を支給する「教育公務員特例法の一部を改正する法律」案を閣議決定し、国会に提出しましたが結果的には廃案となりました。
しかし、学校現場では、正規の勤務時間を超えて職務に当たる教員がいて、その時間も増えるという実態が続きました。そのため、国家公務員の労働基本権に基づく人事管理等を司る人事院は、教員の勤務状態に照らし、教職調整額を支給する制度を設けて、超過勤務手当を支給しないことを国に提言しました。この提言を受けて、政府は「給特法」案を国会に提出し、昭和46年に制定。その翌年から施行され、現在に至っています。
こうして、教員の職務の特殊性に応じた教職調整額として、一律に給料月額の4%が支給されることになっています。
校長が教員に命ずることができる時間外勤務
教員は教職調整額を支給されることで、現在だと7時間45分の正規の勤務時間外に働いた分の手当を受けているということになります。しかし、次の4つの職務については、校長が当該の教員に時間外勤務として命じることができるようになっています。
①校外実習その他生徒の実習に関する業務
②修学旅行その他学校の行事に関する業務
③職員会議に関する業務
④非常災害の場合、児童生徒の指導に関して緊急の対応を必要とする場合等の業務
宿泊を伴う移動教室や、修学旅行などの行事で子どもたちを引率する場合、日常の勤務時間を超えて指導することになります。このように、上記の合理性のある時間外の職務については、相当の手当が支給されるしくみも整えられています。

