横田 愛幼児教育企画官⑵|幼児期には遊びを通して、小学校の生活や学習の基盤となる資質・能力を育むことが重要 【教育キーパーソンにインタビュー! 令和の教育課程「その課題と未来」#12】
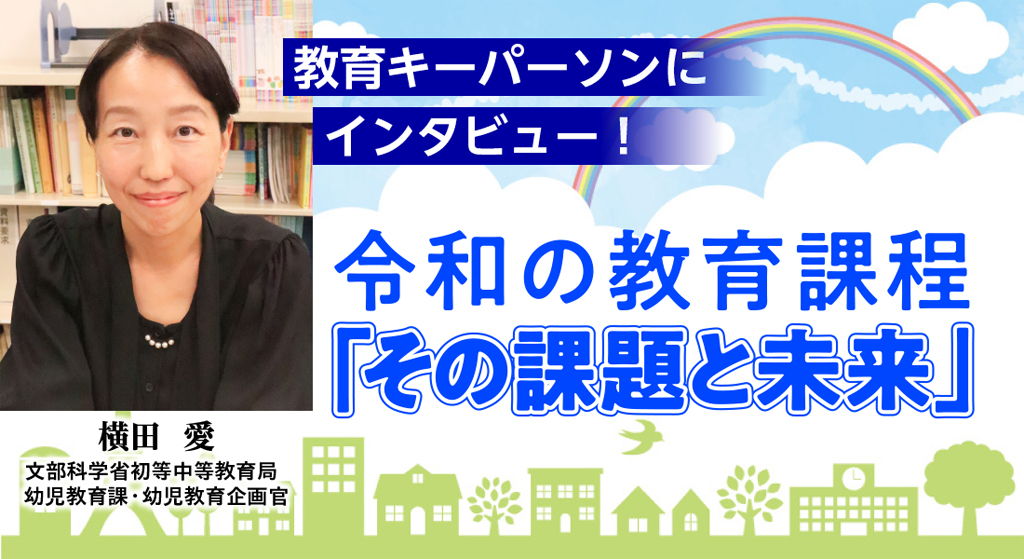
前回は、今後の幼児教育の教育課程、指導、評価等の在り方に関する有識者検討会の最終報告について、事務局担当者である文部科学省初等中等教育局幼児教育課の横田愛幼児教育企画官に、資料も示していただきながら第1章について概説をお願いしました。今回は第2章の前半について概説をしていただきます。
目次
近年の幼児の遊び・生活の変化や幼児教育の成果・課題等
横田幼児教育企画官は、第2章では、第1章で示されている幼児教育の基本的な考え方に照らし、近年の幼児の遊び・生活の変化や幼児教育の成果・課題等について、重要な指摘がなされているとし、次のように概説してくれました。
「第2章 幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく教育活動の成果と課題等の1.幼児教育の基本に関する事項の⑴身体の諸感覚を通した豊かな体験では、前回ご紹介したように、『幼児期は、幼児自身が自発的・能動的に環境と関わりながら、生活の中で状況と関連付けて(必要な能力や態度などを)身に付けていく時期』であり、『幼児が身体の諸感覚を通して人やものなどの環境と主体的に関わり、多様な体験をすることができる機会を保障すること』が必要とされている一方で、家庭や地域においては、そのような体験を十分に確保することが困難になっていることが指摘されています。近年、幼児の遊びや生活にも変化が生じ、外遊び機会の減少、インターネット利用の低年齢化、スマホ・タブレット端末などによるゲーム時間や動画の視聴時間の増加、子供同士の交流機会の減少なども挙げられているところです。そのため、幼稚園、保育所、認定こども園(以下、「幼児教育施設」)において、『幼児が自由に伸び伸びと遊びながら、様々な人やもの、自然や文化等で直接的・具体的に触れて関わり、豊かな体験をする機会を積極的に設けていくことが一層必要となっている』ことが示されています。
また、⑵自発的な活動としての遊びでは、『自発的な活動としての遊びは、幼児期特有の学習』であり、幼児期は『知識・技能を教え込む』のではなく、『遊びを通して楽しいと感じる多様な体験をしながら、小学校以降の生活や学習の基盤となる資質・能力を育んでいく』ようにすることが重要であることが示されています。この幼児期の遊びを通した学びと小学校以降の各教科等の学習のつながりは、幼保小の先生方においてもなかなかイメージをすることがむずかしいとされているところです。この点、最終報告では、幼児期の生活・遊びと小学校の算数などとのつながりを例として示しています。具体的には、幼児は『収穫した野菜の大きさや集めた木の実の量などに驚いて思わず大きさを比べたり、数を数えて友達と同じ数ずつ分け合ったり、積み木や空き箱、木の枝など、それぞれの形の特徴を捉えながら見立てたり、イメージに合わせて形を作ったりすることもある。このような直接的・具体的な体験は、算数の数量や図形などについての基礎的・基本的な概念の形成や性質などを理解する上で大きな支えとなるものである』こと、『そうした学習の中で得ていく知識・技能等は生活と遊離したものとならず、子供の自発的な知的欲求の対象となり、資質・能力の育成につながっていく』ことなどが示されています。幼保小の円滑な接続に取り組むためには、幼保小の先生方に、幼児期の遊びを通した学びと小学校以降の各教科等の学習のつながりを理解していただくことがとても重要です。そのため、文科省では「幼児教育と小学校教育がつながるってどういうこと?」を作成し、幼児期の遊びと小学校1年生の全教科等とのつながり、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関係についても詳細に解説をしておりますので、そちらも併せてご覧いただけたらと思います(資料1参照)。
【資料1】「幼児教育と小学校教育がつながるってどういうこと」
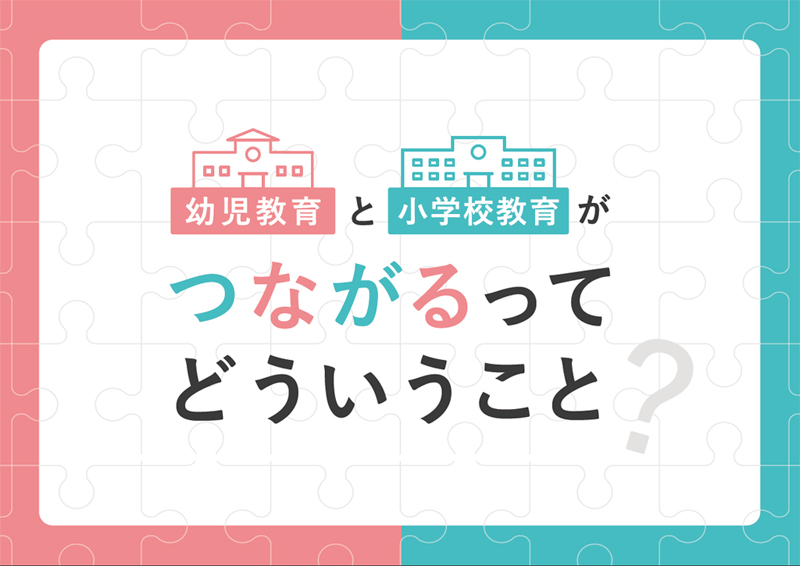
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/mext_02697.html
続けて、最終報告では、一部の幼児教育施設においてはSNSなどからの偏った情報やそれらに影響を受けた一部の保護者のニーズなどを優先し、ややもすると、文字や数量の機械的暗記や一方的指導など幼児の発達にふさわしくない教育活動が行われていたり、保護者をはじめ社会においては、幼児教育施設はただ遊ばせていたりするだけとの誤解もあるとの課題が指摘されました。保護者の皆さんには、幼児期の遊びの重要性や幼児教育施設の先生方が遊びを通して子供たちに必要な資質・能力を育むため、日々尽力されていることについて知っていただきたいです。子供たちは遊びながら様々なことを感じたり、気付いたり、考えたり、試したり、工夫したりなどして、成長していきます。子供たちが自ら進んで遊ぶことや遊びに夢中になる経験をたくさんすることが、小学校以降において主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことにもつながると考えます。文科省では、幼児期の発達の特性や幼児期にふさわしい教育の在り方について、一層の普及・啓発に取り組んでいきたいと思います。
そのほか、⑶幼児教育において育みたい資質・能力、⑷「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」、⑸幼児理解に基づいた評価では、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(以下、「3要領・指針」)において、『幼児教育において育みたい資質・能力…が、小学校以降の教育において育む資質・能力と系統的に明記された』ことを受け、その成果と課題について示しています。
例えば、幼児教育において『小学校教育との接続を意識した実践が行われるようになってきた』、『幼保小相互の連携・協働の意識が高まるとともに…相互理解が深まっている』といった成果が見られます。一方、幼児教育関係者からは『資質・能力と5領域のねらい及び内容、“幼児期の終わりまでに育ってほしい姿” との関係を理解して実践につなげることがむずかしい』という声があったり、実際に『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』に当てはまるよう、取り出し指導が行われているといった課題も指摘されたりしています。
そうしたことについて、今後、『一層の理解・啓発』や『より実践的な調査研究を進め、充実につなげていく』としています。

