学習指導要領【わかる!教育ニュース #55】
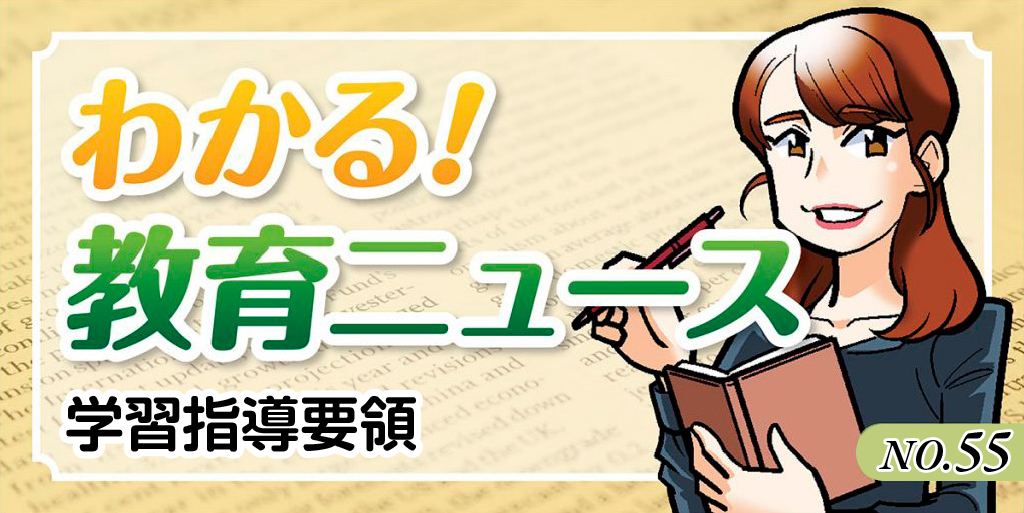
先生だったら知っておきたい、様々な教育ニュースについて解説します。連載第55回のテーマは「学習指導要領」です。
目次
次期学習指導要領に関する議論の柱の1つは「授業時数を増やさない」
どの学校でも一定水準の教育ができるよう、教えるべき最低限の内容を示した学習指導要領は、社会の変化を踏まえ、おおむね10年に1度改められます。前回の改訂から7年。次の指導要領がどうなるか、関心が高まっています。
これからの教育課程や学習指導などのあり方を議論してきた文部科学省の有識者会議がこのほど、次期指導要領に関する議論のベースになる論点をまとめました(参照データ)。様々な角度で論じていますが、柱の1つは、今以上に授業時数を増やさないよう提案したこと。学ぶ内容や授業時数を増やしてきた近年の改訂の見直しです。
まず現状を踏まえて、今後の学校教育に求められることを説きました。不登校、特別支援教育の対象、外国籍など、子供の多様性が顕著になったと指摘し、多様化した子供たちを包み込み、個々の強みを伸ばし、資質や能力を育むことが重要だとしています。
資質や能力を育む視点として「主体的・対話的で深い学び」を掲げた現行の指導要領については、「知識の質」という考え方を提起した、と一定の評価をしています。ただ、指導要領に曖昧な言葉があって分かりにくい面があること、教員の多忙化やなり手不足などの問題点があると指摘。現場の負担感が大きいという懸念に向き合い、過度な負担感を生じさせない仕組みを検討するよう促した上で、「総授業時数は、現在以上に増やすことがないよう検討するべきだ」と訴えました。

