廊下にて……全員の作品を掲示する意味って何?【連載|管理職を楽しもう #10】
- 連載
- 管理職を楽しもう

前例踏襲や同調圧力が大嫌いな個性派パイセン、元小樽市立朝里中学校校長の森万喜子先生に管理職の楽しみ方を教えていただくこの連載。いま管理職の先生も、今後目指すかもしれない先生も、自分だったらどんなふうに「理想の学校」をつくるのか、想像しながら読んでみてくださいね。
第10回は、<廊下にて…>です。
執筆/元小樽市立朝里中学校校長・森 万喜子
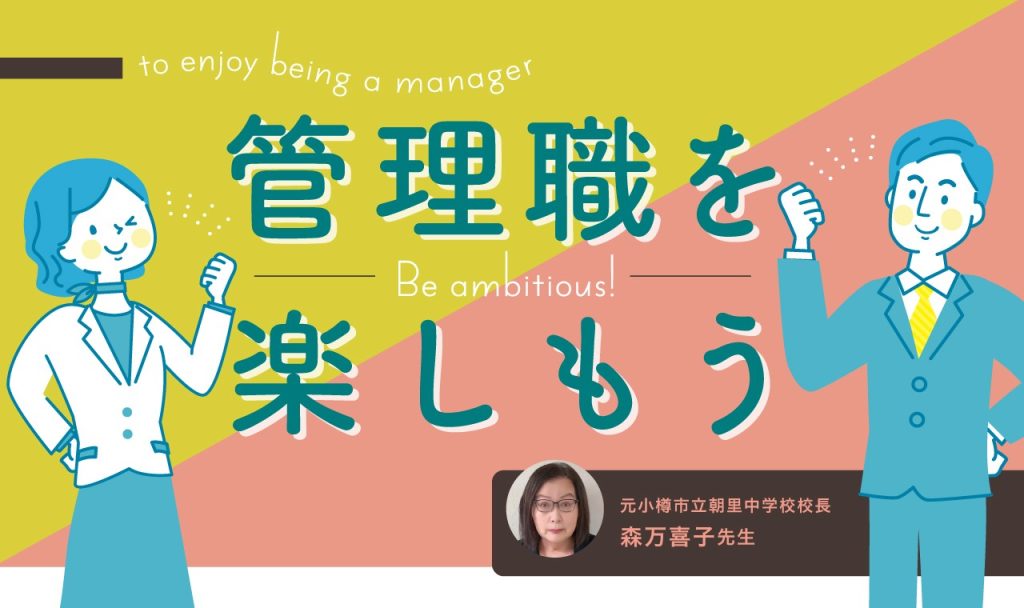
目次
9月です
みなさんこんにちは。夏休みが終わり、子どもたちの笑顔や歓声が聞こえる日常が始まっていることでしょう。多くの方が言及されているように、夏休み明けの子どもたちの心身の健康が気がかりです。追い詰められていたり、絶望していたり、孤立していたりしていないか、事務的なお仕事や提出物を大人も抱えているこの時期ですが、なにより子どもたちの安心安全を第一に気にかけたい、そんな9月です。
良い学校の見分け方
20年近く前、「わが子の教育に関心の高い親御さん向け」雑誌がいくつか創刊されました。当時は自分の子どもも小学生だったこともあり、時々買って読んでいました。私は地方に住んでいるので、いわゆる「お受験」は選択肢にない。それらの雑誌は家庭で子どもの知的好奇心を伸ばすことの記事が多かったようでした。リビングのテーブルで勉強をするとか、家庭に地図や子ども向け百科事典や辞書をすぐ手に取れるように置いておこうとか、そんな内容です。ある時、その雑誌の中に「お子さんが入学予定の学校がこんなだったら要注意」というような記事があり、職業柄気になって読んでみました。そこには、学校に行って、まずごみが落ちていたり、壊れた場所がそのままだったり、落書きが消されていなかったりするような学校はNG、あと、廊下の掲示物も注意して見ましょう。期限切れの告知ポスターがいつまでも貼られているとか、画びょうが1個外れて、ひらひらしているような学校は要注意ですよ! と書かれていました。なるほど。
さっそく、校内を見てみると……ああ、結構ありました。まずは「いつ書かれたの? 貼られたの?」という古いポスターが何か所も。学校の大人たちって、子どもたちが作ったものは外したり捨てたりしづらくて、何年も貼り続けてしまうことが多いのです。でも、児童会・生徒会の任期が変わったら外したほうがいいでしょう。特に気をつけなくてはならないのは、事前の働きかけが足りないと、禁止命令文だらけになることです。権力は、もったら振り回したくなっちゃうのが人間の性。だけど「〇〇禁止」「△△するな」に囲まれているのってあんまり居心地がいいもんじゃないですよ。
いじめ防止キャンペーン週間などに生活委員会がポスターを描いて貼ると、学校中に「いじめはダメ!」「いじめをやめよう」のポスターがあふれかえる。同様に、教職員の交通事故や飲酒運転などの不祥事が起きると、教育行政の指導のもと、交通安全遵守キャンペーンとか飲酒運転撲滅強化月間などが設定される。各学校での取組も求められるから、職員室や職員玄関などに「飲酒運転をなくそう」というステッカーやポスターをたくさん貼っている学校もある。それを見た子どもたちに「先生方ってお酒を飲むの? 飲酒運転するの?」と尋ねられたことがあり、びっくりしたのだけど、禁止命令文が多い学校は「日常的にそういう問題が起きている学校なのかな……」と思うのだと再自覚しました。通学路にある立て看板「非行の芽を摘もう」「暴力追放」なんかも、たくさんあると「この地域、治安悪いのかな……」なんて思ってしまうのです。ポスターを貼ったり標語をつくったりすることは学校でよく行われているけど、「本当に効果あるの?」と問い直すことも必要なんじゃないかしら。特に手間暇かけて自作する場合、ターゲットは誰? どんなふうに行動変容をしてほしいの? 効果的な表し方は? なんて、つい美術科教員の私は考え、イージーな掲示物作戦に疑問を感じてしまうのです。

